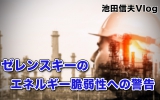今週のアップデート — 原発再稼動を考える(2014年2月10日)
アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
原子力規制委員会は何を審査しているのか
1)【本記】 2)【要旨】 3)【資料】
アゴラ研究所は、2月4日にインターネット放送「言論アリーナ」で「原子力規制委員会は何を審査しているのか」という放送を行いました。
出演者は、諸葛宗男(もろくず・むねお)元東京大学公共政策大学院特任教授・NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事、澤田哲生・東京工業大学助教、池田信夫・アゴラ研究所所長。原子力規制委員会の活動の問題点を議論しました。
その内容を、報告、要旨、さらに諸葛氏の作った資料に分けて公開します。
同委員会の活動の問題は、適正手続きを省略して、原子力発電所の設備についてバックフィット(法の遡及適用)を行う問題の多いものです。これを分析しています。
今週のリンク
1)(映像)原子力規制委員会は何を審査しているのか
今回記事で取り上げた言論アリーナの更新です。GEPRトップページ上部に掲載します。
原子力規制委員会が法律上あいまいで、政省令上に明確な規定のない原発へのバックフィットを行っています。その根拠がこの文章ですが、委員会の田中俊一委員長のメモにすぎません。こうしたあいまいなもので国の行政が動く、おかしな状況になっています。
池田信夫アゴラ研究所所長の論考。2月9日に投開票が行われた東京都知事選は舛添要一氏が当選しました。原発ゼロを掲げた細川護煕氏、宇都宮健児氏は落選しました。リスクゼロにするその騒ぎの無意味さを、指摘しています。
ブルームバーグ・ニューエナジーファイナンス。米国事情を紹介するリポート(英語)。米国ではわずか5年前に比べて、エネルギーの消費効率が向上し、二酸化炭素排出量が減少しており、さまざまな最新技術の影響で、過去何十年も続いてきたエネルギーを取り巻く環境が変化しつつあることを伝えています。
日経2月7日記事。菅義偉官房長官は7日の閣議後の記者会見で、高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)の実用化に向けた目標や組織の見直しを示唆しました。月内にも閣議決定するエネルギー基本計画に関し「もんじゅを含め徹底的に議論し、与党とも調整して決定する」としています。国は1兆円の支出をしましたが、その見直しは画期的なことです。

関連記事
-
EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月
-
サプライヤーへの脱炭素要請は優越的地位の濫用にあたらないか? 企業の脱炭素に向けた取り組みが、自社の企業行動指針に反する可能性があります。2回に分けて述べます。 2050年脱炭素や2030年CO2半減を宣言する日本企業が
-
美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった
-
2025年5月15日、ロイター通信は「中国製インバーター(太陽光発電の電気を送電系統に接続する装置)から、製品仕様書に記載されていない通信機器が発見された。遠隔操作によってインバーターを停止させ、送電を遮断することも可能
-
台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ
-
厚生労働省は原発事故後の食品中の放射性物質に係る基準値の設定案を定め、現在意見公募中である。原発事故後に定めたセシウム(134と137の合計値)の暫定基準値は500Bq/kgであった。これを生涯内部被曝線量を100mSv以下にすることを目的として、それぞれ食品により100Bq/kgあるいはそれ以下に下げるという基準を厳格にした案である。私は以下の理由で、これに反対する意見を提出した。
-
ゼレンスキー大統領の議会演説は、英米では予想された範囲だったが、ドイツ議会の演説には驚いた。 彼はドイツがパイプライン「ノルドストリーム」を通じてロシアのプーチン大統領に戦争の資金を提供していると、かねてから警告していた
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間