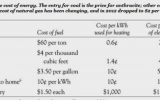「大飯原発判決」これだけの誤り
(産経新聞「正論」 転載)
5月21日、大飯原発運転差し止め請求に対し福井地裁から原告請求認容の判決が言い渡さ れた。この判決には多くの問題がある。
専門技術知識欠いた判断
第一に論理の乱暴さである。判決は、「(新しい)技術の危険性の性質やそのもたらす被害の 大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じ た安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよい だけ」とし、危険性を一定程度、容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかという 議論を切り捨てている。
だが、まさにその「危険の性質と被害の大きさに応じた安全性」を確保するため原子炉等規 制法が改正され、福島第1原発事故の反省に立って規制基準を厳格化したうえで原子力規制 委員会が新基準適合性を審査しているのだ。
判決は「人格権」の保護という法理から裁判所は直接的に危険性の有無を判断できるとし、 「行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない」として規制委の判断は無関係 だと言う。
しかし、福島事故後に改正された新炉規制法は「国民の生命、健康及び財産の保護」を法目 的に謳(うた)い、「人格権」自体を保護するための法律であることを明確にしている。判決 はこの点を全く無視して、あたかも裁判所のみが人格権保護の役割を持っているかのような 態度を取る。そのうえ、炉規制法に基づく新規制基準の適否について評価もしないまま、原 発の危険性について独断的説示を行っている。しかも、その検討内容はずさんだと言わざる を得ず、判決後に専門家からさまざまな技術的誤りを指摘する批判が出ている。
こうした批判は事前に予想していたとみえ、判決は「(人格権の法理)に基づく裁判所の判断 は…必ずしも高度の専門技術的な知識・知見を要するものではない」と予防線を張っている。 専門技術的な知識に基づく規制委の規制基準と必ずしも専門技術的な知識に基づかない規制 基準が二重に存在することになるという点について、判決は何も語らない。
「ゼロリスク」求めた愚
第二に「危険性」と「安全性」の定義を明確にしていないため、判決自体も混乱しているこ とだ。前述の通り「安全性が保持されているかの判断をすればよいだけ」と自ら述べつつ、 その後で「かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべ き」としている。判決はこの二つの議論を同義だと考えているようだが、誤りである。
裁判官が安全規制の本質を理解していない証左だろう。原子力を含む全ての技術に危険性が 存在することを所与のものとして、その危険性が顕在化する確率を最小化し、顕在化した際 の被害を最小限に食い止める対策を施すのが安全規制の根本的な考え方なのだ。
判決に際しては、「危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべき」ではなく、差し 止め請求を受けている原子力事業者が、リスク(危険が顕在化する確率とその際の被害の大 きさ)を最小化するため適切かつ十分な対策を取っているかどうかが、判断の対象とされる べきなのである。
この本質論を裁判官が理解できない限り、「ゼロリスクでなければ原発を動かすべきではない」 という一見尤(もっと)もらしい判決が今後とも増える懸念がある。それを避けようとすれ ば、原子力事業者は訴訟で実質ゼロリスクを証明することが必要となりかねない。すなわち、 これは「原発を動かしたければ、原子力事業者は再び安全神話を語って世の中を説得せよ」 と求めるに等しい判決なのである。
累は全てのインフラに及ぶ
第三は、本判決というより、訴訟の構造問題とでもいうべきものだ。つまり、原発のみなら ず全てのインフラは何らかのリスクを有していると同時に、公益的な利便も提供している。 インフラに隣接する住民が人格権に基づいて当該インフラの運転差し止めを求め、裁判で、 その請求が認容された場合、インフラの機能は停止し公益的な利便も失われてしまう。
裁判所は、具体的な事案に限定して局地的な解決を判示することしかできない。公益的な利 便を維持するために何が必要になるかを考える必要も責任もない。インフラ機能停止によっ てもたらされる混乱や公益の喪失は、行政にそのしわ寄せがくることになろう。
判決を下す前に、それによって予想される混乱や公益の喪失をカバーするための行政との調 整が行われるような制度的な仕組みはない。であれば、判決を行う裁判官の良識に頼るしか ない。
今回の判決は、電力需給問題、電気料金、温暖化ガス排出問題などは原発の危険性に比べれ ば取るに足りないかのごとき扱いをしており、世間の喝采を受けている。しかし、私から見 れば、本判決は個別的請求に対する答えでしかないのだという防壁を築きながら、一方で公 益の喪失との調整の必要性については、想像力が遠く及んでいないものでしかない。
(2014年6月9日掲載)

関連記事
-
原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。
-
小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。
-
「原発は危険だ。だからゼロに」 — 菅元首相の発言から考える(上)で示された菅氏の発言を、どのように解釈するべきであろうか。そこからうかがうかぎり、菅氏はエネルギーについて、誤った、もしくは片寄った考えを数多く信じていた。もし首相として、それらに基づいて政策を決断していたのなら、おそろしいことだ。
-
不正のデパート・関電 6月28日、今年の関西電力の株主総会は、予想された通り大荒れ模様となった。 その理由は、電力商売の競争相手である新電力の顧客情報ののぞき見(不正閲覧)や、同業他社3社とのカルテルを結んでいたことにあ
-
(GEPR編集部) 原子力問題の啓発と対話を求める民間有志の団体である原子力国民会議が、12月1日に原子力政策のあり方について集会を開催する。原子力の適切な活用を主張する動きは、2011年の東京電力の福島第一原子力発電所
-
日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。
-
日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加し、馬英九総統と会見した。その報告。日台にはエネルギーをめぐる類似性があり、反対運動の姿も似ていた。
-
原子力の始まりが、政治の主導であった歴史を紹介している。中曽根氏の演説は格調高いが、この理想はなかなか活かされなかった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間