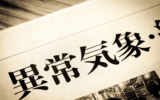アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」・映像
アゴラ研究所は9月27日、静岡市で第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を行った。その映像を公開する。
第1セッション
畑村洋太郎氏基調講演「東日本大震災が教えるもの」
討議「東海地震のリスクをどう考えるか」
~東海地震は本当に起こるのか、震災の経験を含め、その対策を考える~
2014年9月27日開催。出演・畑村洋太郎(東京大学名誉教授)/池田浩敬(常葉大学教授・社会環境学部長)/後藤大輔(鈴与・危機管理室長)/西澤真理子(リテラジャパン代表、リスクコミュニケーションコンサルタント)/司会・池田信夫(アゴラ研究所所長)
第2セッション
討議「エネルギーの選択と環境問題におけるリスクを考える」
〜直面する世界規模のエネルギー危機を分析する
2014年9月27日開催。出演・小川和久(静岡県立大学特任教授/特定非営利活動法人・国際変動研究所理事長/軍事アナリスト)/澤昭裕(21世紀政策研究所・研究主幹、国際環境経済研究所・所長)/佐々木敏春(中部電力静岡支店副支店長)/山本隆三(常葉大学教授)/司会・池田信夫(アゴラ研究所所長)
(2014年10月6日掲載)

関連記事
-
はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた
-
森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに
-
はじめに 北海道・釧路湿原のすぐそばで、大規模なメガソーラー建設が進められている。開発面積は約27ヘクタール、出力は21メガワット規模。すでに伐採・造成工事が始まり、国立公園・ラムサール条約湿地の隣にパネル群が並ぶ計画で
-
日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 新しい政権が発足したが、エネルギー・環境関連では、相変わらず脱炭素・水素・アンモニア・メタネーション等、これまで筆者が散々こき下ろしてきた政策を推進する話題で持ちきりである。そ
-
18世紀半ばから始まった産業革命以降、まずは西欧社会から次第に全世界へ、技術革新と社会構造の変革が進行した。最初は石炭、後には石油・天然ガスを含む化石燃料が安く大量に供給され、それが1960年代以降の急速な経済成長を支え
-
低CO2だとされるLNGの方が石炭よりもCO2排出量が多い、と言う論文がコーネル大学のハワースらのチームから報告されて話題になっている(図1)。ここではCO2排出量は燃料の採掘から利用までの「ライフサイクル」で計算されて
-
エネルギーは、国、都市、そして私たちの生活と社会の形を決めていく重要な要素です。さらに国の安全保障にも関わります。日本の皆さんは第二次世界大戦のきっかけが、アメリカと連合国による石油の禁輸がきっかけであったことを思い出すでしょう。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間