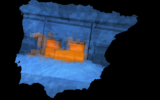今週のアップデート - 福島原発事故の教訓とは(2014年10月6日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」・映像
アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開しました。
東南海地震とエネルギーのリスクを専門家が集い、語り合っています。有意義な情報をなるでしょう。
2) 「東日本大震災が教えるもの」畑村洋太郎氏講演要旨【アゴラ・シンポ関連】
畑村洋太郎氏が、アゴラ・シンポジウムで講演しました。畑村氏は、東京大学名誉教授であり、「失敗学」の提唱者としても知られます。政府福島原子力発電所事故調査・検証委員会では委員長として報告をまとめています。平易な言葉で示される奥深い思想を、ぜひ参考にしてください。
3) 中川恵一・東京大学准教授に聞く 低線量被ばくの誤解と真実・2−福島で甲状腺がんは増えたか?
4) 中川恵一・東京大学准教授に聞く 低線量被ばくの誤解と真実・3−福島へのメッセージ
東大病院の中川先生に、低線量被ばくをめぐる質問に、分かりやすく答えていただきました。全3回で、2と3を公開します。
今週のリンク
1)震災伝承館
国土交通省東北地方整備局ホームページ。畑村氏の講演で言及された、災害復旧で成果を上げた機関の震災記録です。経験を継承するために、つくられた映像、写真サイト。経験を継承する情報が集まっています。
2)【再生可能エネルギーの買い取り制度】固定買い取り抜本改定へ 送電網の容量限界で、再生エネ普及に影響
共同通信9月26日記事。再エネが支援制度で普及しすぎ、電力会社が買い取りを拒否し、固定価格買い取り制度の見直しが検討されています。普及は成功したものの、補助金バブルが発生したことは、修正するべきでしょう。
3)再生可能エネルギー賦課金「3.12円/kWh、単年度総額2.7兆円」と政府試算
日本商工会議所ニュース。9月30日記事。経産省が、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度で、現在計画中の再エネがすべて稼働したとき、キロワットアワーあたり3.12円の付加金でも、単年度総額で2.7兆円になると試算しました。既存メディアは大きく伝えていませんが、大変な負担となります。(経産省資料・直近の認定量が全て運転開始した場合の賦課金等について)
東亜日報(韓国紙)9月30日記事。核拡散を恐れ、プルトニウム製造技術の拡散を抑える政策を常に取り続ける米国が、珍しく韓国の再処理を容認する意向のようです。
読売新聞10月5日社説。福島原発事故後の避難が一部解除されたことを受け、地域社会と生活の再建を呼びかける記事です。畑村氏の講演にあったように、災害対策には、こうした長期的視点が必要です。

関連記事
-
菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ
-
1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。
-
太陽光発電を導入済みまたは検討中の企業の方々と太陽光パネルの廃棄についてお話をすると、ほとんどの方が「心配しなくてもそのうちリサイクル技術が確立される」と楽観的なことをおっしゃいます。筆者はとても心配症であり、また人類に
-
筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。
-
来たる4月15日、ドイツの脱原発が完遂する。元々は昨年12月末日で止まるはずだったが、何が何でも原発は止めたい緑の党と、電力安定のために数年は稼働延長すべきという自民党との与党内での折り合いがつかず、ついにショルツ首相(
-
中国で石炭建設ラッシュが続いている(図1)。独立研究機関のGlobal Energy Monitor(GEM)が報告している。 同報告では、石炭火力発電の、認可取得(Permitted) 、事業開始(New projec
-
経済産業省は再エネ拡大を「燃料費の大幅削減策」として繰り返し訴えている。例えば2024年1月公表の資料では〈多大な燃料費削減効果を有する〉と強調した※1)。 2022年以来、未曽有の化石燃料価格高騰が起きたから、この局面
-
1. イベリア半島停電の概要 2025年4月28日12:30すぎ(スペイン時間)イベリア半島にある、スペインとポルトガルが広域停電になりました。公表された資料や、需給のデータから一部想定も含めて分析してみたいと思います。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間