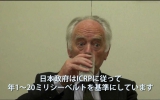福島産の食物を食べる3・地域の人々の思い

7 ・行政は規制をどのように考えていたのか
ⅰ)運営事務局よりこのシンポジウムの司会進行は地域メディエーターが担うことが説明され、司会者の開会宣言に続き、シンポジウムの位置付けと今日のシンポジウム開催に至るまでの経緯が説明された。まず、前述したこのシンポジウムに至る背景を説明され、その中で、「出荷制限値100Bq/kgは厳守しつつ、地元民の目安としての摂取制限値の検討(おとな1,000Bq/kg、子ども100Bq/kgの提案)」について、福島県職員やJA関係者からの事前質問の回答を紹介した。
〇福島県生活環境課、林業振興課、自然保護課からは、以下となった。これらの回答は、回答者個人の意見かつ摂取制限の指示を守る事をお願いするという前提であり県やJAとしての正式な見解表明ではない。
・摂取制限値はあっても良いと思える
(過剰に恐れすぎないように・無頓着になって食べ過ぎないように)
・自己責任で食べているので実態とあっていないのは確か
・基準値ではなく、自主的に測って食べることを進めるためにも目安が良い
〇福島県食品衛生課
・出荷制限値に沿うべきで、摂取制限値は必要ない
〇JA伊達みらい
出荷制限値は厳重に守られているので、あえて摂取制限値を設けることに疑問がある
これらに対して司会者より、関係機関の中でも摂取制限値の提案に対する考え方が2分していることが理解できるだろうという解説があった。
8 ・損失余命とは何か
次いで、福井県立大の岡敏弘氏から、損失余命についての解説が示された。同氏は、放射線のリスクは、これ以下なら安全(ここではリスクがないと考えられることであり、本来の定義とは使い方が異なる)という値が証明されていない。よって、どれだけ小さな放射線を浴びても何らかの危険があると考えて行動することが合理的である。
ところが、危なさには度合があるのでこれを考えて行動しないといけない。あまりにも小さなリスクを避けるために別の大きなリスクを引き受けることは合理的ではない。そこで、このリスクの比較が必要となり、その大きさを示すものが損失余命であり、異種の健康リスクの相互比較が可能になる指標であるとした。
具体的な解説として各年齢の損失余命が表に示され、実際例として、1kgあたり2,400Bq(出荷制限値の24倍)のイノハナ10gと5合のお米を使ってイノハナご飯を作って、お茶碗1杯食べた場合、損失余命は、7秒となる。これがどの程度のリスクがあるかを知るためには、他の食品と比較することが役に立ち(本来、リスク比較は慎重に提示する必要があるが時間の制約があった)、例えば、発癌性物質であるヒ素を含むヒジキ10gを含むご飯1合は、7~8分の損失余命となる。また、損失余命は食品に限らず他のリスクとの比較も可能で、自動車を10㎞運転するリスクを21秒とした。このような事実を考えて行動することが合理的となると話された。
ドブジンスキ氏から放射線の専門家としての意見は、放射線生物学の知見から考えると低線量被ばくの危険性はないと言う個人の強い信念を示しつつ、低線量被ばくのリスクの理解が学術的に難しく、その前段としてかつ科学的ではないが(低線量でのリスクを集団で定量的に考えるのは不確かさが大きすぎるとして)心理学的な手段として、他のリスクとの比較も容易で分かり易い損失余命という考え方に理解を示した。
会場からも、出荷制限値は1kgあたりの数値であり、その食品を常に1kgを食べたりはしない、さらに損失余命は専門的な知識がなくてもとても分かり易いという意見があった。ここで、司会者から会場内に損失余命の考え方が理解できたかという赤青カードで答えを求める質問が出され、2名の赤以外は、ほぼ全員青を挙げの会場内の意思が共有されたものの、赤カードを上げた2名の方から、損失余命の定義が分からない、低線量被ばくのリスク評価に自己修復機能を踏まえていない生物学的理解が乏しいリスク評価を採用した損失余命は理解できないとの意見が出された。
9 ・住民の食べ物への考え方
次に、川俣町、川内村、霊山町の3名の方から発言があった。川俣町の方は、震災直後の生々しい記憶や測定所へ野生のキノコを測ってもらったとき出荷制限値を超えたものは没収されてしまったことが多々あったこと、行政の過剰な放射能防護への矛盾への怒りが示され、山菜やキノコなどの地物はコミュニケーションのツールであり、お金のやりとりのない物については、数値化しないで制限を出来るだけ無くして欲しい、自由にして欲しいとの発言があった。
川内村の方からは、川魚はえらや内臓を外すと数値が極端に下がることから食べ方の工夫ができる。山菜やキノコなどの里山資源を線量で管理をするという切り口は、食文化をずたずたに切り裂き、地域にストレスを与えている。食べる食べないという安全性と生き甲斐や楽しみという地域の資源を分けて考えるべき。損失余命という考え方は専門家のご意見はいろいろあると思うが、このような軸があることで地域が蘇ってくることを専門家のみなさんできちんと考えて欲しいとの発言があった。
霊山町の方からは、生活する上で、放射能だけがリスクではない、さらに自然放射線や医療被ばくによる線量と比較すると、この地域で暮らす上での被ばく量は極わずかであるという意見があった。
これら会場の意見を受けて、越智医師より医師と公衆衛生の違いの説明があった。医師は、病気を治すが公衆衛生は健康を守るものと言う定義の説明をし、放射線のリスクを議論するときに病気にならないことばかりを議論してしまい、健康を守る議論を完全に無視していると指摘した。
また、損失余命に関して、この名称はマイナスイメージなので良くないのではないか。都会の生活より、中山間地域が獲得余命の要素がたくさんあり、それを加えた計算も必要でないかとした。次に、放射線のリスクを避ける事例として、外に出ない、魚を食べない、野菜を食べない、キノコを食べないことを挙げ、相馬市の仮設住宅と玉野地区の比較を説明した。肥満、高血圧、糖尿病の率が仮設住宅の方が高い事を示し、原因を食生活と運動不足とした。
さらに、肥満や運動不足はガンのリスクも上がることにも言及し、最も心配する点は骨であると指摘し、骨を作る三大要因である、食べもの、運動、日光を挙げ、キノコ中のビタミンD、魚のカルシウム、野菜中のビタミンKを挙げた。
これらが不足すると骨そしょう症への影響、つまり放射線による発がんリスク以上に、転倒による死亡リスクが上がると指摘した。放射能を避けても安全な条件として、食生活を変えない、運動量を変えない、飲酒・喫煙量を変えない(増やさない)ことが重要で、これらが変わるようであれば、むしろ「低線量の放射線を避けすぎると健康に悪い」可能性があると指摘した。最後に、都会と中山間地域の大気汚染の差を示し「私たちはリスクを避けるのではなく選ぶ時代である」と結論付けた。
「4・子どもへの影響は?」に続く。
(2015年3月16日掲載)

関連記事
-
政策家石川和男さんのネット放送「霞ヶ関政策総研チャンネル」の報告。民主党で実務ができる政治家と注目された馬淵澄夫議員が登場しました。東電から事故処理を切り出し、国が関与するなどの現実的提言を行っています。
-
広島、長崎の被爆者の医療調査は、各国の医療、放射能対策の政策に利用されている。これは50年にわたり約28万人の調査を行った。ここまで大規模な放射線についての医療調査は類例がない。オックスフォード大学名誉教授のW・アリソン氏の著書「放射能と理性」[1]、また放射線影響研究所(広島市)の論文[2]を参考に、原爆の生存者の間では低線量の被曝による健康被害がほぼ観察されていないという事実を紹介する。
-
東京大学大学院医学系研究科 総合放射線腫瘍学講座 特任教授 中川 恵一 東京電力福島第一原子力発電所のALPS(多核種除去設備)処理水の海洋放出が始まっている。 ALPS処理水とは、原子力発電所の事故で発生した汚染水から
-
波紋を呼んだ原田発言 先週、トリチウム水に関する韓国のイチャモン付けに対する批判を書かせていただいたところ、8千人を超えるたくさんの読者から「いいね!」を頂戴した。しかし、その批判文で、一つ重要な指摘をあえて書かずにおい
-
アゴラ研究所の行うシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」の出演者が、GEPRに寄稿した文章を紹介します。
-
NHK 3月14日記事。大手電機メーカーの東芝は、巨額損失の原因となったアメリカの原子力事業を手がける子会社のウェスチングハウスについて、株式の過半数の売却などによってグループの連結決算から外し、アメリカの原子力事業からの撤退を目指す方針を明らかにしました。
-
アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」を運営している。東日本大震災、そして福島第一原発事故から4年となる、3月11日に「なぜ正確な放射能情報が伝わらないのか-現地視察した専門家の提言」を放送した。
-
2017年3月23日記事。先進国29カ国が加盟するOECD/IEA(経済協力開発機構/国際エネルギー機関)と170カ国以上が加盟するIRENA(国際再生可能エネルギー機関)が共同でCO2(二酸化炭素)の長期削減シナリオを策定した。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間