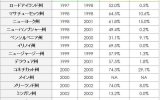自民党、原子力規制の改革に前向き-実現は不透明

写真 田中俊一原子力規制委員会委員長、
運営への不満は原子力関係者に高まる
自民党が原子力規制委員会の改革に前向きだ。同委員会の設置法では発足3年での見直し条項が置かれているが、今年9月でその年になる。それに合わせて問題の多い同規制委の活動を組織改編で見直そうとしている。しかし反原発に傾いた世論は規制委改革に批判的で、先行きは見通せない。
「独善」の批判強まる規制委
自民党は「原子力規制に関するプロジェクトチーム(PT)」(座長・吉野正芳衆議院議員・福島5区)、さらに電力安定供給推進議員連盟(会長・細田博之衆議院議員・島根1区)などが有識者からヒアリングを重ねている。議論は非公開だが、内部の議論では参加する衆参の議員が、規制に多くの問題があるとの意見で一致しているという。
規制委による原子力規制の状況は一言でまとめると「混乱」と形容できる。活断層の判定問題では、日本原電などの事業者と対立している。新安全基準の施行から2年が経過したのに一つも原子炉の審査を完了できず、再稼動の大幅な遅れが続いている。この2つの問題は、「組織の構造に問題がある」(自民党議員)との、批判が大勢だ。議連は議員の私的な勉強会という位置付けで、方針をまとめるのはPTだが、議員のメンバーの多くは重なっている。
原子力規制委員会は民主党政権時代の2011年に、当時野党だった自民党との合議で設立が決まった。独立性を強め国会、他省庁、民間の介入が行えないようにした。11年に起こった東京電力福島第一原発事故では規制のなれ合い、また甘さが事故の一因になったという反省に基づくものだ。そして経産省の外局で経産大臣の下にあった原子力安全・保安院を解体。そして規制委を環境省の外局にして、政策実施機関として原子力規制庁をおいた。しかし環境大臣の指揮・命令権はなく、独立性を強めた。
しかし、その独立が「独善」「孤立」になっているようだ。規制が手続き上、明文化されず、法律に根拠しないものも多い。原子力の研究者、メーカー、電力会社との意見交換が少なく、出先の審査官の裁量で規制の細目が決まっている。科学的な分析も足りないと、専門家は批判する。
やみくもな再稼動推進の議論なし
特に、規制委改革に熱心なのは原発立地地域選出の議員だ。反原発の立場の人々が批判することだが、原発は稼働によって交付金が立地する自治体に払われ、また大規模プラントであるために、その活動の波及効果が地元経済にある。また原発停止を主因にして震災以降、電力料金が産業用で2−3割、家庭用で1割上昇した。原発の稼動の長期停止で、関係する人々が経済的に苦しむ現実がある。その苦しみを聞く議員が声を上げるのは自然の流れだし、非難はできないだろう。
同議連は6月2日、10日と原子力の有識者を集め、勉強会を開催した。議連会長の細田博之衆議院議員は冒頭「大変なことが起こっている」と、再稼動の遅れ、そして活断層審査の混乱、さらに原電敦賀2号機などの廃炉の可能性に懸念を示した。
有識者では、アゴラ・GEPRに登場した規制委員会の行動への疑問を示してきた人々が呼ばれた。東大元特任教授の諸葛宗男氏、民間NPO「原子力国民会議」事務局長の山口篤憲氏、北海道大学教授の奈良林直氏などが意見を表明した。「事業者との対話不足」「独善的判断」「非科学的な審査」「法的根拠のない行政指導の連発」「規制の混乱」などの問題を指摘した。また規制委の政策実施機関である原子力規制庁の一部職員が、官僚でありながら新規制基準の適合性審査、活断層審査で、横暴な対応を原子力事業者に繰り返していることも指摘されたという。
出席議員からは、参考人の陳述に賛同する意見が続いた。ただし議員からは福島原発事故の反省から、規制を容易にしてやみくもに再稼動をするべきという意見はなかった。適切な行政が行われていない現状が問題になっているのだ。
組織監視などの改正意見
9月を目指し、同議連は意見を取りまとめ、PTに提出の予定だ。さらに政府も内閣官房内に原子力規制見直しの検討チームをつくる。原子力規制委・規制庁が規制の諸法規を決めているが、その組織を所管する行政官庁がないために、政治家が主導することになった。
同議連の議論では具体的な改正のアイデアとして、規制委員会の監視組織の設置、審査円滑化のための専門家の活用、環境省の傘下にある独立行政委員会という立場から内閣府に所管を移し外部監督権限を増やすなどが出ている。
また「そもそも現行法規を適切に運用させれば、独善という問題は起きないはず。適切な法適用を求めたい」(出席議員)という意見もある。日本の官僚は組織のクセとして部外者を排除する傾向がある。現行の規制委設置法では、米国の制度を取り入れて専門家を集め技術的な問題を判定する「原子炉安全審査会」(炉安審)を規制庁内に置くことになっている。ところが、それはほとんど開催されず、人も集めていない。これも自民党議員らは是正を求める方針という。
原子力規制委側も政治の動きは気にしているようだ。これまで学会や事業者と、規制委は交流が断絶していた。ところが規制委のある委員が規制庁幹部と共に、自民党に呼ばれる有識者を6月に呼び「自分たちは適切にやっている」と説明したという。「何を今さら」と突き放した感想が原子力関係者に広がった。
根強い反対意見、不確定要因は多い
しかし、すんなりと原子力規制改革は進むのだろうか。自民党の河野太郎衆院議員は6月2日、原子力規制PTに出席。自民党どのPTは、メンバーでなくても発言を認める。河野議員は「原子力ムラが跋扈するヒアリングであってはならない」と、座長の吉野議員らに注文を付けた。
この発言は、原子力を敵視する新聞、テレビで大きく取り上げられた。自民党内で河野氏に同調する意見は少数だが、メディアや一部の人々の間で彼の行動が注目を集めることでも分かるように、原発の活用につながる動きは今の日本では批判を受けてしまう。
またある自民党の有力議員は次のように語った。「規制委員会の運用は問題だらけだ。しかし、それは設立間もないために不慣れという点もあるし、せっかく再稼動間近なのだから組織をいじるとまた遅れる可能性がある。今大改革をするべきなのか」。自民党らしい波風を立てたくなく、現状維持を続けるという考えだ。
そして反原発の姿勢を野党各党は崩さない。連立与党の公明党も、規制委のおかしな行政の批判は同調しても、原子力の利用促進と見られることには消極的だ。安倍晋三首相も菅義偉官房長官も、「原子力問題で目立つことはしたくないようだ」との見方が広がる。安全保障問題の審議に政府と官邸・自民党のエネルギーが現時点で割かれる中で、原子力規制改革や原発再稼動の促進は、政治的課題として優先順位は低いだろう。そして来年は参院選だ。反原発の動きが社会の中で根強くある中で、議員らの規制委改革の動きは鈍るかもしれない。自民党内の原子力規制改革の意向が、そのまま政策になるかは不透明だ。
今、自民党内では、「原子力規制が適切に行われていない」という問題を議論している。これは現状で適切なものだ。ところがメディア、そして原子力に懐疑的な人は「規制を強め、電力会社を困らせ、原発をなかなか動かさない原子力規制委員会が正しい」という立場で原子力規制の改革を語る人が多いようだ。
原子力規制委・規制庁は、法律に基づかない行政、そして稚拙な手法による混乱した規制を行っている。その行政活動の是正は、原発の賛成、反対にかかわらず進めるべきだ。これは「法の支配」「適切な行政」を実現し、おかしな行政機関を改めるという問題なのだから。
(2015年6月22日掲載)

関連記事
-
原子力規制委員会が、JAEA(日本原子力研究開発機構)によるもんじゅの運営に対して不適切な行為が多いとして、「機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に行う能力を有すると認められる者を具体的に特定すること」と文部科学省に対して「レッドカード」と言える勧告を突きつけた。
-
4月30日に、筆者もメンバーとして参加する約束草案検討ワーキングにおいて、日本の温暖化目標の要綱が示され、大筋で了承された。
-
ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。
-
10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。
-
国は9月5日に楢葉町の避難指示を解除する。しかし、放射線への不安や生活の利便性などから、帰還をためらう町民も多い。多くの課題が残る中、これからどう町を再建していくのか――。松本幸英町長に方針を聞いた。
-
エネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、旬な政策テーマを選び、識者・専門家と議論する映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。9月9日夜は1時間に渡って「どうなる福島原発汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」を放送した。
-
世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期
-
米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間