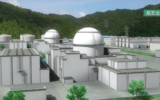原子力エネルギー利用への信頼回復の道のり
原子力エネルギー利用への信頼喪失の現状
福島第一原子力発電所の重大事故を契機に、原発の安全性への信頼は大きくゆらぎ、国内はおろか全世界に原発への不安が拡大しました。津波によって電源が失われ、原子炉の制御ができなくなったこと、そしてこれを国や事業者が前もって適切に対策をとっていなかったこと、そのため今後も同様の事故が発生するのではないかとの不安が広がったことが大きな原因です。
国はこれを教訓として、全原発の稼働を停止し、新しい規制基準を設けてこの基準を満たさなければ再稼働させないこととし、規制委員会が厳正に審査を行っています。事業者側も、新規制基準対応に全力を傾注し、一刻も早い再稼働をめざして最善を尽くしています。世界一の安全対策を施すことによって二度とあのような事故を起こさないこと、また万一過酷事故(シビアアクシデント)が起こったとしても、近隣住民に放射能汚染の被害が及ばないようにすることが、新規制の背景にあります。
しかし、そのような官民あげての努力にも関わらず、現在までに再稼働を達成したのは九州電力・川内原発のわずか2基にとどまっています。国民の再稼働反対の世論は、依然多数を占めており、この現状に国や原子力関係者は戸惑いを隠せず、いかにしたら国民の原発への信頼を回復できるかを模索しているのが現状です。
原子力エネルギーへの信頼喪失の原因
福島の事故を契機に、原子力エネルギーについてのマスコミの報道は事故以前に比べて格段に増加しました。1986年のチェルノブイリ原発事故によって原子力への信頼が失われた後には、自然エネルギーが注目を浴び、新聞紙上に原発という二文字が全く載ることがない時期が長年続きましたが、福島の原発事故以降は原子力に関するおびただしい情報が報道されてきました。
その結果、原発に対する報道関係者はじめ国民の理解は相当進んだといえます。福島の事故の前には、原発は自分とは無関係だと考えて全く関心を示さなかった大多数の人々が、原発とはどういうものかを知るようになりました。しかしながら、原発を知れば知るほど不信感を増幅させていったことも否定できません。不信感を抱いた原因は様々ですが、主な不信感は次の二つになると思います。
(1)一度起こった原発事故は再び起こるに違いない。福島で起こった事故と被害の終息も済んでいない現状で、今後の原発を認めるわけにはいかない。
(2)原発の使用済燃料から排出される長寿命の高レベル放射性廃棄物の処分の道筋がつけられていない。このまま原発を運転すれば、高レベル放射性廃棄物は増え続けてしまう。
これらの不信感を払拭するため、国や原子力事業者は最善の努力を払っていますが、華々しい成果を示せるようなものではありませんから、信頼を回復させるのは容易ではないと思います。
原子力関係者や専門家の信頼回復へのアプローチ
国や原子力関係者あるいは専門家が、国民の信頼回復を得るために、様々な努力を重ねています。その一つとして、議論の俎上にあがっているのが、確率論的安全評価(PRA)、あるいはリスク評価の手法の導入です。確率論的安全評価とは、原発の安全性を理解する上で、システムを構築している個々の機器の信頼性を確率的に評価して、システム全体のリスクをより科学的かつ定量的に把握し説明しようとする考え方です。
この手法は、原発に限らず複雑な機器から構成されるシステムのリスク評価を合理的かつ定量的に行う上で有効な方法の一つではあります。また、原発の安全性評価だけでなく、原発の設計段階から確率論的評価を取り入れることで、安全性のより高い原発システムを開発しようという方向にも向かっています。従って、今後も確率論的安全評価が重要な役割を担っていくことは期待されます。
リスクコミュニケーションを取り入れることが信頼回復の鍵になると、国や専門家は考えるようになっています。しかし、このような評価を真に必要としているのは、原発の専門家や工学者(エンジニア)自身であり、国民が必要としているかは疑問があります。
一般国民の意識との乖離
大多数の一般国民が、国や事業者あるいは専門家に求めているのは、そのようなきめ細かな定量的リスク評価でしょうか。原発の関係者のような科学技術の専門家は自身の判断基準が一般国民にも通用すると思い込みがちだと思います。
積極的に反対していない人々は、原発以外の技術系や、電力料金の上昇を望まない商工業等の産業関係者など、経済分野に多いのも事実だと思います。一方、原発反対を唱えている人々は、主に原発被害を受けた人々と今後被害を受けることを懸念している地元や近県の住民、および良識的な自然派の生活者、農業・漁業関係者、その他の科学技術とは異分野の人々、たとえば文化人やジャーナリスト、そして反対している人々の意志を代弁している政治家などです。
科学技術的思考を日常としている専門家とはやや違う人々が多いと思います。このように根本的な考え方が異なる原発反対の人々に、リスク評価やリスクコミュニケーションのような科学的な論理だけを手段として、原発の安全性や廃棄物対策について訴えても、信頼回復にはおのずから限界があると言わざるをえません。
信頼回復への遠い道のり
原発とは、核分裂反応を起こさせる装置にとどまらず、炉心を高い温度に上昇させて、高温・高圧の蒸気を発生させ、最終的に動力を得るものですから、温度が高くなりすぎて炉心が溶融し、あるいは放射性物質がその圧力によって環境へ放出されることがないようにしなければなりません。
そのような安全な原発の設計や運転を長年にわたり続けていくことが信頼を得るための唯一の手段であることは、原子力エネルギー利用の黎明期から今日までよく知られていたはずでした。しかし、それがひとたび失われた現状では、原子力関係者が地道な努力を積み重ねて信頼の再構築をはかろうとしても、なかなか思うように行かないのが現実です。
信頼の再構築は、具体的には、原子力関係者個人への信頼、官民の関係組織への信頼、専門家への信頼、およびそれらを基礎とした国の原子力政策への信頼がそれぞれ増進し、全体として信頼の輪が拡大していくように進めていくことが大事だと思います。つまり、それぞれの立場で最善を尽くすことが、大きな信頼へとつながっていくものと思います。
それは原子力関係者側からのリスク論などの科学的論理の一方的押し付けではなく、科学技術とは異分野の人々に歩み寄ることによって信頼感を醸成していくようなことではないかと思います。そのようになるまでには長い道のりが待っていることと思います。
理想とする未来社会
現在は原発反対の声が大きくても、原子力関係者の多くは、「原子力エネルギーは人類が発見した貴重なエネルギー源であり、これを適切に利用していくことで長期にわたって人類の福祉と平和に役立っていくもの」という科学的な確信のもとに、批判や障害に耐えながら奮闘していることと思います。原発技術を一層発展させると共に、後世に継承していくシステムを確立することも必要です。その際、厳しい批判の意見も受け入れて、緊張感を保った上で、技術の発展、安全対策を推進しなければなりません。
それによって、より多くの人々が原子力エネルギー利用への信頼と共感をもてるような未来社会がおとずれることを期待したいと思います。
(2015年10月26日掲載)

関連記事
-
【ノート・GEPR編集部】2006年に発足したIPFM(International Panel on Fissile Materials:核物質をめぐる国際パネル)の提言の一部として、日本の使用済み核燃料の再処理政策について提言した論文の要約を紹介する。
-
アゴラ編集部の記事で紹介されていたように、米国で共和党支持者を中心にウクライナでの戦争への支援に懐疑的な見方が広がっている。 これに関して、あまり日本で報道されていない2つの情報を紹介しよう。 まず、世論調査大手のピュー
-
高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) 政府は、高速増殖炉(FBR)「もんじゅ」を廃炉にする方針を明らかにした。これはGEPR(記事「「もんじゅ」は研究開発施設として出直せ」)でもかねてから提言した通りで、これ以外の道はなか
-
アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。
-
先月政府のDX推進会議で経産省は革新的新型炉の開発・建設を打ち出したが、早くもそれを受けた形で民間からかなり現実味を帯びた具体的計画が公表された。 やはり関電か 先に私は本コラムで、経産省主導で開発・建設が謳われる革新的
-
英国はCOP26においてパリ協定の温度目標(産業革命以降の温度上昇を2℃を十分下回るレベル、できれば1.5℃を目指す)を実質的に1.5℃安定化目標に強化し、2050年全球カーボンニュートラルをデファクト・スタンダード化し
-
ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分
-
イーロン・マスク氏曰く、「ヨーロッパは、ウクライナ戦争が永遠に続くことを願っている」。 確かに、トランプ米大統領がウクライナ戦争の終結に尽力していることを、ヨーロッパは歓迎していない。それどころか、デンマークのフレデリク
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間