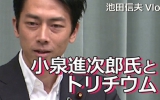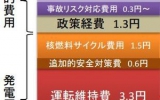フィンランド、使用済み核燃料処分地決定の理由
使用済み核燃料の処理問題の関心が集まる。しかしどの国も地中処分を目指すが、世界の大半の国で処分地が住民の反対などがあって決まらない。フィンランドは世界で初めて、使用済み核燃料の処分場の場所を決め、操業開始を目指す。同国の雇用経済省エネルギー局次長のヘルッコ・プリット氏が10月来日したのを機に、取り組みを聞いた。

-フィンランドにおける使用済み核燃料処理の現状はどうか。
プリット・現在、西部のオンカロという場所で、最終処分施設の工事が行われている。今は地下へのアクセストンネルの工事は終わり、研究施設でデータを集めている。来年から、使用済み核燃料の貯蔵所が地下450メートル以下に建設される予定だ。
そして100年程度の操業、その後の埋設を予定している。ただしどの程度の量が処分されるかは明確ではない。運営者は原子力事業者2社が1995年に設立したポシバ社だ。2004年から工事が始められ、2020年代の始めに、その操業が開始される予定だ。
-最終処分の方法でどの国も合意を得られない中で、なぜフィンランドは可能になったのか。
プリット・1983年に最終処分の実施を議会が決定し、国の方針が明確になったことが、処分場の選定を前進させた。そこで最終処分で、事業者は明確な責任を果たすべきこと、国が国民の合意形成を支えることが法律で決まった。そしてポシバ社がつくられ、2000年に場所を選び、01年に議会が操業を認めた。
経済的効果が住民同意に結びつく
-住民の反対運動は起こらなかったのか。日本でも、住民の不安と「私の裏庭には迷惑施設をつくってほしくない」(ノット・イン・マイ・バックヤード)」という感情は消えない。
プリット・オンカロは、2つの原子炉を持つオルキルオト原子力発電所に隣接し、地域住民に理解があった。またフィンランドは花崗岩に覆われた国で、住民も岩盤の堅固さを知っている。さらにポシバ社が住民との対話を重ね、地域における事業継続、そして雇用を100年保証したのも影響した。
-原子力施設の立地地域に財政支援はあるのか。
プリット・原則として、ない。税の支出への公平性を守るためだ。しかし地域の自治体、コミュニティに、原子力施設による経済メリットがある。原子力施設が置かれるのは、人口の密集地や都市から離れている。こうした企業が誘致されることで地域社会に従業員の雇用、税収など、多くの経済的メリットがある。この処分場もそれが注目され受け入れられた。
-政府は原子力の啓蒙活動はしているのか。
プリット・していない。行政は中立性を確保するために、原子力を推進も反対もしない。広報活動は事業者が行う。当然、反対の意見も尊重される。
私たち行政府は法律の執行を行う立場だ。原子力エネルギー法では、原子力事業者は事業で、住民の合意の上に活動すること、環境アセスメントの実施と公表、正確な事業情報の公開が決まっている。
原子力事業者、そして最終処分を担うポシバ社は、住民と対話集会を重ねている。その事業者の説明会で、政府が呼ばれれば担当者が説明する。オンカロでは、70年代からそうした住民合意が積み重なってきた。
行政府も使用済み核燃料の問題について、論点を整理し、政策をまとめている。私が委員長になった放射性廃棄物の検討委員会が13年から14年に開催され、ステークホルダーを集めて問題を討議した。原子力の未来を完全に見通せないために不確実性は残るが、現在の処分方法を事業者が進め政府が支援することを決めている。
政治の意思決定が重要な意味
-フィンランドは教育水準が高く、また理性的な国民性があると聞く。それが冷静な議論と処分地の決定に影響したのか。
プリット・その答えは部分的に正しく、部分的には正しくないだろう。原子力の問題については、感情的な反応はどうしても呼び覚まされてしまう。それはフィンランドでも同じだ。しかし情報の公開、行政の公正さ、事業者による説得と合意形成を重ねてきた。
私の個人的な意見では、1980年代に国会が明確に国の方針を決めたことが、現在の状況を生み出したと思う。政治家が、党派を越えて問題解決に協力し、合意形成を試みたことが、良い影響をもたらした。
-フィンランドで原子力はどのような位置付けか
プリット・エネルギー政策の基本はベストミックスの追求であり、これは世界各国と同じだ。ただし電力の生産が足りず、需要量の2割を海外から調達している。これの引き下げが政策上の課題だ。原子力は、過渡期のエネルギーとして国民の大半は使うことを容認している。発電量のうち原子力は3割、2割が水力やバイオマスなどの再生可能エネルギー、残りが火力だ。再エネを増やすのが現在の政策だ。
-工事の遅れが伝えられ、建設を請け負った仏アレバ社の経営悪化の一因になったオルキルオト原発の状況はどうか。
オルキルオト3号炉は18年中に操業する予定と聞いている。原子力規制は別の委員会が担当しているので、私はそれ以上のコメントはできない。またアレバ社の経営も報道で知るのみだ。
-日本は福島事故を起こした失敗をし、そしてその後はエネルギー政策、また原子力規制行政の混乱が続いている。これを抜け出すアドバイスはないか。
プリット・他国の政策の論評は控える。どの国の政策も、私たちの政府は尊重している。わが国について言えば、原子力規制は独立委員会が保健省の管轄下で担当している。私たち雇用経済省は、それに関与できない形になっている。それが安全性の確保に役立つと考えるためだ。そして日本の福島事故の後の政策は世界的に注目されている。
ヘルッコ・プリット 1996 年ヘルシンキ工科大学終始。2008年フォータム原子力サービス社長などを経て12年より現職。
この原稿は筆者が取材し、エネルギーフォーラム11月号に寄稿したものを、転載した。許諾をいただいた関係者の方に感謝を申し上げる。
(2015年11月16日掲載)

関連記事
-
「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にその経験をどのように活かせばよいのか。
-
ここは事故を起こした東京福島第一原発の約20キロメートル以遠の北にある。震災前に約7万人の人がいたが、2月末時点で、約6万4000人まで減少。震災では、地震、津波で1032人の方が死者・行方不明者が出ている。その上に、原子力災害が重なった。
-
原田前環境相が議論のきっかけをつくった福島第一原発の「処理水」の問題は、小泉環境相が就任早々に福島県漁連に謝罪して混乱してきた。ここで問題を整理しておこう。放射性物質の処理の原則は、次の二つだ: ・環境に放出しないように
-
東電の賠償・廃炉費用は21.5兆円にのぼり、経産省は崖っぷちに追い詰められた。世耕経産相は記者会見で「東電は債務超過ではない」と言ったが、来年3月までに債務の処理方法を決めないと、純資産2兆3000億円の東電は債務超過になる。
-
アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。
-
はじめに 台湾政府は2017年1月、脱原発のために電気事業法に脱原発を規定する条項を盛り込んだ。 しかし、それに反発した原発推進を目指す若者が立ち上がって国民投票実施に持ち込み、2018年11月18日その国民投票に勝って
-
原子力発電は「トイレの無いマンション」と言われている。核分裂で発生する放射性廃棄物の処分場所が決まっていないためだ。時間が経てば発生する放射線量が減衰するが、土壌と同じ放射線量まで減衰するには10万年という年月がかかる。
-
はじめに 原子力発電は福一事故から7年経つが再稼働した原子力発電所は7基[注1]だけだ。近日中に再稼働予定の玄海4号機、大飯4号機を加えると9基になり1.3基/年になる。 もう一つ大きな課題は低稼働率だ。日本は年70%と
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間