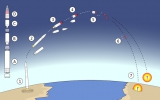サウジアラビア:サルマン国王生前退位か
(GEPR編集部より)サウジアラビアの情勢は、日本から地理的に遠く、また王族への不敬罪があり、言論の自由も抑制されていて正確な情報が伝わりません。エネルギーアナリストの岩瀬昇さんのブログから、国王の動静についての記事を紹介します。(元の原稿はこちら)
以下本文
すぐには信憑性が確認できないが、もしそうなったら中東はさらなる激動に襲われるのではないか、というニュースが報じられている。
英国の有力紙 “Sunday Times” が1月17日 “Saudi king ‘plots to bypass nephew’ in handover of crown” と題して報じているものだ。”Sunday Times” を検索すると、ある箇所からは有料となっている。念のために同題で検索してみたら、元ネタと思われる記事に遭遇した。1月13日付で “the Institute of Gulf Affairs” なるものが Adam Whitcomb の名前で、全く同じタイトルで報じているのだ。そしてこの元ネタは在ワシントンのシーア派反体制派のサウジの一族の出身であるAli al-Ahmadが自らのThe Institute of Gulf Studiesのウェブサイトに掲載したもの。Whitcombは何らかの補助をしただけと思われる。“Sunday Times” が「反政府派に支援されているGulf Instituteの発表」としているが、この手の話題は反政府派からしか出て来ない類のものだろう。
要点をまとめると次のようになる。昨年1月23日に即位したサルマン国王(80歳)は、4月29日に腹違いの弟で第一皇太子だったムクリン(母はイエメン系)を解任し、第二皇太子だった同腹の兄の息子(甥)のモハマッド・ビン・ナイーフ(MBN、56歳)を第一皇太子とし(内務大臣)、最愛の息子モハマッド・ビン・サルマン(MBS、30歳)を第二皇太子(国防大臣兼経済開発評議会議長)に任命し、今日を迎えていることは読者の皆さんもご存知のとおりだ。
サルマン国王は、サウジ国家の「安定」のため、これまでのlateral or diagonal(横または斜め)に王位を継承してきたルールを改め、vertical(垂直)なものとすべきだと、「兄弟」たちのところを巡り、説いて回っている。すでに数億ドルの金も使っている。ヨルダン王制の例を出して、正当なることを主張している。カタールの前首長 Hamed bin Khalifah Al’Thaniも2013年に生前退位し、息子に王位を譲っている。
ひとつの根拠としているのは、噂ではコカインを愛飲していたため、MBNのところには娘が2人いるだけで息子がいないという事実だ。MBSには2人の娘と2人の息子がいる。
かつての兄王たち、アブドラ、ファハド、カリド、サウドの場合も、国王として逝去した後、息子たちは全員、要職を外されている。サルマン国王はこれも心配している。
サルマン国王が生前退位するタイミングについては、情報筋は言及していないが、数週間以内では、と見られている。一方、米国政府筋は、この夏だろう、としている。
いやはや、大変な変化だ。
サウジ事情に詳しい友人によると、サウジはこれまでも「長老たち」がカーテンの裏で調整に調整を重ね、全員が合意できる形で穏やかな変化を推し進めて来た。今回も、サルマン国王の独断専行ではなく、王族長老たちが納得できる形で進んで行くだろう、という。
だが、筆者は王位継承権を持つプリンスが1000人以上となった今日では、これまでのような「長老による調整」がスムースに行われるだろうか、と疑問に思っている。
特に、原油価格大幅下落による国家財政の悪化が、さらに「長老による調整」を困難にするのではなかろうか?
さて、読者の皆さんはどうお考えになるだろうか?
(2016年2月1日掲載)

関連記事
-
(編集部より)国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソン氏が急逝されました。アゴラのシンポジウムや番組でも、鋭くも知性に満ちた言葉を届けてくださった氏の、あまりに早すぎる別れに、編集部一同深い悲しみに暮れています。 本稿
-
台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ
-
北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。
-
(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か③) 結局、火力発電を活かすことが最も合理的 再エネの出力制御対策パッケージをもう一度見てみよう。 需要側、供給側、系統側それぞれの対策があるが、多くの項目が電力需給のバラ
-
7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択
-
こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国
-
山火事が地球温暖化のせいではないことは、筆者は以前にも「地球温暖化ファクトシート」に書いたが、今回は、分かり易いデータを入手したので、手短かに紹介しよう。(詳しくは英語の原典を参照されたい) まずカリフォルニアの山火事が
-
【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間