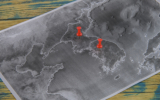東電の分社化は「国策民営」をやめて責任の明確化を
経済産業省は東電の原子力部門を分離して事実上の国営にする方向のようだが、これは順序が違う。柏崎刈羽原発を普通に動かせば、福島事故の賠償や廃炉のコストは十分まかなえるので、まず経産省が今までの「逃げ」の姿勢を改め、バックフィットのルール化など再稼動の態勢をつくるべきだ。
その上で、分社化は検討の余地がある。これは3年前から野村修也氏など企業法務の専門家がほぼ一致して提言していることで、今の「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」のような官民癒着の組織は最悪だ。ここでは原発が正常化するという前提で、その長期的な採算性を考える。
核兵器開発という「密教」
日本の原子力開発の方針を最初に決めたのは、1956年の「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(通称「長計」)である。ここには「原子力の平和利用を計画的かつ効率に推進することを目的とする」と書かれており、日本の原子力開発を平和利用に限定している。
長計を立案したのは原子力委員長だった正力松太郎と、後に科学技術庁長官になった中曽根康弘だった。ここにはすでに「将来わが国の実情に応じた燃料サイクルを確立するため,増殖炉,燃料要素再処理等の技術の向上を図る」と書かれており、原子力の平和利用が核燃料サイクルをめざすものであることを示している。
正力がCIAの工作員だったことは周知の事実だが、中曽根は核武装論者だった。彼らは核兵器開発の第一歩として、原発を構想していたのだ。これは当時のアメリカの世界戦略にも合致していた。1952年に日本が独立するまではアメリカの戦略は敵国だった日本を武装解除することだったが、冷戦の激化で情勢は変わった。
本来は日本に再軍備させて軍事力を肩代わりさせる予定だったが、吉田茂首相がそれを拒否したため、警察予備隊を自衛隊と改称し、日本を極東の橋頭堡にする予定だった。そのため当初はイギリスから導入した原子力技術をアメリカ製に切り替えるよう求め、アメリカの管理のもとで日本の原子力開発は行なわれた。
核武装は悪ではなく、ソ連の核兵器の脅威が大きかった当時は、通常戦力より低コストで抑止力を実現できる可能性があった。しかし広島・長崎の経験を知っている日本国民にとって核武装はタブーであり、ビキニ島核実験による被曝事故(死因は放射能と無関係)もあって、この目的はいわば密教として関係者に語り継がれた。
「国策民営」の無責任体制
このように核燃料サイクルの最大の目的は(他国と同じく)核兵器の開発だったので、政府が電力会社に原発の立地を求めたとき、核燃料サイクルのコストは国が負担するという暗黙の了解があった。太田昌克『日米〈核〉同盟』によれば、東電の豊田正敏・元副社長は「国策なので国がやってくれるという認識があった」と次のように語っている。
再処理は他の国でも政府がやっているので、「国がやってくれるなら、やってもらったらどうか」という話はあった。高レベル廃棄物の処分も、国がやってくれることだと。電力は軽水炉を問題なく動かすことが使命だと考えていた。ところが動燃が東海村の再処理工場をつくっても、まともに動かない。(pp.142-3)
全体計画は政府が立案したが、特殊法人である動燃が導入したイギリスの再処理技術は使い物にならなかったので、結果的には電力会社の共同出資した日本原燃が技術開発をやることになった。再処理工場の最大のコストは技術開発にかかるので、これは国が計画だけ立てて電力会社がすべてのコストを負担する国策民営だった。
ところが1974年にインドが再処理したプルトニウムで原爆をつくったので、アメリカのカーター政権は再処理工場の凍結を打ち出した。このため60年代からアメリカの技術で核燃料サイクルを開発してきた日本の電力業界は、ハシゴをはずされる結果になった。この方針は核拡散防止条約でも決まったが、日本だけはそれまでの経緯から核燃料サイクルの開発が認められ、1988年に日米原子力協定が結ばれた。
こうして日本の核燃料サイクルは、当初の「密教」だった核兵器の開発が非核三原則で禁じられ、アメリカも歓迎しない中で、当初の予定どおり進められた。原子力開発のためにつくられた科学技術庁(今の文部科学省)は後退し、通産省が前面に出て「資源論」で開発が進められた。それは国が電力会社に「ただ乗り」する無責任体制だった。
全量再処理をやめて多様なオプションを
このような場当たり的な原子力政策のとがめが、いま表面化している。ある電力会社の首脳は「もし今から六ヶ所村[の再処理工場]をつくるかどうか判断するとしたら、つくらないだろう」という。これまでの設備投資だけで総額は約3兆円、保守経費も含めると最終的に7〜12兆円以上が核燃料サイクルに投じられる予定だが、採算のとれる当てはない。
原子力委員会の試算では、再処理コストは直接処分の2倍で、kWhあたり1円高いが、それに見合うメリットは不明だ。核燃料サイクルの中核である高速増殖炉(FBR)の実用化が絶望的になったからだ。おまけに非在来型ウランは(海水ウランを含めると)ほぼ無尽蔵にある。
したがって核燃料サイクルの是非は、投資収益率(ROI)という経済問題に帰着する。これは簡単にいうと、長期的な投資の割引現在価値(NPV)と将来のキャッシュフローのどちらが大きいかという問題だ。つまり核燃料サイクルで得られる利益がプラスなら投資したほうがよく、マイナスならやめたほうがいい。
核燃料サイクルの投資収益率を考えると甘い想定でも8.5兆円の赤字である。さらに問題なのは、高速炉の開発に失敗して核燃料サイクルのリターンがマイナスになるおそれが強いことだ。これは大事件の確率がわからないテールリスクである。
テールリスクにどう対応するかは経済学でも明確な答がないが、少なくともいえるのは多様なオプションをもったほうがいいということだ。これはファイナンスと同じで、たとえ株式のリターンが債券より高くても分散投資することが安全だ。こういう金融技術にも限界があり、2008年の金融危機のような超大型のテールリスクには対応できないが、分散しないよりましだ。
今の全量再処理という政策は、FBRという高利回りの銘柄を1点買いしたら、その会社が倒産したような状態で、他のプロジェクトは倒産した会社に依存している。リスク管理としては、きわめて危険だ。
日本の原子力開発は理論物理学者がリードしてきたので、決定論的に計画を立てる傾向が強いが、現実は不確実だ。確率も計算できないが、少なくともいえるのは、プロジェクトのリスク負担のルールを明確にすべきだということだ。東電を分社化するなら原子力部門は廃炉・賠償とともに国営にし、火力発電部門は100%民営にする。責任の所在が曖昧な国策民営はもうやめるべきだ。
(2016年11月1日更新)

関連記事
-
前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。
-
地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。
-
20日のニューヨーク原油市場は、国際的な指標WTIの5月物に買い手がつかず、マイナスになった。原油価格がマイナスになったという話を聞いたとき、私は何かの勘違いだと思ったが、次の図のように一時は1バレル当たりマイナス37ド
-
核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ
-
ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報
-
9月14日、政府のエネルギー・環境会議は「2030年代に原発ゼロ」を目指す革新的エネルギー環境戦略を決定した。迫りくる選挙の足音を前に、エネルギー安全保障という国家の大事に目をつぶり、炎上する反原発風に気圧された、大衆迎合そのものといえる決定である。産業界からの一斉の反発で閣議決定にまでは至らなかったことは、将来の国民にとって不幸中の幸いであった。報道などによれば、米国政府筋などから伝えられた強い懸念もブレーキの一因と いう。
-
田中 雄三 要旨 世界の温室効果ガス(GHG)排出量が顕著に減少する兆しは見えません。 現状、先進国のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、2050年世界のGHGネットゼロを目指すには、発展途上国のGHG削減が不可欠です
-
人工衛星からの観測によると、2021年の3月に世界の気温は劇的に低下した。 報告したのは、アラバマ大学ハンツビル校(UAH)のグループ。元NASAで、人工衛星による気温観測の権威であるロイ・スペンサーが紹介記事を書いてい
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間