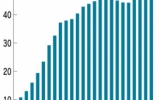「トリチウム水」の海洋放出に残された時間は少ない

これは水素の放射性同位体で、ごく微量のベータ線を出すが、人体に害はないので「汚染水」ではない。最近はマスコミも「トリチウム水」と呼ぶようになった。世界ではトリチウムは薄めて流すのが普通で、日本でも他の原発はそうしているが、福島第一だけができない。それは科学的な理由ではなく、地元の同意が得られないからだ。
経産省の「トリチウム水タスクフォース」は、他の方法も検討した上で、2016年4月に「希釈して海洋放出」することがベストだという報告書を出した。しかし経産省には処理方法の決定権がないので、これは単なる意見である。
原子力規制委員会の田中俊一前委員長は昨年、海洋放出の方針を示し、東電の川村会長も7月に「大変助かる。委員長と同じ意見だ」とコメントした。これに福島県漁連が「裏切り行為だ」と反発し、田中氏も「東電は地元と向き合う姿勢がない」と強く批判し、問題は暗礁に乗り上げてしまった。
しかし東電が地元と向き合えば、問題は解決するのだろうか。私が福島第一を見学したとき「薄めて流したらどうですか」と東電の幹部に質問したら、彼は「それは当社からはいえない」という。トリチウム水を流すこと自体は経営判断として可能だが、事実上の「国営企業」になっている東電は、国の方針なしで意思決定はできないのだ。
では誰が決めるのだろうか。田中氏は「原子力規制委員会は規制への適合性をチェックしているだけだ」という。彼の後任の更田委員長も今年1月、地元との話し合いで「意思決定をしなければならない時期に来ている」と述べたが、誰が決定するのかは明言しなかった。
更田氏によると「原発内に貯水できるのはあと2、3年程度で、タンクの手当に2年以上かかる」という。したがって今年中に結論を出さないと、貯水タンクが足りなくなる。今の状態でも地震が来たらタンクが破壊され、大事故が起こるおそれもある。
東電が決められず、規制委員会も決められないとすれば、委員会を統括する内閣が決めるしかないが、吉野復興相は風評被害を理由に放出に反対した。あとは安倍首相の決断しかない。オリンピック誘致のとき彼が約束したように「政府が前面に出て」福島の処理を進めるしかないのだ。残された時間は少ない。

関連記事
-
以前、CO2濃度は産業革命前の280ppmに戻りたがっていて、いま人為的なCO2排出量のうち大気中に留まるのは約半分で、残り半分は陸上と海洋に自然に吸収されていること、を書いた。 だとすると、人為的排出を半分にすれば、大
-
(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難③) 田中 雄三 風力・太陽光発電の出力変動対策 現状の変動対策 出力が変動する風力や太陽光発電(VRE)の割合が増大すると、電力の積極的な需給調整が必要になります。前稿③の「E
-
1.メディアの報道特集で完全欠落している「1ミリシーベルトの呪縛」への反省 事故から10年を迎え、メディアでは様々な事故関連特集記事や報道を流している。その中で、様々な反省や将来に語り継ぐべき事柄が語られているが、一つ、
-
他方、六ヶ所工場に関連してもう一つ、核不拡散の観点からの問題がある。すなわち、はっきりした使途のない「余剰プルトニウム」の蓄積の問題である。
-
日本各地の火山が噴火を続けている。14年9月の木曽の御嶽山に続き、今年6月に鹿児島県の口之永良部島、群馬県の浅間山が噴火した。鳴動がどこまで続くか心配だ。火山は噴火による直接の災害だけではない。その噴煙や拡散する粒子が多い場合に太陽光を遮り、気温を下げることがある。
-
アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過
-
けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー
-
「万感の書を読み、万里の道を行く」。士大夫の心構えとして、中国の格言にこのような言葉がある。知識を吸収し、実地で確かめることを推奨しているのだろう。私は旅行が趣味だが、この言葉を知って旅をするごとに、その地域や見たものの背景を一層考えるようになった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間