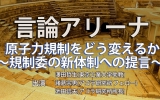処理水問題は安倍首相の「貯蓄過剰」だった
福島第一原発の処理水問題が、今月中にようやく海洋放出で決着する見通しになった。これは科学的には自明で、少なくとも4年前には答が出ていた。「あとは首相の決断だけだ」といわれながら、結局、安倍首相は決断できなかった。それはなぜだろうか。
政治家の人気を政治的資本(political capital)と呼ぶことがある。安倍首相は第1次内閣では「戦後レジームからの脱却」などの理念を打ち出したが、政治的反発を呼んで1年足らずで退陣に追い込まれた。その反省から第2次内閣では「デフレ脱却」で政治的資本を蓄積し、安保法制や憲法改正などの不人気な政策に投資するつもりだったのだろう。
ところが安保法制で2015年の国会が大混乱になり、このあおりで憲法改正も公明党が反対して行き詰まった。この状況を打開するために、経済政策は慢性的な景気刺激になった。消費税の増税は2度も延期し、日銀の量的緩和は果てしなく続き、利害対立の生じる原子力や規制改革のような政策には手をつけなかった。その結果、政治的資本は蓄積されたが、結局それを使わないまま退陣してしまった。
「リスク回避」が長期停滞をもたらす
これは日本経済の問題と似ている。マクロ経済的にみると日本の最大の問題は、企業が貯蓄過剰になっていることだ。いわゆる内部留保(利益剰余金)が460兆円、そのうち現預金が210兆円もある。カネを借りて投資する企業がカネを貸している状況で経済が成長できないことは自明である。
それにはいろいろな原因があるが、一つは企業が過剰にリスク回避的になったことだ。人口減少で国内には新しい投資先がなくなり、確実にプラスの金利がつくのは国債だけなので、企業は預金し、銀行は国債を買う。これは個々の企業にとっては合理的だが、経済の効率は上がらず、長期停滞が続く。これは景気刺激ではどうにもならない。
安倍首相のようにリスクを避けて政治的資本を蓄積しても、それを処理水のような人のいやがる政策に投資しないと、廃炉費用はふくらみ、電気代は上がり、製造業は日本から出て行く。その意味では処理水問題は、日本経済の「失われた30年」を象徴する失敗だった。
菅首相はそれを意識して、厄介な宿題を片づけているようにみえる。学術会議も占領統治の遺制という意味では、安倍首相の残した宿題である。手法はちょっと荒っぽいが、安倍首相のような安全運転では何もできない――それが彼を官房長官として見てきた菅氏の教訓ではないか。

関連記事
-
問題:北緯60度から70度の間の世界の森林(シベリアやアラスカなど)を全部伐採したら、地球はどれだけ温暖化するか? 答え:0.4℃、気温が下がる(上がるのではない!) あれ? 温暖化対策のために、植林しているんじゃなかっ
-
前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない
-
G7では態度表明せず トランプ政権はイタリアのG7サミットまでにはパリ協定に対する態度を決めると言われていたが、結論はG7後に持ち越されることになった。5月26-27日のG7タオルミーナサミットのコミュニケでは「米国は気
-
人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば
-
昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 縄文時代は「縄文海進期」と言われ、日本では今
-
世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている
-
なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。
-
2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間