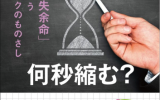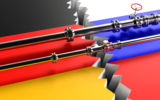民主党政権の「原発事故責任」を総括するとき
まもなく3・11から10年になる。本書は当時、民主党政権の環境相として福島第一原発事故に対応した細野豪志氏の総括である。当時の政権の誤りを反省し、今も続くその悪影響を考えている。

本人ツイッターより
あの事故が民主党政権で起こったのは、不幸なめぐり合わせだった。菅直人首相はヘリコプターで現地に乗り込んで事故処理を妨害し、政権は過剰避難を勧告して、現地には大混乱が起こった。そして細野氏が設定した1ミリシーベルトという環境基準が除染に莫大なコストをもたらし、今も被災者の帰宅を妨害し、福島の農産物や魚に風評被害を起こしている。
本書の第1章は6人の関係者と細野氏の対談だが、前原子力規制委員長の田中俊一氏の話には違和感がある。彼はトリチウムを含む処理水について「海洋放出しかない」と判断して、2014年に経産相に進言したら、大臣が「じゃあ私がやる」と約束したが、やらなかったという。
まるで他人事のように話しているが、田中氏はこの問題についての責任者なのだから、正式に「海洋放出すべきだ」という委員会決定をなぜ出さなかったのか。問題を先送りした政治家に責任はあるが、田中氏も2017年に東電の川村会長が海洋放出を示唆したとき、「はらわたが煮えくり返る」と発言して、処理を混乱させた張本人ではないのか。
もう一つ田中氏が責任を負うべきなのは、田中私案と呼ばれる怪文書で原発の再稼動を法的根拠なく阻止し、原子力規制委員会が原発の再稼動を審査するかのような慣例をつくったことだ。これは後に委員会が「再稼動の審査はしていない」と否定したが、いったんできた慣例は変わらなかった。これについては何も語っていない(細野氏も質問していない)。
フクシマを食い物にする人々
第2章は現地の人6人との対談だが、林智裕氏は「事故を千載一遇のチャンスと考えた人々が問題を長引かせてきた」という。安全神話が崩壊したのだから、必要なのは科学的事実だったが、マスコミは「プロメテウスの罠」や「核の神話」といった新たな神話をつくり、人々に核への恐怖を植えつける宣教師になった。
2013年に国連は「放射能の人的被害はない」という報告書を出したが、マスコミはそれを無視し、フクシマという言葉でビキニ環礁など無関係な問題と混同して、その恐怖を世界に売り込んだ。その意味で福島事故は、民主党政権とマスコミと活動家が被害を何倍にも誇張して作り出した情報災害だった。
これはコロナと似ている。両者に共通するのは不確実性の中の最悪の場合だけを想定する発想である。本書にも登場する近藤駿介氏(事故当時の原子力委員長)のシミュレーションについて「首都圏で3000万人の避難が必要だった」というデマを拡散している政治家が今もいる。
全国各地で原発の再稼動を差し止めて名前を売る弁護士や、甲状腺癌の過剰検査を求めて「福島は恐い」というイメージを植えつける医師がいる。そしてそういう人々を英雄扱いするマスコミがいる。10年たっても福島を食い物にして、復興を妨げているのはこういう人々である。
彼らは「被災者に寄り添う」と称して、自分たちのリスク評価が大幅な誇張だった事実を隠し、「まだ最終結果はわからない」と逃げる。ここでもコロナと同じく、不確実性が大きいことが言い訳となり、その中で最悪の場合を想定したのは善意だったという免罪符になる。
彼らが人々に与えた恐怖は10年たっても収まらず、1ミリシーベルトは今も福島を呪縛し、処理水は今も放出できない。これもコロナと似ている。行政がいったん最悪の場合を想定して基準をつくると、それが民衆の感情に刷り込まれ、正常化はきわめて困難になるのだ。
そういう福島事故の「戦犯」が野党の政治家である。特に菅氏や枝野幸男氏など当時の責任者がいまだに事故処理の責任から逃げ、「原発ゼロ」などという無責任な主張を続けている。それに比べると自分の責任を直視する細野氏の姿勢は立派だが、今後は民主党政権の責任を追及し、彼らの振りまいてきた放射能デマを是正してほしい。

関連記事
-
地球温暖化に関する報道を見ていると、間違い、嘘、誇張がたいへんによく目につく。そしてその殆どは、簡単に入手できるデータで明瞭に否定できる。 例えば、シロクマは地球温暖化で絶滅する、と言われてきたが、じつは増えている。過去
-
「必要なエネルギーを安く、大量に、安全に使えるようにするにはどうすればよいのか」。エネルギー問題では、このような全体像を考える問いが必要だ。それなのに論点の一つにすぎない原発の是非にばかり関心が向く。そして原子力規制委員会は原発の安全を考える際に、考慮の対象の一つにすぎない活断層のみに注目する規制を進めている。部分ごとしか見ない、最近のエネルギー政策の議論の姿は適切なのだろうか。
-
「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説
-
高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。
-
美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してやまない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。
-
(前回:温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①) 新興国・途上国の本音が盛り込まれたBRICS共同声明 新興国の本音がはっきりわかるのは10月23日にロシア・カザンで開催されたBRICS首脳声明である。
-
米ニューヨーク・タイムズ、および独ARD(公営第1テレビ)などで、3月7日、ノルドストリームの破壊は親ウクライナ派の犯行であると示唆する報道があった。ロシアとドイツを直結するバルト海のガスパイプラインは、「ノルドストリー
-
トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。 この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間