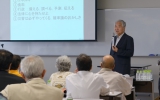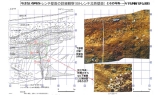暴論・妄論の横行と抑止力の減退
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智
筆者は毎日、大量に届くエネルギー関連記事を目にするわけだが、相も変わらず科学的根拠のない暴論が世に蔓延するのを見て、この国の未来に対し暗澹たる気持ちに襲われる。また、これらの暴論・妄論に対して、冷静で科学的な反論があまり多くないことを憂える。特に、現役の学者・研究者が声をあげない現状に、危険な未来を感じるのである。表向き、言論統制はないのだが。

Bulat Silvia/iStock
それは本来、科学技術を専門とする者ならば、必須の義務であるはずなのだが、現役の学者・研究者からは、日本政府のエネルギー政策に対する、根本的な批判がほとんど出てこない。白状すれば、筆者も現役時代は発言しづらかった。学会等で政府のエネルギー政策に批判的な研究成果を発表しても、会場はどことなく白けた雰囲気で、座長さんも「そんなこと言われたってなあ・・」と言った風情で、意見交換も盛り上がらなかった。科研費などにそんな研究計画を出して通るはずもなく、筆者は研究費を主に民間企業との共同研究で稼いでいた(科研費に熱心でない筆者は学内の「変わり者」であった)。定年退職後、無職の老人になり、何のしがらみも無くなって、ようやく思うことを遠慮なく広く世間に発表することができるようになった。
現役の学者・研究者が自由に意見を表明できない背景には、やはり一種の「同調圧力」がかかっていると思う。現在、日本の多くの学会は政府の「脱炭素政策」に追随し、何とかしてそれに役立ちたいと奮闘しているように見える。しかし、本来の科学に忠実に考えるならば、その根本にある「人為的温暖化説」がどの程度信用できるのかを真摯に検討し、気候変動なるものが本当に人間活動の結果として生じているのかを検証する努力を続けるべきであるのに、そのような動きはほぼ見られない。みんなと異なる意見を述べると「のけ者」にされてしまうからだろう(雉も鳴かずば撃たれまい・・)。
そして、研究者でもなく科学を何も知らない政治家や記者等が、したり顔で大手マスコミに暴論を載せる。例えば「気候危機とグレタと資本主義」と言う記事。その中に「気候変動を安全と思われる許容範囲にとどめるには、世界の二酸化炭素の排出量を2030年までに半分にして、50年までには実質ゼロにしなければなりません」と何の断りもなく書かれている。科学的根拠は一切示されずに、ごく当たり前の事実であるかのように書かれているのだ。しかし、この言説に科学的根拠はない(詳しくは「地球温暖化のファクトフルネス」参照)。
また、同じ新聞の「日本を資源国家に 国内CO2と水素による経済安全保障」と言う記事。「とりわけCO2は、多くの可能性を秘める資源として着目でき、水素との合成によって、多様なマテリアルや燃料を製造する夢の原料になり得るのだ」とか「石油から製造された化石由来のマテリアルや燃料を、大気中から回収したCO2由来の原料や燃料に変えて、カーボンニュートラルを進めて行くことが可能になる」などと書かれているが、多少とも化学工学を知っている人間なら、簡単にこんなことは書けないはずである。
そもそも、CO2を再利用しようという研究は相当以前から行われ、また水素製造に関する研究も、1970年代の石油危機以降、1980年代からこれまで40年以上も行われてきた経緯を知っているのだろうか? もし知っていたら、上記のようなお気楽な記事は書けないだろうと思う。
まず「大気中から回収したCO2由来」と書かれているが、大気中CO2濃度は約400ppm、つまり0.04%しかない。これを回収し固定するには、大量の空気を輸送し効率的に固定する必要があり、技術的には非常に難しい。空気輸送だけで大量のエネルギーを要するし、僅か0.04%しかない成分をガス吸収や吸着で固定するのは恐ろしく大変である。吸収剤・吸着剤の量も膨大になるし、一度固定したCO2を脱着するにもエネルギーがかかる。吸収・吸着に頼らず、直接空気を圧縮してCO2を液化しようとすると、これまた莫大なエネルギー消費が必要になる。いずれにしても、大気中CO2を回収して利用するには、最初の固定の段階ですでに膨大な外部エネルギー投入が避けられず、この段階でカーボンニュートラルなど夢のまた夢と消える。
人類が利用してきた有機物の炭素源は、これまでずっと化石燃料とバイオマスが主体で、この状況は相当長く続くと考えるのが現実的である(石油化学が高くて使えなくなったら石炭化学がある)。大気中CO2が人類の炭素源になる日は、化石燃料が枯渇した後の遠い将来だろう。
また、記事にも書かれているが、CO2から燃料や原料を製造するには水素が必要になり、これらの製造過程とはイコール水素の消費過程である。従って本質的な問題は、水素をどう得るか? に帰着する。記事では「その水素は水から製造する、ミネラルなどの不純物を除けば海水からも生成可能だ」とある。結局は水の電気分解である。水電解による水素製造は、電力の無駄遣いに過ぎないことと何度も述べた。電気分解に使う電力を、そのまま使う方がずっとトクである。
海水をそのまま電気分解したら液相に水酸化ナトリウム、気相に水素と塩素ガスが生成する。これらをどうするつもりなのか? それとも、電解前に海水から塩分も除くつもり? 海水からの真水生成は、現在でも逆浸透法で可能であるが、それには膨大なエネルギーが要る。これまた、カーボンニュートラルから遠ざかる道である。太陽光による光分解も原理的には可能だが、効率の面で実用からはかなり遠い。
結論としてこの記事は「大気中や工場排ガスから取り込むCO2と豊富な水の組み合わせは、日本にとって有利な資源となり得る。地球温暖化の視点が本格化したことで、エネルギー源が産業革命以降主流を成した石油・石炭から大きく変わろうとしている」と書いているが、どんな「専門家」から聞きかじった知識なのだろうか?
「豊富な水」が海水を意味し、CO2源が大気であるのなら、別に日本でなくても地球上のどこでも同じことが可能なのではないのか? なぜ日本にとって有利なのか筆者には分からない。また、エネルギー「源」の捉え方が決定的に間違っていることも改めて指摘したい。水素は決してエネルギー「源」ではないから、水素を用いることでエネルギー問題が解決することはあり得ない。
水素に関しては相変わらず脳天気な記事が目立つ。例えば「世界をリードする日本の技術で「水素バリューチェーン」の構築に向かう」という記事。ここでは大手商事会社の社員3名とエネルギー問題の「専門家」が座談しているわけだが、いきなり「脱炭素社会の実現とエネルギー安定供給の両立を目指すうえで、水素が重要な役割を果たすことは間違いありません」と断言している。そして、あれをやった、これをやるつもり・・と自慢話が続くのだが、水素に関わる種々の問題点には、ほとんど全く触れていない。この点も以前に指摘した通りだ。水素推進論者たちは、水素の抱えている技術的・経済的・エネルギー収支的な問題点を狙ったようにスルーする。「見たくないものは見ない」主義としか言えない。
この座談会は何回か連載されているのだが、読んでいても夢物語ばかりで、およそ現実離れしているとしか思えない。まるで裸の王様の衣服を「まあ、これもお綺麗ですわねえ・・」と褒め合っているような錯覚を覚える。繰り返すが、科学に基づかないエネルギー論は「おとぎ話」に過ぎない。多くの人たちが目にするマスコミ上に妄想論を載せるのは、犯罪的行為である。

関連記事
-
きょうは「想定」「全体像」「共有」「平時と有事」「目を覚ませ」という話をします。多くの人は現象を見て、ああでもない、こうでもないと話します。しかし必要なのは、現象から学び、未来に活かすことです。そうしなければ個々の事実を知っていることは、「知らないよりまし」という意味しかありません。
-
経産省と国交省が進めていた洋上風力発電をめぐって、いったん決まった公募入札のルールが、1回目の入札結果が発表されてから変更される異例の事態になった。 ゲームが始まってからルールを変えた これは2020年から始まった合計4
-
経済産業省は再エネ拡大を「燃料費の大幅削減策」として繰り返し訴えている。例えば2024年1月公表の資料では〈多大な燃料費削減効果を有する〉と強調した※1)。 2022年以来、未曽有の化石燃料価格高騰が起きたから、この局面
-
福島第一原発事故は、日本人が原子力とともに生きるかどうかの選択を突きつけています。他方、化石燃料には温暖化や大気汚染などのリスクもあり、私たちの直面している問題は単純ではありません。十分なエネルギーを利用し、豊かな環境を維持しながら、私たちは持続可能な文明を構築できるのでしょうか。
-
菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ
-
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。
-
台湾有事となると、在韓米軍が台湾支援をして、それが中国による攻撃対象になるかもしれない。この「台湾有事は韓国有事」ということが指摘されるようになった。 これは単なる軍事的な問題ではなく、シーレーンの問題でもある。 実際の
-
【原発再稼動をめぐる政府・与党の情勢】 池田 本日は細田健一衆議院議員に出演いただきました。原発への反感が強く、政治的に難しいエネルギー・原子力問題について、政治家の立場から語っていただきます。経産官僚出身であり、東電の柏崎刈羽原発の地元である新潟2区選出。また電力安定推進議員連盟の事務局次長です。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間