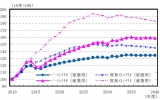何事も学ばず、何事も忘れず・・・
表題の文言は、フランス革命を逃れて亡命してきた王侯貴族たちを、英国人が揶揄した言葉である。革命で人民が求めた新しい時代への要求からは何事も学ばず、王政時代の古いしきたりや考え方を何事も忘れなかったことを指す。

sirichai_asawalapsakul/iStock
この文言は、様々な場面で有効に使えると思うが、現在の筆者から見て強く連想されるのは、昨今の「脱炭素」を巡る動きと、ウクライナ情勢をめぐる多くの日本人の対応ぶりである。
まず「脱炭素」については、これまでもあれこれ書いてきたつもりだが、何せ多勢に無勢、今でも「人為的温暖化説」がマスコミ・論壇を席巻し、「脱炭素」が正義であると言った認識が大半である。
基本のキと言うべき、気温や大気中CO2濃度変化のデータを基にした議論にはトンとお目にかからない。「温暖化の科学は決着などしていない:『気候変動の真実』」と言ったごく真っ当な論説も出ているのに、マスコミは見向きもしない。ここで紹介されているクーニンの著書などは、もっと広く読まれ、議論のタネとなるべき著書であると筆者は思うのだが。
NHKや朝日新聞など「人為的温暖化説」一色のマスコミの人々は、このような本から何事も学ばず、昔からの「人為的CO2が気候変動の元凶」とのドグマは何事も忘れない、と言うことか?
そして、政府の脱炭素政策に乗った動きだけがマスコミで大々的に取り上げられる。そこでは、それらの政策が抱えている課題や問題点が、ほとんどが意図的と思えるほどにスルーされる。その例は枚挙に暇がないほどあるが、その中から幾つかを取り上げる。
まずは、航空機燃料としての「バイオ燃料」。
バイオジェット燃料でチャーター便運航/高校生ら80人、特別フライト
これはTV各局でも取り上げられた。事前に取材依頼を念入りに行っていたのだろう。ただし、大々的に宣伝した割には、実際に飛んだのは1時間ほどで、使ったバイオ燃料は全体の10%に過ぎなかった。
しかも、この燃料は微細藻類ユーグレナから作った油脂分と廃食用油からのディーゼル燃料の混合物で、その比率は公表されていない(筆者の推測では大部分が廃食用油のはず:ユーグレナは、燃料にするより健康食品として使う方が良い:食料の方が経済価値も圧倒的に高い)。
経済性にも大きな問題を抱えている。ある放送では「ジェット燃料の10倍以上高い」と述べていたが、別の放送では「現在のジェット燃料は100円/Lだが、バイオ燃料は約1万円/L」と述べていた。これだと約100倍高いことになる(普通、不利な情報は流したくないはずだから、後者が正しいのだろうと推測する)。
今回の飛行は、80人ほどを約1時間飛ばす程度だから、PRと考えて(混入比率10%でも)少々赤字でも挙行できたのだろうが、実際の商売になるとハードルは高い。
世界のバイオ燃料生産は2021年で5000万トンにも上るが、原料の多くはパーム油・大豆油などで、廃食用油は1割程度に過ぎない。すなわち、他に本来的な用途があるのに、いきなり燃料化され燃やされている油脂類が大半なのである。筆者らは、かなり以前からこれを問題視し反対していた(「幻想のバイオ燃料」その他参照)。
日本の油脂及び油脂製品の流れを見ると、事業系・家庭系合わせて生産は年間42〜46万トン、使用後は多くが飼料用に回され、BDF(バイオディーゼル燃料)向けは10%程度、平成22年で2万KLとなっている(なぜか、平成22年=2010年以降の統計数字が見つからない・・)。
廃食用油からディーゼル燃料を作る際には、約半分に減量してしまう(約半分がグリセリンとなり、大半は廃棄される)点にも問題がある。廃食用油はむしろ、夾雑物だけ除去して、重油代替で使う方がまだマシに思える。
一方、日本の燃料油需要実績は、2019年度で約1億6千万KL(電力用C重油を除く)となっており、ジェット燃料油だけで515万KLに上る。BDF2万KLでは0.4%にも満たない(かつ、BDFの用途の大半は農業トラクター用などで、ジェット燃料などにはほとんど使われない:品質上も種々の問題を抱えているからだ)。
しかも、ジェット燃料が日本の運輸部門のエネルギー消費に占める割合は、19年度で5.1%に過ぎない。5.1%のさらに0.4%未満・・、これでよく「日本の空の脱炭素化」などと謳えるものだ。
このように、バイオ燃料はディーゼル油・バイオエタノール共に多くの問題を抱えている。化石燃料と比べて量的に少なく、製造工程を含めるとエネルギー収支が不利(→決して「カーボンニュートラル」ではない!)、かつ価格的にも安くできない(栽培や収集・加工等にコストがかかるから)。また、原料によっては食料需要を圧迫すると言う倫理的な問題もある。
バイオ燃料推進派は、実際は問題だらけなのに、全てに目を塞いで「バイオ燃料はカーボンニュートラル、脱炭素に役立つ」との呪文を唱えているだけなのだ。
ここでも、何事も学ばず、何事も忘れず・・。
筆者らはずっと以前からこの問題を論じてきた。上記「幻想のバイオ燃料」を出したのは2009年だが、この年に筆者は環境情報科学の英文誌にバイオエタノール批判の論文を載せている。査読者からトンチンカンなコメントが来て、憤慨して反論を出したが、それでも何とか掲載された記憶がある(査読付き論文誌は査読ナシよりはマシなはずだが、実際には査読者の「質」は運任せである。査読者の「質」は、論文への判定結果とコメントで分かる)。
それから13年も経ったのであるが、これらの著書や論文から、日本政府や企業のエネルギー政策担当者は、何事も学んでいないのではないだろうか・・?
バイオマス発電が太陽光発電に比べて格段に不利(単位面積当りのエネルギー収量が1/200以下)であることも、既に指摘したが、相も変わらずバイオマス発電に熱心な企業が存在するようだ。
これらの担当者に伺いたいが、日本で植林して、発電に使えるほどの樹木が持続的に供給できると、本気で思っているのだろうか?
成長の早い樹木を使うとあるが、成長が早い樹木は、当然ながら土壌からの栄養分の収奪力が強い。豪州などでは、この種の樹木栽培では約10年×2周期くらい使うと、その土地は放棄してしまう。育ちが悪くなってしまうから。つまり、この種の栽培は持続可能ではなく、土地収奪型なのである。広い豪州なら、その土地を20年も放置しておけばまたいくらか使えるかも知れないが、狭い日本でそんな悠長なことはできないはずだ。
水素・アンモニア絡みでも相変わらず科学・技術無視としか思えない試みは多いが、今回はパスして、ウクライナ情勢について書く。筆者は政治関連にはなるべく触れずにいたが、今の状況に何も発言しないでいるのは、墓場で後悔するような気がするから。
今の日本では、99%くらいの人は「ロシアだけが怪しからん、ウクライナを支援しよう」と思っているだろう。これだけマスコミが一斉報道したら、情報の真偽を疑う方がどうかしているような気がするはずだし。筆者も無論、プーチンの暴挙を擁護するつもりはない。ただちに戦争を止めるべきだと思う。これ以上死者を出すな!と。しかし、この事態を招いた大きな要因は、ウクライナのNATO加盟を強引に進めようとしたバイデンの米国と、それに乗せられたゼレンスキーの強硬姿勢にあると言う客観的な事情も無視することはできない。「泥棒にも三分の理」という言葉があるが、プーチン側にも言い分はあり、ロシアとウクライナの関係は、歴史的背景もあって、そんなに単純ではない。
しかるに、今の日本は「極悪非道のロシアをやっつけろ」の一点張りで、戦前戦中の「鬼畜米英、撃ちてし止まん」を彷彿とさせる大政翼賛会的様相を示している。もう少し、頭を冷やして考えてみたら? と言いたい。
例えば、田中宇氏が指摘するように、ロシアはゼレンスキーのビデオ演説を妨害しようと思えば簡単にできるはずなのに、なぜ容認しているのか? それだけでも不思議で、考察に値するだろう。結論的に言えば、今回のロシアの侵攻の目的は、ロシア政府の公式発表の通り、ウクライナの非武装中立化(英米傀儡からの脱却)と非ナチ化(米英に操られた極右勢力の排除)であると考えるのが自然だと言うことだ。だから、原発を破壊したり化学兵器、ましてや核兵器を使う意味はないはずだ。ロシアが本当に「劣勢で追い詰められている」のなら、なぜ、ゼレンスキーはNATO加盟を諦める、などと言い出すのか? 辻褄が合わないではないか?
戦前戦中は「鬼畜米英」だったのが、敗戦後一夜にして「米国様は神様です」に変わり、現在に至る。今は、米国の言うことなら何でもホイホイ聞く。まるで属国のように。この頭の単純さぶりは昔から全然変わっていない。
地政学的に考えたら、日本は、北からロシア・中国・東南アジア諸国・豪州という環太平洋地域諸国と関係を強化し、隣国韓国とも良い関係を築くのが、長い目で見て安全保障にも経済発展にも寄与するはずだ。米国の手先になって中露と無益な係争をしても、単に損するだけだ(現に、今すでに大損している・・)。
過去の歴史から何事も学ばず、単細胞的思考を何事も忘れずにいるようでは、日本国の将来は危うい。もっと冷静に、大局的に物事を考えるべきであることを強調したい。

関連記事
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 「要約」に環境影響についての観測の統計が図表で提示されていないのはおかしい、と指摘したが、唯一あったのはこれだ(図TS.6)。 これは、気候
-
3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。
-
原子力規制委員会は、運転開始から40年が経過した日本原子力発電の敦賀1号機、関西電力の美浜1・2号機、中国電力の島根1号機、九州電力の玄海1号機の5基を廃炉にすることを認可した。新規制基準に適合するには多額のコストがかか
-
九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。
-
エネルギー問題では、福島事故の影響で、原発に賛成か反対かという論点ばかりが議論されがちです。しかし私たちが考えなければならない問題は数多くあります。原子力規制庁、外部コストと呼ばれる社会影響、代替策についての論考を紹介します。
-
地球温暖化問題は、原発事故以来の日本では、エネルギー政策の中で忘れられてしまったかのように見える。2008年から09年ごろの世界に広がった過剰な関心も一服している。
-
原子力規制委員会は、日本原電敦賀2号機について「重要施設の直下に活断層がある」との「有識者調査」の最終評価書を受け取った。敦賀2号機については、これで運転再開の可能性はなくなり、廃炉が決まった。しかしこの有識者会合なるものは単なるアドバイザーであり、この評価書には法的拘束力がない。
-
7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間