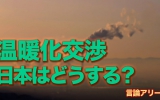企業の脱炭素は自社の企業行動指針に反する②

HadelProductions/iStock
太陽光発電の導入は強制労働への加担のおそれ
前回、サプライヤーへの脱炭素要請が自社の行動指針注1)で禁じている優越的地位の濫用にあたる可能性があることを述べました。
今回は、自家消費目的の太陽光発電導入が同じく行動指針で排除するとしている強制労働を自らサプライチェーンに招き入れてしまう可能性について考えます。
2021年6月のG7サミットおよび同年10月のG7貿易相会合の宣言でサプライチェーンからの強制労働排除が明記されました。2022年6月に米国でウイグル強制労働防止法が施行され、同年9月にはEUも禁輸措置の意向を表明しました。2022年8月には国連が中国・新疆地区で「深刻な人権侵害」が見られるとする報告書を公表しました。
近年は海外企業から日本のサプライヤー企業に対してウイグル関連の問い合わせが急増しています。現状では質問内容が新疆ウイグル自治区由来の原材料に限定されていますが、今後「エネルギー」にまで言及されたら回答に窮する日本企業が続出するのではないでしょうか。ウイグル問題は新たな社会要請となりつつあります。
一方、日本の国会では2022年2月に衆議院が、また同年12月に参議院が、それぞれ人権侵害に関する決議を採択しましたが、非難決議ではなく人権侵害に懸念を示す内容にとどまり、中国の名指しも避けました。
国際社会が中国による新疆ウイグル自治区における人権侵害、ジェノサイドに対して厳しい目を向ける中、国会の及び腰や報道の少なさのためか、日本の産業界は中国産太陽光パネルの利用に対する人道上の問題やビジネスリスクの意識がきわめて低いと言わざるをえません。東京都の新築住宅への太陽光パネル設置義務化などの動きも、産業界の危機意識が高まらない遠因になっていると思います。
後述の通り各社の行動指針の「人権」の項目では強制労働を行わないと明記していますが、ウイグル人の強制労働によってつくられた太陽光パネルから生み出された電力で事業活動を営むことは行動指針に反しないのでしょうか。部品や原材料などの直接材ではなくエネルギーはいわば間接材ですが、サプライチェーンに自らの判断で強制労働を招き入れていることになります。
さらに、脱炭素を宣言し太陽光発電を導入する企業のほとんどが行動指針に加えてSDGsへの貢献も表明しています。世界ウイグル会議のドルクン・エイサ総裁は「中国製のパネルであればジェノサイド(民族大量虐殺)に加担することになる」と訴えており、企業が中国製の太陽光パネルを利用することは「誰一人取り残さない」社会にも反してしまいます。
ここで、企業における行動指針の策定状況、ならびに人権と公正な取引に関する表明について簡単に調べてみました。対象としたのは、東洋経済新報社が毎年公表しているCSR企業ランキングです。2022年の同ランキング上位50社について各社のウェブサイトを確認しました。結果を表1に示します。

表1.行動指針等の公表状況
※ ②③が①に含まれていない場合でも、ウェブサイト上で宣言されていればカウントした
まず、当然ながらすべての企業が行動指針を策定し公表していました(①)。また、強制労働および優越的地位の濫用については、上記行動指針に含まれているか、またはウェブサイト上の他のページ(人権宣言、調達方針、など)に記載されていれば〇として集計しました。その結果、強制労働は50社すべてで表明されており、優越的地位の濫用は43社(86%)となりました。おそらく大半の大手企業、上場企業も同様の状況だと考えられます注2)。
なお、③については概念として「法令順守」「コンプライアンス」などに当然含まれますが、今回の調査では「優越的地位の濫用」「有利な立場による強制」「取引先に不利益を与える」など具体的な表記がある場合に限りました。7社については筆者の見落としがあるかもしれないことを申し添えます。
このあたりで本稿を閉めようとしていた矢先に、日米でウイグルを念頭に供給網から強制労働排除に向けた覚書を締結する、という大ニュースが飛び込んできました。経済産業省2023年1月7日付ニュースリリース「サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書に署名しました」の日本語仮訳には以下の記述があります。
エルマウにおける2022年G7首脳コミュニケ、ノイハーデンベルクにおける2022年G7貿易大臣声明、ウォルフスブルクにおける2022年G7労働雇用大臣声明、及びロンドンにおける強制労働に関する2021年G7貿易大臣声明において、強制労働は地球規模の問題であることを認め、全ての国、多国間組織企業に対し、グローバル・サプライチェーンを通じて人権及び国際労働基準を支持し責任ある企業行動についての関連原則を尊重することにコミットし、これにより強靭で持続可能なサプライチェーンに資するための明確性及び予見可能性を更に高めることを再確認し、
強制労働を含め、国際的に認められた労働者の権利の侵害は、グローバルな貿易体制において不正競争上の利益を得るために決して利用されてはならないことを認識し、グローバルな貿易体制において、強制労働の余地はないことを確認し、
※ 覚書全文はリンク先をご覧ください。
前述の通り、米国では昨年6月にウイグル強制労働防止法が施行されており、太陽光パネルを含むウイグル由来の製品が輸入禁止となっています。その米国とタスクフォースを組んでサプライチェーンからの強制労働排除に取り組むということは、日本でも同様の措置を取る可能性が出てきたことを意味します。
すでに昨年12月には米上院から日本企業を含む複数の自動車メーカーへウイグル強制労働に関する調査が行われています。日本企業としても、部材や原材料に加えて中国製太陽光パネルを利用している場合の強制労働排除について、行動指針で宣言するだけではなく具体的に考えざるをえない状況に来ているのかもしれません。
前回指摘したサプライヤーへの脱炭素要請と合わせて、自社の行動指針に反していないかサステナビリティ部門の担当者は虚心坦懐に考えてみてはいかがでしょうか。
注1)行動憲章、CSR規範、サステナビリティポリシー、コードオブコンダクト、ESG憲章、など名称は各社各様。
注2)たったのサンプル数50社で日本企業や産業界全体を推し量るのは適切ではないが、筆者は研究者ではないので厳密でなく大まかな傾向として認識できれば十分である。東洋経済のCSRランキングは500社までリンク先に出ているので、環境学部の学生さんが実施してどこかで発表してくれると筆者も嬉しい(1社あたり10分~30分ほどかかるため、50社でも年末年始のかなりの時間をこの作業に費やしてしまった)。
■

関連記事
-
「本当のことを言えば国民は喜ぶ、しかし党からはたたかれる」 石破が首班指名され、晴れてゲル首相になったのちに野党の各党首を表敬訪問した。 このふと漏らしたひとことは、前原誠司氏を訪れたときに口をついて出た。撮り鉄・乗り鉄
-
パリ協定が合意される2か月前の2015年10月、ロンドンの王立国際問題研究所(チャタムハウス)で気候変動に関するワークショップが開催され、パネリストの1人として参加した。欧州で行われる気候変動関連のワークショップは概して
-
4月21日放送映像。
-
崩壊しているのはサンゴでは無く温暖化の御用科学だ グレートバリアリーフには何ら問題は見られない。地球温暖化によってサンゴ礁が失われるという「御用科学」は腐っている(rotten)――オーストラリアで長年にわたりサンゴ礁を
-
今月末からCOP26が英国グラスゴーで開催される。もともと2020年に開催予定だったものがコロナにより1年延期しての開催となったものである。 英国はCOP26の開催国となった時点から鼻息が荒かった。パリ協定の実施元年にあ
-
今回はマニア向け。 世界の葉面積指数(LAI)は過去30年あたりで8%ほど増えた。この主な要因はCO2濃度の上昇によって植物の生育が盛んになったためだ。この現象は「グローバルグリーニング」と呼ばれる。なお葉面積指数とは、
-
米国のウィリアム・ハッパー博士(プリンストン大学物理学名誉教授)とリチャード・リンゼン博士(MIT大気科学名誉教授)が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国環
-
国のエネルギーと原子力政策をめぐり、日本で対立が続いている。いずれも国民の幸せを願ってはいるのだが、その選択は国の浮沈に関わる重大問題である。東京電力の福島第1原発事故の影響を見て曇るようなことがあってはならない。しかし、その事故の混乱の影響はいまだに消えない。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間