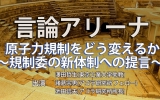「もしトラ」のエネルギー環境政策
本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。
エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであり、第一次トランプ政権はパリ協定からの離脱をはじめ、オバマ政権のエネルギー温暖化政策の否定からスタートした。
その反動でバイデン政権はトランプ政権のエネルギー温暖化政策の否定からスタートした。政権発足Day1でパリ協定に復帰したのはその典型だ。バイデン政権はオバマ政権よりも更にグリーン色が強く、トランプ陣営のリベラル派への敵愾心は第一次政権時よりも比較にならないほど強い。このため、第二次トランプ政権が誕生した場合、バイデン政権の政策からの振れ幅は第一次政権時よりも更に大きくなるだろう。
トランプ陣営への政策インプットを行っている米国第一政策研究所(America First Policy Institute)が掲げる政策提言を見れば、第二次トランプ政権が目指す方向性が相当程度に見えてくる。エネルギー温暖化政策に関する彼らの考え方は以下の通りだ。
1.エネルギー自給を実現し、輸入石油ガスへの依存を終了
- 沖合および陸上での石油・ガス生産の拡大を奨励。
- アラスカ国立野生生物保護区(ANWR)とアラスカ国立石油保護区(NPR-A)の開放。
- 重要鉱物やレアアースのエネルギー自給への明確な道筋を確立。
- ウランの採掘、転換産業における許可の合理化と規制上のハードルの除去
- 戦略的ウラン備蓄の確立
- 次世代原子力技術開発のための官民パートナーシップ
- 原子力教育、人材育成
2.エネルギー生産増大による価格引き下げ
- 生産段階から消費段階までの非効率な補助金、規制の廃止
- 退役する発電所の迅速な復旧 等
3.予測可能、透明、効率的な許可プロセスと規制環境の構築
- 市場歪曲的な補助金が系統の信頼性、レジリエンス、消費者コストに与える影響を評価
- 規制・許認可改革による環境近代化
- あるセクターを不当に標的にする新たな裁量的規制をすべて停止
4.すべてのアメリカ人にきれいな空気、きれいな水、きれいな環境を
- 環境改善と経済成長の成果を促進するために、大気浄化法(CAA)水質浄化法(CWA)国家環境政策法(NEPA)エネルギー政策節約法(EPCA)等の環境法制を近代化
- 中国をはじめとする敵対国の膨大な環境破壊と、人間への多大な影響への対処を優先
- パリ協定ではなく、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)のような意味のある強制力のある環境協定を優先
5.豊富なエネルギー輸出でエネルギー大国に
- 国際的なエネルギー・環境機関(UNFCCC、IEA、IREN等)を包括的に監査し、米国の利益に資するよう関与を適正化
- エネルギー省による30日間の審査プロセスでLNG輸出認可を合理化
- 自由貿易協定(FTA)の待遇を非FTA諸国、特にアメリカの同盟国に拡大
- 国際石油パイプライン・インフラに対する国務省の監視を緩和または撤廃
- 海外の化石燃料プロジェクトへの融資に対する障壁を撤廃
- 連邦政府による財政支援、保証、契約を受けるための要件として、国内外を問わず、再エネプロジェクトに対して少なくとも75%の国産要件
- 原子力技術の移転に必要な認可の期限を設定
全体を通じて特徴的なのは、
- 国内化石エネルギー資源の生産促進
- 補助金による再エネ支援に懐疑的
- 化石燃料生産及び関連インフラに対する規制の緩和・撤廃
- 原子力の役割を重視
- 米国のエネルギー・技術輸出による「エネルギードミナンス」
- 国際環境レジーム(パリ協定)や国際機関(IEA、IRENA等)への懐疑
である。
トランプ第二次政権が誕生すれば、第一次政権と同様、行政命令でできることを行うことになろう。Day1でやる可能性があるのはパリ協定からの離脱、LNG輸出認可凍結の解除等である。
クリーンエネルギーへの3700億ドルの補助を内容とするインフレ抑制法(IRA)はバイデン政権のエネルギー転換政策の中核だが、トランプ第二次政権の下で白紙に戻されるとは考えにくい。そのためには共和党が上下両院で絶対多数をとる必要があるし、風力を中心にIRAから受益している共和党州も多いからだ。トランプ第一次政権においても再エネに対する税額控除は続けられた。ただし原子力技術に対する支援を拡大する等、ポートフォリオの見直しはあるかもしれない。
バイデン政権の真逆を行くトランプ第二次政権であるだけに、日本への影響も大きい。第二次トランプ政権は米国内のエネルギー生産を促進し、「エネルギードミナンス」のため、同盟国への輸出拡大を図ることは確実である。
日本との間で第一次トランプ政権時代の日米戦略エネルギーパートナーシップ(JUSEP)的なものが生まれる可能性もあり、LNG供給、CCUS、原子力技術開発、バッテリー、重要鉱物等が協力分野となろう。同盟国である米国とのエネルギー関係の強化は日本のエネルギー安全保障上は概ねプラスの影響が期待される。
これまで日本はG7でバイデン政権の米国と欧州から脱化石燃料をプッシュされていたが、第二次トランプ政権の下では脱炭素に冷淡な米国と脱炭素に前のめりな欧州の間で日本は「泳ぎやすい」立ち位置となろう。
先述のように第二次トランプ政権はDay1でパリ協定から離脱することが確実だが、更にパリ協定の上位にある気候変動枠組み条約自体からも離脱する可能性がある。米国の離脱、気候資金拠出の拒否、更にはトランプ政権誕生による国際秩序、貿易秩序への衝撃により、タテマエはともかく温暖化防止に向けた国際的モメンタムが低下すること可能性が高く、1.5℃目標の死はいよいよ誰の目にも明らかになるだろう。
「日本も米国と同様、パリ協定を離脱すべき」との議論があるが、賢明な選択とは思われない。第一次トランプ政権の際も米国に続いてパリ協定を離脱する国はなかった。パリ協定から離脱すれば「温暖化防止への国際的取り組みに後ろ向き」との烙印を押されることになり、日本の国際的評判へのダメージが大きすぎる。またいずれは民主党が政権復帰するだろうが、その時にのこのことパリ協定に復帰するのでは自主性も何もない。
もともとパリ協定は京都議定書と異なり、ボランタリーな枠組みであり、46%目標、2050年カーボンニュートラル目標が未達であっても罰則などはない。アジア太平洋地域の主要貿易パートナーである米国が温暖化対策コストを負わずに安価なエネルギーを享受する中で、日本が脱炭素のために、ただでさえ高いエネルギーコストを引き上げれば日本の製造業と雇用の海外流出を招くだろう。
最大の同盟国である米国が長期的な取り組みを要するエネルギー温暖化政策分野で政権交代のたびに左右に大きく振れるのは困ったことだ。だからこそ右往左往せず、NDC (Nationally Determined Contribution)という言葉が示すとおり、国益や経済成長を毀損せず、日本の国情を踏まえた現実的な脱炭素化を追求することが重要である。
トランプ第二次政権の誕生は日本に国益と脱炭素化のバランスを改めて考える機会を与えるかもしれない。

関連記事
-
この連載でもたびたび引用してきたが、米国共和党は、気候危機など存在しないことを知っている。 共和党支持者が信頼しているメディアはウオールストリートジャーナルWSJ、ブライトバートBreitbart、フォックスニュースFo
-
6月23日、ドイツのハーベック経済・気候保護相は言った。「ガスは不足物資である」。このままでは冬が越せない。ガスが切れると産業は瓦解し、全世帯の半分は冬の暖房にさえ事欠く。 つまり、目下のところの最重要事項は、秋までにガ
-
前稿で紹介した、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」(集英社新書1071G)と言う本は、多くの国民にとって有用と思える内容を含んでいるので、さらに詳しく紹介したい。 筆者は、この本から、単にリニア新幹線の危険性
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 ■ 今回は2章「陸域・水域の生態系」。 要約と同様、ナマの観測の統計がとにかく示されていない。 川や湖の水温が上がった、といった図2.2はある(
-
世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている
-
ウォール・ストリート・ジャーナルやフォーブズなど、米国保守系のメディアで、バイデンの脱炭素政策への批判が噴出している。 脱炭素を理由に国内の石油・ガス・石炭産業を痛めつけ、国際的なエネルギー価格を高騰させたことで、エネル
-
「甲状腺異常が全国に広がっている」という記事が報道された。反響が広がったようだが、この記事は統計の解釈が誤っており、いたずらに放射能をめぐる不安を煽るものだ。また記事と同じような論拠で、いつものように不安を煽る一部の人々が現れた。
-
日本は世界でもっとも地震の多い国です。東海地震のリスクが警告されている静岡を会場に、アゴラ研究所はシンポジウムを開催します。災害と向き合う際のリスクを、エネルギー問題や環境問題を含めて全体的に評価し、バランスの取れた地域社会の在り方を考えます。続きを読む
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間