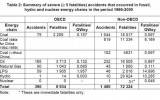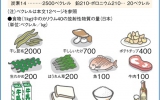教会税を払いたくないドイツ国民が炭素税を負担するか?

ilbusca/iStock
新ローマ教皇選挙(コンクラーベ)のニュースが盛り上がる中、4月30日付の「現代ビジネス」に川口マーン恵美さんが寄稿された記事「ローマ教皇死去のウラで~いまドイツで起きている『キリスト教の崩壊』と『西洋の敗北』」を読んでいて、これは!と思い当たることがあった。
同記事の論点は近年のドイツ社会における移民イスラム教徒の跋扈と、その背景にあるキリスト教の衰退、その代替物としての左翼政治イデオロギーの躍進であり、それはそれでとても説得力がある論説なのだが、そこに筆者の興味を引く記述があった。
「ドイツでの住民票はキリスト教徒であるかどうかを書き入れなくてはならず、キリスト教徒と書くと、税務署が所得税と共に自動的に宗教税を差っ引くので、それが嫌さに、正式に「脱キリスト教」する人も後を絶たない。脱キリスト教すると、結婚式も子供の洗礼もやってもらえないが、それでもいいということだ。」
ドイツに宗教税があるということを知らなかったので早速調べてみたのだが、確かに「教会税(Kirkeskat= Church tax)」が存在していた(ドイツのみならず、オーストリア、スイス、スェーデン、デンマーク、フィンランドにも同様の教会税制度があるようである)。ここでいう教会税の定義は、公的法人であるキリスト教会が、その経費を賄うために国家の承認の下でその構成員に対して一律に課す税金ということである。
ドイツではカトリック教会、福音主義(プロテスタント)教会、復古カトリック教会、ユダヤ教徒のいずれかであることを住民票に登録した国民に対して、所得税の8~9%(地域によって異なる)の教会税が課されている。この教会税がドイツ国内の教会の運営や歴史的なカテドラルの修復費用などに必要な資金の半分近くを支えているという。その2023年の総額はカトリック教会で65億ユーロ、プロテスタント教会で59億ユーロにのぼり、合わせると2兆円規模に上っていることである。
それが川口さんも指摘されているように、近年ドイツでは教会からの離脱者が増えており、2022年だけでも52万人、23年も40万人が脱会(=棄教)しているということである。確かに所得税の8~9%が追加で課されるとなるとバカにならない出費なので、もともと教会に通う人が減少している中、不景気が続くドイツで脱キリスト教宣言をする人が増えるのもやむを得ないのかとも思う。
もっとも、詳しく調べるとこの教会税は所得税の算定時に全額が所得控除されるということなので、実際の所得税額の上乗せ分は約6%程度にとどまり、平均的なドイツ人の場合、実質で年間所得の1%程度を教会税として負担するという見合いになるようである※1)。
年間所得が45,000ユーロの平均的な人の場合、信仰するキリスト教会の運営・維持のために年間約450ユーロ(約7万円、月額6千円)を、この教会税を通じて教会に寄進していることになるのだが(実際に教会に寄進されるのは政府負担となる所得税控除分が上乗せされるのでもっと大きくなる)、これを払いたくないために教会から脱会して、非キリスト教徒となったことを申告するドイツ人が増えているというわけである。
教会税を回避するためにキリスト教から離れたドイツ人は、それによって教会で結婚式や葬式を挙げることができなくなり、子供が生まれても洗礼を受けて祝福を受けられなくなる。そうした「神の恩寵」を受けるために月々6,000円を負担することを忌避する風潮がドイツ社会に広がってきているのだとすると、そうした人たちが果たして気候変動対策で今後確実に増えていくカーボンプライスを負担することを受け入れるだろうか?という疑問がわいてくる。
EUがコミットし、ドイツがリードしている欧州の気候変動対策において、その目標としている2050年温室効果ガス排出ネットゼロという目標(いわゆる1.5度目標)を達成するためには、IEAのシナリオ分析によると2030年に先進国においてCO2排出トン当たり130ドルのカーボンプライスが必要ということになっている※2)(ちなみに2040年は205ドル、2050年は250ドルである)。
一方ドイツ連邦環境省(UBA)の2023年のデータによると、ドイツ人一人当たりの年間CO2排出量は約10トンということであるから、このままの排出が続けばドイツ人は2030年に一人当たり1,300ドルのカーボンプライスを負担しなければならないことになる。仮に何らかの対策によって一人当たり排出量を半減できたとしても年間650ドルの負担である(もっとも排出量を半減するためには車をEVに乗り換え、家庭に高価なヒートポンプ暖房を設置するなどの追加的なコスト負担が必要なので、650ドルはそうした負担をした上で残った排出量に課されるカーボンプライスである※3))。
年間650ドル(約600ユーロ)の負担ということは、せっかくキリスト教を捨ててまで節約した教会税450ユーロを上回る新たな負担を背負うことを意味している。もしドイツ人が素直にこの負担を引き受けるとした場合、その背景にある意図はそれによって地球温暖化が回避・抑制され、異常気象や災害頻度が下がり、快適・安全な気候条件を取り戻すことができると信じるからと好意的に解釈されよう。
つまり気候変動政策が掲げる2050年カーボンニュートラルという目標は、それによって「地球が救われる」という救済論(あるいは何もしなければ人類が滅亡するという終末論)を掲げた、ある種の宗教的な教義ともいえるイデオロギーになっているのだが※4)、仮にそれを信じてこの年間600ユーロの「気候変動教会税」を毎年払う結果として、はたしてドイツ国民はその御利益を実感できるのだろうか?(実際にドイツ国民が負担することになるカーボンプライスは「税」ではなく、化石燃料価格や化石燃料を使って供される様々な物品、サービスの価格上昇を介して負担することになるのだが、ここではそれらを「気候変動教」の下での「救済」を得るための教会税負担として比喩的に表現している)
ドイツ国民がこれだけの負担をいとわずに温暖化対策を進めれば、確かにドイツのCO2排出量は大幅に削減できるかもしれない。しかし地球温暖化の抑止効果は一国・一地域の排出削減で発現するものではない。
パリ協定のもとで各国が宣言している削減目標(NDC)によると、世界最大の排出国は中国であり(年間排出量約110億トン)、世界全体の排出量の3割を占める中で中国は「2030年までに排出量の増加を止める」と宣言しているので、それまでは排出量は減少しないらしい。世界4位の排出国インドは、過去10年間で5億トン以上排出量を増やしていて、経済成長を最優先に掲げる同国でこれも2030年までに減少トレンドに入る見込みはない※5)。
こうした現実世界の趨勢を見たとき、ドイツ人が現行教会税を上回る「気候変動教会税」を負担して果敢に排出削減を進めたとしても、ドイツの年間CO2排出量である約6.5億トンは、向こう数年は減らないとされる中国の年間総排出量110億トンのたった6%に過ぎず、せいぜいインドが過去10年間に「増加させた排出量」と同等の水準にすぎないのである。
つまりドイツ国民がこの「気候変動教会税」を負担することで「地球が救われる」、つまり地球温暖化が回避・抑制され、その結果異常気象や天災なくなるという「御利益」を期待しているとしたら、それを2030年に実感できる可能性はほぼ「無い」といっても過言ではないだろう。
ヨーロッパ文明の長い歴史に根付き、信仰によって神の恩寵を授かり、死後の「最後の審判」で天国に行く道が保証されてきたキリスト教の信仰を捨てて教会税を払わなくなった現代社会のドイツ国民が、果たして新たな「天国」を掲げて支払いを求められるこの「気候変動教会税」を、その成果も実感できないという現実の中、ご利益を信じて払い続けることを期待できるのだろうか?
■
※1)以上の教会税の負担に関する分析は杉山大志氏がChatGPTを使って調査した結果の数字を使わせていただいている。
※2)Net Zero by 2050; A Roadmap for the Global Energy Sector” IEA (2021)
※3)EVやヒートポンプ導入には政府の補助金が期待できるかもしれないが、その財源はまわりまわって国民の税金から賄われることになるので負担増につながる。
※4)冒頭に紹介した川口さんの記事では衰退するキリスト教の代替物として左翼政治イデオロギーの躍進が指摘されているが、気候変動を教義とした代替宗教が掲げる「正義」はまさに左翼政治イデオロギーと共鳴しているといえる。
※5)政府が見せない中国とインドは脱炭素していない図を公開します(杉山 大志)

関連記事
-
小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相
-
エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供している。9月3日は1時間にわたって『地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える』を放送した。
-
3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。
-
きのう「福島県沖の魚介類の放射性セシウム濃度が2年連続で基準値超えゼロだった」という福島県の発表があった。これ自体はローカルニュースにしかならなかったのだが、驚いたのはYahoo!ニュースのコメント欄だ。1000以上のコ
-
第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」
-
アゴラ研究所、また運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。
-
2022年11月7日、東京都は「現在の沿岸防潮堤を最大で1.4 m嵩上げする」という計画案を公表した。地球温暖化に伴う海面上昇による浸水防護が主な目的であるとされ、メディアでは「全国初の地球温暖化を想定した防潮堤かさ上げ
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間