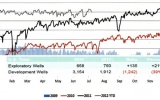腐敗した気候科学を叩き直すトランプ大統領命令に日本も倣え
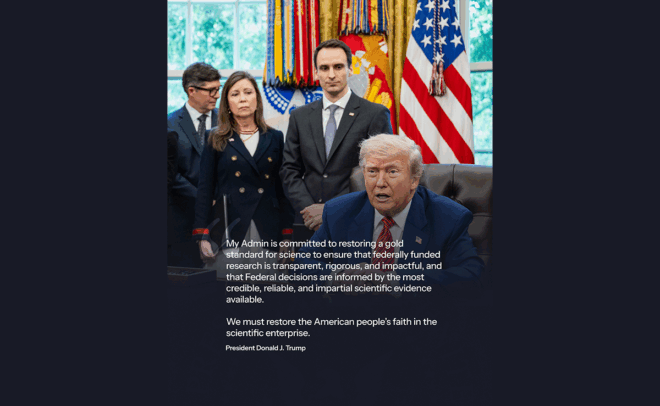
大統領令に署名するトランプ大統領
ホワイトハウスXより
5月23日、トランプ大統領は、 “科学におけるゴールドスタンダードを復活させる(Restoring Gold Standard Science)”と題する大統領令に署名した。
バイデン政権の下では、気候変動問題を筆頭として、公衆衛生問題や環境問題において、根拠が乏しくブラックボックス的なシミュレーション結果が「科学」の衣をまとって流布され、それに基づいて左翼リベラル的な政策を推進することが行われてきた。それを正そうとするものだ。
以下は大統領令からの抜粋である。
政府の機関は保有する以下の情報を公開する:
(A) 機関が作成または使用した科学的・技術的情報(機関が重要な公共政策または重要な民間部門の決定に明確かつ重大な影響を与えると合理的に判断した情報(影響力のある科学的情報))に関連するデータ、分析、結論(ピアレビューされた文献で引用されたデータを含む);および
(B) 影響力のある科学的情報を生成するために当該機関が使用したモデルおよび分析(該当する場合、当該モデルのソースコードを含む)。職員は、OSTP局長への事前通知を経て、当該機関の長から書面による承認を得ない限り、情報公開法の免除規定を根拠に、このようなモデルの開示を拒否することはできない。
シミュレーションについても、ブラックボックスは許されず、透明性を持って公開しなければならない、ということだ。
気候変動問題に関しては、非現実的に排出量の多いRCP8.5シナリオが「なりゆき」として使われていることを名指しで問題視している:
政府の機関は気候変動の「より高い」温暖化シナリオにおける潜在的影響を評価するために、代表的濃度経路(RCP)シナリオ8.5を採用している。RCP 8.5は、世紀末の石炭使用量が回収可能な石炭埋蔵量の推定値を超えるなど、極めて可能性の低い仮定に基づく最悪のシナリオです。科学者は、RCP 8.5を「可能性の高い結果」として提示することは誤解を招くと警告している。
この大統領令には、物理学者ウィリアム・ハパーとリチャード・リンゼンが実施した1か月前の4月28日付の政策提言が色濃く反映されている(この報告書は、ホワイトハウス、規制当局の全責任者、両党の政治指導者に提出されたとのこと)。
この政策提言も一部を抄訳しよう:
4. 機能しないモデル
モデルは理論の一種であり、物理的観測を予測するものである。科学的方法論では、モデルが観測で検証されるかどうかを確認するためにテストすることを要求する。 モデルの予測が、現象の観測結果と一致しない場合、そのモデルは誤っており、科学として使用してはいけない。気候危機の物語を支えるモデルは、予測する現象の観測結果と一致していない。代わりに、二酸化炭素(CO2)排出の温暖化効果を過大評価し、観測された値の2倍から3倍の温暖化を予測している。・・・
5. 選択的、捏造、改竄、または省略された矛盾するデータ
理論は観測で検証されるため、データを捏造したり、改竄したり、矛盾する事実を省略して理論を成立させようとすることは、科学的方法の重大な違反である。・・・
私たちの一人(リンゼン)は次のように指摘する:「誤った表現、誇張、選択的引用、または明白な虚偽といった行為は、ネットゼロ理論を支持するために提示されたいわゆる『証拠』のほとんどに該当する」・・・
要約すると、科学的知識とは、科学的方法論によって決定され、理論を観測で検証するものであり、政府の意見、コンセンサス、ピアレビュー、選択的引用、捏造、改竄、または矛盾するデータを省略するといったものであってはならない。
科学的手法とは、経験的なデータによる仮説の検証を重視し、真実の追求において絶対的な誠実さを要求する、何世紀にもわたる探求のアプローチである。
しかしながら、気候の研究では、この伝統的なプロセスが集団思考に取って代わられることがあまりにも多い。 いわゆるコンセンサスを形成し維持するために、科学的な議論は抑圧されてきた。 バイデン政権の下、米国の政府機関は、人為的な気候危機というシナリオを推進するために、虚偽で誤解を招くような偏った情報を流してきた。
日本においても、気候変動に関する科学は捻じ曲げられている。米国に見習って、科学のゴールドスタンダードを復活させねばならない。
■

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
-
サプライヤーへの脱炭素要請が複雑化 世界ではESGを見直す動きが活発化しているのですが、日本国内では大手企業によるサプライヤーへの脱炭素要請が高まる一方です。サプライヤーは悲鳴を上げており、新たな下請けいじめだとの声も聞
-
先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。
-
メディアが捏造する分断 11月中旬に北海道の寿都町を訪ねる機会を得た。滞在中、片岡春雄町長や町の人たちに会い、また、街の最近の様子を見て雰囲気を感じることもできた。私が現地に着いた日の夜、折しもNHKは北海道スペシャル「
-
米国が最近のシェールガス、シェールオイルの生産ブームによって将来エネルギー(石油・ガス)の輸入国でなくなり、これまで国の目標であるエネルギー独立(Energy Independence)が達成できるという報道がなされ、多くの人々がそれを信じている。本当に生産は増え続けるのであろうか?
-
沸騰水型原子炉(BWR)における原子炉の減圧過程に関する重要な物理現象とその解析上の扱いについて、事故調査や安全審査で見落としがあるとして、昨年8月に実証的な確認の必要性を寄稿しました。しかし、その後も実証的な確認は行わ
-
英国の新聞の社説は、脱炭素に対する「反対」が「賛成」を、件数で上回る様になった(図)。 環境団体のカーボンブリーフがまとめた記事だ。 Analysis: UK newspaper editorial opposition
-
自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間