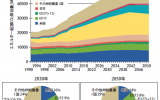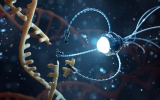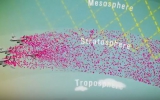複雑怪奇な温暖化対策制度では経済成長などできない

Tomwang112/iStock
GX推進法の改正案がこの5月に可決され、排出量取引制度の法制化が進んでいる。教科書的には、「市場的手段」によって価格を付けるのが、もっとも経済効率が良いことになっている。
だが、日本の場合、排出量取引制度は、既存の制度に、さらに追加されるだけで、全体としての温暖化対策制度はますます複雑怪奇になる。まるで、増築を重ねたオンボロ温泉旅館のようである、と言ったら、AIが絵を描いてくれた。

日本の温暖化対策制度の概要を書くと、表1のようになる。直接規制があり、補助金があり、税があり、自主的取り組みがあり、自治体には、政府と別の制度がある。
事業者は経産省と環境省と自治体に似たり寄ったりの報告書を毎年書かねばならない。そうかと思えば、温暖化対策に逆向きの補助金として電気とガソリン等への累積12兆円の補助金などというのもある。足下ではこんなばらまきをやっておきつつ、今後は「市場的手段」として、GX-ETS(排出量取引制度)と化石燃料課徴金が追加される予定になっている。
もしもこれが、例えば「化石燃料課徴金」だけの1本にして、他の制度はすべて廃止します、というのであれば、まだ納得感はある。だがそうではない。これら沢山ある制度には、それぞれなわばり、権限、予算が発生し、役人は自ら制度を簡素化する動機も能力も欠いているため、制度は年々肥大化し、複雑化する一方だ。
税は「簡素・中立・公平」であるべきだという原則があることはよく知られている。この原則は、制度先般にとっても重要なことだ。
表1 日本の温暖化対策制度(主なもの)
| 手段類型 | 主要制度・法令(施行/開始) | 主体・対象 | 義務・税率等 |
| 直接規制 | 省エネ法(1979→改正継続) | 工場・事業所/輸送/建築物/家電・自動車 | エネルギー管理・燃費/省エネ基準・DR等 |
| エネルギー供給構造高度化法(2009) | 電力小売(5億kWh超) | 2030 非化石44%義務+罰則 | |
| 補助・賦課型 | 再エネ特措法(FITとFIP)(2012→FIP22) | 再エネ発電事業者 | 固定価格/プレミアム買取(賦課金で回収) |
| 燃料油・電力・ガス補助(激変緩和事業)(2022‑25) | 需要家(価格転嫁) | 元売・小売に定額補助 累計12兆円 | |
| 市場的手段 | GX推進法:GX‑ETS(自発23→義務26) | 直接排出10万t超事業者 | キャップ&オークション・排出権取引 |
| 化石燃料賦課金(2028予定) | 化石燃料輸入者等 | 段階的 t‑CO₂課金(GX債償還財源) | |
| 税 | 石油石炭税(温対税含む)(1978/2012増税) | 化石燃料全般 | 289 円/t‑CO₂相当 |
| 揮発油税・軽油引取税など(1940s‑) | 自動車燃料 | 53.8 円/ℓ(暫定税率込み)等 | |
| 自主協定 | 経団連低炭素社会実行計画(1997‑) | 約35業種 | 自主削減目標・第三者評価 |
| 横断法 | 地球温暖化対策推進法(1998) | 国・自治体・企業 | 排出量報告・計画策定・情報公開 |
| 自治体 | 東京都キャップ&トレード(2010‑)、東京都・京都府等の太陽光義務ほか | 大規模事業所/新築住宅・非住宅 | 独自キャップ、PV設置義務、EV充電義務 |
さて、以上は国全体の話であったが、部門別に見ても、制度は複雑怪奇である。表2は、電力部門についてまとめたものだ。
石炭火力で発電事業をしようと思ったら、いったいどれだけの制度が待ち構えているだろうか?
まず直接規制として、省エネ法の「効率ベンチマーク」で、効率の低い発電設備は早期廃止やリプレースを迫られる。さらに、電気事業法にもとづく環境影響評価では、「環境大臣意見」によって、石炭火力の新設が事実上禁止されるようになった。2018年以降、石炭火力発電の新設計画5件は全て撤回されるに至っている(環境大臣意見の例として:「秋田港火力発電所(仮称)建設計画に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について」)。
これに加えて排出量取引制度が導入されることになっているのだが、これで発生するコストは、すでに存在する石油石炭税に上乗せされることになる。この石油石炭税には「温暖化対策上乗せ分」もすでにある。つまり石炭には、1トンあたりで、本則税率700円に温暖化対策上乗せ分が670円で、合計1,370円が課されている。
再エネの導入に関係する制度も多岐にわたる。直接規制であるエネルギー供給構造高度化法では、小売り電気事業者は2030年までに非化石電力の割合を44%にする義務があり、これは証書を買ってでも達成しなければならない。
省エネ法には、変動性再エネに対応するための需要調整が盛り込まれた。容量市場は、再エネの変動に対応するために設けられた。そして何より、再エネ事業はFITやFIPによって補助を受けて推進されている。GX移行債を用いた基金では低利ローンの貸付がある。自治体も国とは別に太陽光パネルの義務付けや排出量取引制度などを儲けている。
表2 日本の電力部門における温暖化対策制度(主なもの)
| 手段類型 | 制度 | 対象 | 義務・税率等 | 開始・最新改正 | メモ |
| 直接規制 | エネルギー供給構造高度化法 | 年販電5億 kWh超の小売電気事業者 | 2030 非化石44%義務(未達→罰則) | 2009制定/2022改正 | 非化石価値証書購入によるコスト増。 |
| 省エネ法:火力発電効率ベンチマーク | 主要火力発電所(出力20 万 kW以上) | LNG複合 ≥52%HHV、石炭超々臨界 ≥44%HHVなど。未達の場合は改善計画提出・公表 | 2010制度化/2023見直し | 火力発電設備の早期廃止・リプレース圧力。 | |
| 省エネ法(DR・需要側調整義) | 一般送配電・小売 | 調整力専用契約、DR計画 | 2023改正 | 変動再エネへの対応コスト | |
| 電気事業法(設備認可時環境審査) | 発電事業者 | 設置許可時に環境影響評価(EIA)・BAT審査を審合。 | 常時 | 新規純石炭火力の許可は2018年以降事実上禁止 | |
| 市場的手段(価格付け) | GX‑ETS(排出量取引) | 10万 t‑CO₂超排出発電所 | 2026〜義務キャップ | 2023施行 | 排出権買入れコスト |
| 非化石価値取引市場 | 小売電気事業者 | 証書調達で非化石比率充足 | 2018市場開始 | 証書調達コスト | |
| 容量・調整力市場 | 発電・需要家 | 調整力を入札で価格化 | 2021本格 | 再エネ変動対応費を反映。 | |
| 税・賦課金 | 石油石炭税(温対税含む) | 化石燃料輸入者 | 289円/t‑CO₂相当上乗せ | 2012温対税導入 | 税負担 |
| 化石燃料賦課金(GX賦課金) | 化石燃料輸入者 | 2028開始、段階増税 | 2025法改正 | 賦課金負担 | |
| 再エネ賦課金(FIT/FIP) | 小売電気事業者 | 3.98円/kWh(25年度) | 2012〜 | 総額で年2.7 兆円。 | |
| 電源開発促進税 | 小売転嫁 | 0.375円/kWh | 1974〜 | 原子力・立地関連財源。 | |
| 補助金・投融資 | FIT/FIP支払(再エネ特措法) | 再エネ発電 | 固定価格/プレミアム | 2012/22 | 再エネへの補助 |
| 省エネ法関連補助:エネルギー使用合理化等事業者支援(NEDO等) | 発電・送配電事業者 | 高効率火力への更新、発電所熱効率向上設備に1/3〜1/2補助 | 毎年度予算 | 火力発電省エネへの補助 | |
| グリーンイノベーション基金 | 電力・メーカー | 水素・アンモニア火力、CCS実証 | 2021〜 | 中長期の脱炭素技術投資。 | |
| 送配電網・蓄電池補助 | 一般送配電 | 系統増強・蓄電池1/2補助 | 補正予算ベース | 再エネ大量導入の系統対応を補助 | |
| GX移行債基金 | 電力・再エネ・送配電事業 | 国が最大20兆円規模で債券発行し、水素・アンモニア火力、CCS、系統増強、再エネ低利融資に充当。 | 設備費の1/3〜1/2補助、長期(20年)0.4〜0.7%融資 | ||
| 情報公開・自主協定 | 経団連カーボンニュートラル行動計画(電力) | 発電事業者 | 2030▲46%自主目標 | 2021改編 | |
| 排出量報告・公表(温対法) | 発電所 | 年度排出量報告 | 2006〜 |
再エネに関しては、電力を購入する一般の事業者の方にも制度がある。再エネ賦課金を支払わねばならないし、省エネ法では、再エネを導入する計画を政府に提出して、進捗状況を定期的なチェックを受けることが義務づけられている。
この複雑怪奇な制度は「ポリシーミックス」だとか「政策の総動員」といったレトリックで美化されてきた。しかしそこには、報告書の作成といった手続き面と、投資判断などの企業行動の実体面の両方においての、莫大な無駄が発生する。この認識が、政府にも、政治家にも全く欠落している。このような状態であれば、日本がいつまでも経済成長できないのも、さもありなんである。
■

関連記事
-
エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。
-
『羽鳥慎一のモーニングショー』にみられる単純極まりない論調 東京電力管内で電力需給逼迫注意報が出ている最中、今朝(29日)私はテレ朝の「羽鳥慎一のモーニングショー」をみていました。朝の人気番組なので、皆さんの多くの方々も
-
夏も半分過ぎてしまったが、今年のドイツは冷夏になりそうだ。7月前半には全国的に暑い日が続き、ところによっては気温が40度近くになって「惑星の危機」が叫ばれたが、暑さは一瞬で終わった。今後、8月に挽回する可能性もあるが、7
-
日米のニュースメディアが報じる気候変動関連の記事に、基本的な差異があるようなので簡単に触れてみたい。日本のメディアの詳細は割愛し、米国の記事に焦点を当ててみる。 1. 脱炭素技術の利用面について まず、日米ともに、再生可
-
経産省が、水素・アンモニアを非化石エネルギー源に位置づけるとの報道が出た。「製造時にCO2を排出するグレー水素・アンモニアも、燃焼の瞬間はCO2を出さないことから非化石エネルギー源に定義する」とか。その前にも経産省は22
-
今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。
-
AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント
-
IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間