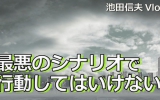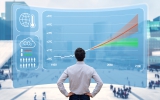COP30最大のリスクは気候でも森林でもなく宿泊問題だ

Md Zakir Mahmud/iStock
COP30議長国ブラジルは11月にベレンで開催されるCOP30を実行力(Implementation)、包摂(Inclusion)、イノベーション(Innovation)を合言葉に、アクション中心の会議にすることを目指しており、グローバル共同作業(Global Mutirão)と呼ばれるイニシアティブを提案している。
「Mutirão」とはブラジルのポルトガル語で「地域住民が自主的に協力し合って行う共同作業」を意味する言葉である。「グローバル共同作業」はこれを地球規模に拡張したものであり、気候変動への対応を政府だけでなく都市、企業、NGO、先住民族、若者、市民社会等、多様な主体の「共同作業」として位置付け、それぞれの役割で協力するプラットフォーム形成を目的としている。
政府が主体となる国別貢献(NDC:Nationally Determined Contribution)に対し、多様な主体が参加するグローバル貢献(Globally Determined Contribution)による国境を超えた協力を提唱している。
またベレンはアマゾン森林を有するため、COP30では森林保全を中心テーマに据えている。年間40億ドル規模の「Tropical Forests Forever Facility(TFFF)」という基金構想(1ヘクタール4ドル)による熱帯林の保全を軸に、途上国や地域社会・先住民族への資金還元を目指している。
さらにCOP29で掲げられた「2035年までに年間1.3兆ドルの気候資金を動員する」目標に向けた「1.3兆ドルに向けたバクー・ベレムロードマップ(Baku to Belem Roadmap to 1.3 T)の実行も議論される予定だ。
グローバル共同作業やグローバル貢献はアイデアとしては理解できるものの、その実現に向けたイメージが不明確であり、TFFFにせよロードマップにせよ、先進国も経済情勢が厳しく、途上国支援の拡大に向けた納税者の理解を得にくいことを考えれば、COP30の見通しは決して明るいものではない。
しかしこうした中身の問題とは別にCOP30を失敗に終わらせる最大のリスクは宿舎問題だ。COP期間中に開催地のホテルの値段が高騰することは決して珍しいことではない。ただ、COP30では5万人人近くの参加が見込まれる一方、開催地ベレンのホテルインフラは圧倒的に不足している。
この点については今年初めから各国政府が強い懸念を表明しており、一時は首脳セッション等の象徴的なイベントはベレンで開催するも、その他の会議はリオデジャネイロやサンパウロ等の大都市で開催するとの希望的観測も流れたが、ブラジルはベレン開催にあくまでこだわった。
6月の準備会合ではブラジル政府によるロジ(運営・宿泊計画)の説明会が開催され、「早急に政府によるホテル予約サイトを立ち上げる。現在、ホテルの建設を進めており、クルーズ船を宿泊用に利用することも検討している」とのことであったが、公式ホテル予約サイトの立ち上げは8月までずれ込んだ。
さらにベレンのホテルがこれまでのCOPと比較しても法外な価格を請求していることが各国の強い怒りを買っている。筆者は11月16日~22日まで7泊するが、その代金が約100万円(!)である(ちなみに9月の1週間の滞在費用は6万円くらいである)。
このような「ぼったくり」がベレン中のホテルで生じており、一部の途上国政府は会議への不参加、代表団規模の縮小を検討している。各国政府からはブラジルに対し、より宿泊施設の充実しているリオデジャネイロ、サンパウロ等の大都市に移すことを求めているが、ブラジルは頑としてこれに応じていない。
世界最大の熱帯雨林を有するアマゾン川の河口であるベレンの開催という象徴的意義にこだわっているのだろう。
8月22日のブラジル政府と気候変動枠組み条約事務局の打ち合わせの際、国連側は発展途上国の代表団に1日当たり100ドル、先進国の代表団に同50ドルの宿泊代補助を求めたが、ブラジル側は「ブラジル政府はすでにCOP30開催のために多大な費用を負担しており、ブラジルよりはるかに豊かな国々を含む他国の代表団を補助する余裕はない」との理由でこれを拒否している。途上国の中には本当に参加見合わせ、代表団縮小を強いられる国も出てくるだろう。
筆者のこれまでの経験に照らせば、開催地の宿泊事情、会場との交通、会場の設備(トイレ、飲食物の値段等)等のロジ面で参加者に強い不満を感じさせるCOPが成功したためしはない。
その典型的な事例は会場のキャパシティを大幅に超える人数を参加登録し、多くの人を雪のふりしきる戸外で行列させたコペンハーゲンのCOP15(2009年)であり、会議運営の拙劣さもあり、「デンマークに2度と大きな会議の主催をやらせるな」とさえ言われるようになった。
今回のCOP30の宿泊をめぐるトラブルがこのまま続けば、会議の成否そのものも危うくなろう。疑いなく宿泊問題はCOP30最大のリスクだ。

関連記事
-
西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし
-
原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。
-
2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2
-
小泉環境相が悩んでいる。COP25で「日本が石炭火力を増やすのはおかしい」と批判され、政府内でも「石炭を減らせないか」と根回ししたが、相手にされなかったようだ。 彼の目標は正しい。石炭は大気汚染でもCO2排出でも最悪の燃
-
日本の学者、国会議員らが、4月に台湾(中華民国)の学会の招待で、台湾のシンポジウムに参加し、馬英九総統と会見した。その報告。日台にはエネルギーをめぐる類似性があり、反対運動の姿も似ていた。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
福島では原子力事故の後で、放射線量を年間被曝線量1ミリシーベルトにする目標を定めました。しかし、この結果、除染は遅々として進まず、復興が遅れています。現状を整理し、その見直しを訴える寄稿を、アゴラ研究所フェローのジャーナリスト、石井孝明氏が行いました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間