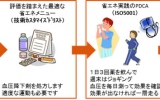気候変動をどう捉えるか:米天体物理学者が語る“Climate Change Forever”

Cimmerian/iStock
はじめに
近年、日本社会では「カーボンニュートラル」「脱炭素」といった言葉が政治や産業、さらには教育現場にまで浸透し、あたかもCO₂削減こそが唯一の解決策であるかのように語られています。電力システム改革や再生可能エネルギー導入、EVシフトなど、多くの施策がこの前提のもとに展開されています。
しかし、世界に視野を広げると、この前提に真っ向から異議を唱える科学者たちが存在します。その一人が、米国の天体物理学者Willie Soon博士です。博士は長年にわたり太陽活動と気候変動の関係を研究し、CO₂主因説に疑問を投げかけ続けてきました。主流の気候科学から激しい批判を受けつつも、国際的に一定の支持を獲得し、いまも積極的な講演・論文発表・寄稿活動を続けています。
このたびSoon博士は、米誌 The New American に “Climate Change Forever” という記事を寄稿しました。本稿では、その要点を紹介するとともに、日本における議論にとってどのような意味を持ち得るかを考えてみたいと思います。
記事の要点
1. 気候変動は「永遠に続く」
地球の歴史を遡れば、氷期と間氷期が繰り返され、急激な寒冷化や温暖化が繰り返し訪れてきました。恐竜時代の高温期、中世温暖期、小氷期など、いずれも人為的なCO₂排出とは無関係に起こっています。
Soon博士は「気候は常に変動し続けるのが本来の姿である」と述べ、現代の温暖化を特別視し「危機」と呼ぶことそのものに疑問を投げかけています。つまり、変化そのものが正常であり、安定不変こそが例外的なのだという視点です。
2. CO₂の影響は過大評価されている
現在の主流的な気候科学は、人為起源のCO₂を中心に据えたモデルに依拠しています。気候モデルは温室効果ガスの濃度変化を大きく増幅させる前提を置き、未来予測を描きます。
しかし博士は、太陽活動や宇宙線、海洋循環、雲形成、火山活動といった自然要因の寄与を軽視してはならないと強調します。たとえば太陽黒点活動の変動は地球の放射収支に影響を与え、長期的な気候変化を引き起こす要因として無視できません。CO₂だけを「悪役」に据える現在の枠組みは、科学的なバランスを欠いていると批判します。
3. 政策のリスクと経済への影響
記事の中で博士は、気候政策が経済や社会に与える副作用にも警鐘を鳴らしています。化石燃料の利用を制限することは、エネルギーコストの上昇をもたらし、生活水準の低下や産業の国際競争力の低下を招きます。特にエネルギーを安価に供給することが成長の前提である途上国にとっては、開発の阻害要因となり、格差拡大につながりかねません。
博士は「科学的根拠ではなく政治的イデオロギーが先行している」と述べ、拙速な政策決定の危うさを指摘しています。
4. 「気候危機」という物語の正体
「気候危機」という言葉はメディアや国際会議、政策文書に頻繁に登場します。博士はこれを「ナラティブ(物語)」にすぎないと喝破します。人々に危機感を植え付けることで、再エネ拡大やカーボンプライシングなど特定の政策を正当化する道具となっている、というのです。科学的な検証よりも政治的な利用価値が優先される現状を、博士は強く批判しています。
Willie Soon博士という人物
Willie Soon博士は、ハーバード=スミソニアン天体物理学センターに長く所属し、太陽黒点や磁場の変動と気候の関係に焦点を当ててきました。特に「太陽活動と地球気候の相関」に関する研究は注目を集め、CO₂の影響を相対化する数々の論文を発表してきました。
一方で、エネルギー関連企業から研究資金を受け取った経歴が報じられ、米国内では激しい批判の的となりました。資金提供者と結論の独立性をめぐっては議論が絶えません。しかし博士は「資金源と研究結果は切り離して評価すべきだ」と反論し、発信を続けています。
米国では彼を「産業の代弁者」とみなす声もありますが、国際的には講演やシンポジウムに招かれ、多くの市民団体や研究者から支持を得ています。異端とされる存在であっても、その視点が議論に厚みと多様性をもたらしているのは確かです。
博士の研究スタイルは、気候モデルの不確実性に光を当て、「複雑な気候システムを単純化しすぎる危険性」を訴えることにあります。こうしたアプローチは、合意形成を急ぐ国際政治においては不都合に映るかもしれませんが、科学の本質に立ち返る姿勢として評価する向きもあります。
日本への示唆
日本では「気候変動=CO₂増加の帰結」という理解がほぼ唯一の選択肢として政策に組み込まれています。温室効果ガス排出量削減が国際公約となり、産業界もそれを前提に投資計画を立てざるを得ません。
しかし海外に目を向けると、Soon博士のように自然要因を重視し、CO₂主因説に異を唱える科学者が少なからず存在します。国際的な議論は必ずしも一枚岩ではなく、多様な科学的見解がせめぎ合っています。
この現実を知るだけでも、私たちの思考の幅は広がります。主流派の研究者は「Soon博士はデータの取り扱いが恣意的だ」と批判しますが、それ自体が健全な科学的論争です。重要なのは、単一の見解だけを政策に直結させるのではなく、異なる視点を突き合わせることです。その結果、エネルギー安全保障や経済成長と環境保護をいかに両立させるかという現実的な道筋が見えてくるはずです。
また、日本は資源制約の強い国であり、エネルギーコストの上昇は国民生活や産業競争力に直結します。「気候危機」の物語に基づいた一方向的な政策は、日本にとってリスクが大きい可能性があります。Soon博士の主張は、必ずしも全面的に受け入れるべきものではありませんが、少なくとも政策形成における「盲点」を示す鏡として参照する価値があるでしょう。
おわりに
Willie Soon博士の “Climate Change Forever” は、CO₂主因説を相対化し、「気候は常に変動してきた」という視点を鮮明に打ち出した論考です。日本ではあまり紹介されることのない立場ですが、国際的な議論の多様性を知ることは、私たちにとって重要な学びとなります。
この記事をどう評価するかは各人の判断に委ねられますが、少なくとも「唯一の真実」が存在するかのように語られる現状に疑問符を投げかける契機にはなるでしょう。
科学的知見は常に更新され、異論や反論の中からより妥当な理解が形成されていきます。Soon博士の声を紹介することは、そうした健全な科学的営為を支える一助となり得るのではないでしょうか。AGORAの読者には、この問題をめぐる多様な議論を手がかりに、自らの立場を再考する契機としていただきたいと思います。

関連記事
-
英独仏を含む欧州7か国が、海外における化石燃料事業への公的支援を段階的に停止する、と宣言した。 だが、もちろんアフリカには経済開発が必要であり、化石燃料はそのために必須だ。このままでは、先進国の偽善によって、貧困からの脱
-
米国では温暖化対策に熱心なバイデン政権が誕生し、早速4月22日に気候サミットを主催することになった。これに前後してバイデン政権は野心的なCO2削減目標を発表すると憶測されている。オバマ政権がパリ協定合意時に提出した数値目
-
今回は英国の世論調査の紹介。ウクライナ戦争の煽りで、光熱費が暴騰している英国で、成人を対象にアンケートを行った。 英国ではボリス・ジョンソン政権が2050年までにCO2を実質ゼロにするという脱炭素政策(英国ではネット・ゼ
-
アマゾンから世界へ 2025年11月、COP30がブラジル北部アマゾンの都市ベレンで開催される。パリ協定採択から10周年という節目に、開催国ブラジルは「気候正義」や「持続可能な開発」を前面に掲げ、世界に新しい方向性を示そ
-
日本の鉄鋼業は、世界最高の生産におけるエネルギー効率を達成している。それを各国に提供することで、世界の鉄鋼業のエネルギー使用の減少、そして温室効果ガスの排出抑制につなげようとしている。その紹介。
-
6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ
-
バイデン大統領は1.5℃を超える地球温暖化は「唯一最大の、人類の存亡に関わる、核戦争よりも重大な」危機であるという発言をしている。米誌ブライトバートが報じている。 同記事に出ている調査結果を見ると「人類存亡の危機」という
-
BBCはいま炎上している。内部告発された文書によって、2021年1月6日のトランプ大統領の演説を勝手に切り張りして報道したことが明るみに出たからだ。 トランプは、本当は「平和的な」行進を呼び掛けていたのに、この「平和的」
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間