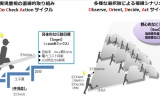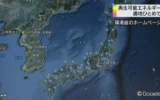ビル・ゲイツが気候危機説の否定に君子豹変して界隈はてんやわんや

ビル・ゲイツ氏
Gates Foundationより
ご存じの方も多いと思いますが、先月末にビル・ゲイツ氏が気候変動対策への主張を転換しました。
ビル・ゲイツ氏、気候変動戦略の転換求める COP30控え | ロイター
米マイクロソフト創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏は28日、ブラジルで開かれる国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議(COP30)を前に、異常気象に順応し、気温の抑制目標よりも健康状態の改善に焦点を当てるよう世界の指導者らに呼びかけた。
(中略)
ゲイツ氏は個人ブログで、気候変動は深刻ではあるが、「文明を終わらせるものではない」と投稿。気温を最良の指標とするよりも、健康や繁栄を強化することによって気候耐性を高める方がより効果的だと述べた。
このゲイツ氏の豹変に対して気候危機界隈は上を下への大騒ぎになっています。たとえば、コロンビア大学のジェフリー・サックス教授や、ペンシルベニア大学のマイケル・マン教授など多くの著名人が猛批判しています。
Bill Gates’s Climate U-Turn: Real Epiphany or Expedient Pivot? – Watts Up With That?
悪名高い地球温暖化の「ホッケースティック」曲線をでっち上げたペンシルベニア大学のマイケル・マンは、ハフポストに対し「近年、ゲイツの気候変動に関するレトリックに憂慮すべき変化が見られる」と記した。
(中略)
コロンビア大学持続可能な開発センター所長で国連持続可能な開発ソリューションネットワークの会長であるジェフリー・サックス氏が、ゲイツ氏のエッセイを「無意味で、曖昧で、役に立たず、混乱を招く」と呼んだと報じた。
(中略)
マンがグレタ・トゥーンベリのように憤慨して「よくもそんなことが言えるものだ!(How dare you?)」と叫ぶ姿が想像できる。
一方で、コペンハーゲン・コンセンサス研究所のビョルン・ロンボルグ博士など、ゲイツ氏を称賛する声も上がっています。
Bill Gates Delivers ‘Tough Truths’ on Climate Just Before Big U.N. Talks – Newsweek
「素晴らしいし、勇気ある発言でもあると思います」と政治学者のビョルン・ロンボルグはゲイツのエッセイについて語った。ロンボルグはコペンハーゲン・コンセンサス・センターの代表であり、気候変動への対応よりも人類が直面する他の脅威の方が重要だという反対意見で知られる。「排出削減は世界の貧困層にとって最も重要なことではない」とロンボルグはNewsweekに語った。ゲイツ氏のエッセイはロンボルグの見解に非常に近く、ゲイツ財団がコペンハーゲン・コンセンサス・センターの一部の活動に資金提供していることも付け加えた。
ゲイツ氏は気候変動緩和策重視から適応策重視へ転換しました。以前から【適応一番 緩和は二番 惨事の回避が優先だ~】を合言葉にしている筆者としては、まさに我が意を得たりです!
筆者は、CO2削減などの緩和策は経済合理性の範囲内で行えばよく、国家や企業において限られた予算やリソースを地球温暖化対策に使うのであれば適応策にこそ振り向けるべきと考えてきました。
筆者個人は無謀なカーボンニュートラル・46%削減・再エネ大量導入には断固反対の立場であり、原発再稼働や火力発電のリプレースなど経済合理性を伴う現実的な緩和策を行ったうえで、余力を水害対策や都市の高台移転といった適応策に振り向けるべきというのが持論です。
国民生活や企業の国際競争力を破壊してまで緩和策(脱炭素政策)に莫大な予算を投じたところで、その効果は地球の大気全体で薄まり日本の影響はごくわずかとなります。一方で、適応策では投入したリソースがその場所・その地域ですべて効果として現れます。もちろん、現実には対策の遅延や不足、また想定を上回る自然災害が発生することはありますが、地球全体で効果が薄まることはありません。
今回、ゲイツ氏は観念的な気候危機論・脱炭素原理主義から現実路線へ転換しました。自らの過去を否定するというのは非常に難しい決断ですが、今こそ日本企業の経営者も見習うべき姿勢だと思います。
そして、実はビル・ゲイツ氏よりも世界の気候危機界隈、就中産業界やESG界隈に対して多大な影響を及ぼしてきた大司教のような人物も変節したのですが、日本国内ではあまり知られていないようです。この方については次回ご紹介いたします。
■

関連記事
-
バイデン政権は、米国内の金融機関に化石燃料産業への投資を減らすよう圧力をかけてきた。そして多くの金融機関がこれに応じてポートフォリオを変えつつある。 これに対して、11月22日、15の州の財務長官らが叛旗を翻した。 すな
-
はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ
-
菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「
-
評価の分かれるエネルギー基本計画素案 5月16日の総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画の素案が了承された。2030年の電源構成は原発20-22%、再生可能エネルギー22-24%と従来の目標が維持された。安全性の確
-
トランプ政権は、バイデン政権時代の脱炭素を最優先する「グリーンニューディール」というエネルギー政策を全否定し、豊富で安価な化石燃料の供給によって経済成長と安全保障を達成するというエネルギードミナンス(優勢)を築く方向に大
-
ロシアへのエネルギー依存を脱却すべく、欧州が世界中からエネルギーを買い漁っている。この影響で世界のエネルギー価格は暴騰した。これに耐えかねて、開発途上国では石炭の増産と石炭火力発電の利用計画が次々と発表されている。 ニュ
-
日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。
-
表面的に沈静化に向かいつつある放射能パニック問題。しかし、がれき受け入れ拒否の理由になるなど、今でも社会に悪影響を与えています。この考えはなぜ生まれるのか。社会学者の加藤晃生氏から「なぜ科学は放射能パニックを説得できないのか — 被害者・加害者になった同胞を救うために社会学的調査が必要」を寄稿いただきました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間