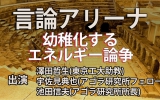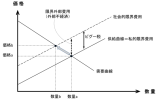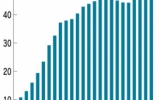-
アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは幼稚化するエネルギー論争」です。 経団連がエネルギー問題で国民的な議論を呼びかけましたが、論争には感情論が多く、むしろレベルは劣化していています。この背景
-
なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん
-
電力・電機メーカーの技術者や研究機関、学者などのOBで構成する日本原子力シニアネットワーク連絡会は3日、「原子力は信頼を回復できるか?」をテーマとしたシンポジウムを都内で開いた。ここでJR東海の葛西敬之会長が基調講演を行い、電力会社の経営状態への懸念を示した上で、「原発再稼動が必要」との考えを述べた。
-
注目されてきたのがカーボンプライシング(Carbon Pricing)である。カーボンプライシングとは炭素(CO2)の排出に価格付けを行うことで、企業などにCO2排出を「費用」と認識させ、費用削減のインセンティブを通じて、CO2排出抑制への取り組みを促すことを狙ったものである。
-
改めて原子力損害賠償制度の目的に立ち返り、被害者の救済を十分に図りつつ原子力事業にまつわるリスクや不確実性を軽減し、事業を継続していくために必要な制度改革の論点について3つのカテゴリーに整理して抽出する。
-
四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年
-
実は、この事前承認条項は、旧日米原子力協定(1988年まで存続)にもあったものだ。そして、この条項のため、36年前の1977年夏、日米では「原子力戦争」と言われるほどの激しい外交交渉が行われたのである。
-
けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー