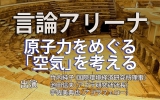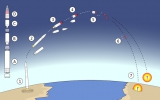原子力規制委員会の見識を疑う — 民意で安全を決めるのか?
事後的に審査要件を一般募集
原子力規制委員会により昨年7月に制定された「新規制基準」に対する適合性審査が、先行する4社6原発についてようやく大詰めを迎えている。残されている大きな問題は地震と津波への適合性審査であり、夏までに原子力規制庁での審査が終わる見通しが出てきた。報道によれば、九州電力川内原発(鹿児島県)が優先審査の対象となっている。
規制庁内審査が終わると、それぞれの原発ごとに審査結果をまとめた「審査書案」が作られ、それを原子力規制委員会が承認し、審査書となった後、設置変更許可が出されることになる。昨年の内に第1号の審査が終了すると見込まれていたので、現時点でかなり遅れている。
ところが、2月12日の定例の原子力規制委員会の定例の委員会会合において田中規制委員長から唐突に、「第1号の審査書案ができた時点でそれに対する科学的・技術的意見を一般から募集したらどうか」との提案がなされた。(同日の会議議事録)
また、併せて「自治体からの要望が有れば公聴会も考えたいので、2月19日の定例委員会に具体案を出すように」と規制庁事務当局に指示が出された。
そして19日の委員会において、審査書案ができた段階で4週間程度の公募期間の設定と、要望に応じて公聴会を開くことが大した議論もなく了承された。(同日の会議議事録)
審査の混乱が重なる懸念
適合性判断に広く国民の科学的・技術的意見を入れようというのである。妥当と思われる意見があれば、審査書案を書き直すという。土台無理である。
適合性に係る会合は既に83回を数えており、時には1回の会合で10時間を超えている。このような議論に参加してこない人に科学的・技術的判断ができるとは考えられない。また、公聴会に関しては、規制委員の原子力災害対策指針が対象とするのは30キロメートル圏以内の自治体であり、多くの自治体から要望が出ることが予想される。
さらに、公平を期すためには、第2号審査書案以下に対しても同じことを企画する必要があり、6原発全部で240日を要することになる。第1号の審査書案だけに留めるのであれば、それに対する正当な理由付けが必要になる。
新規制基準を作るに当たっては1カ月間の意見公募を行っており、一般国民の意見はその中に反映されている。規制委員会委員は国民の代表たる国会の承認を得て委員に就任しており、粛々と新規制基準への適合性審査を終了させる義務と責任を負っている。
ただでさえ審査が長引き、再稼働が遅れ年間4兆円に近い外貨が余分に流出している現状では、一刻も早い真摯な審査が求められる。無為なプロセスを導入することで再稼働を遅らせるべきでない。この点についても、経済がどうなろうと関知せずという発言を繰り返す委員長の見識を疑う。
なお、審査書案は最終的に規制委員会の審議を経なければならない。専門性において規制委員会では全てをカバーすることはできない。それを補完するために、法律で設置を義務付けられている原子炉安全専門審査会(炉安審)の検討結果を規制委員会が見て判断する必要がある。炉安審は未だにメンバーも決まっていない。早急に決めるべきである。
(2014年3月17日)

関連記事
-
IPCCの第6次報告書(AR6)は「1.5℃上昇の危機」を強調した2018年の特別報告書に比べると、おさえたトーンになっているが、ひとつ気になったのは右の図の「2300年までの海面上昇」の予測である。 これによると何もし
-
産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合
-
東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の広域処理が進んでいない。現在受け入れているのは東京都と山形県だけで、検討を表明した自治体は、福島第1原発事故に伴う放射性物質が一緒に持ち込まれると懸念する住民の強い反発が生じた。放射能の影響はありえないが、東日本大震災からの復興を遅らせかねない。混乱した現状を紹介する。
-
文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。
-
福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。
-
2025年6月20日、NHKニュースにて「環境省 気候変動に関するフェイク情報拡散防止で特設ページ」という報道がありました。記事によると、「地球温暖化は起きていない」「人間の活動による温室効果ガスの排出は関係ない」といっ
-
言論アリーナ「原子力をめぐる「空気」を考える」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 福島第一原発事故から7年たちましたが、原子力をめぐる国民感情は意外に変わりません。「原発がなくても電力は足りてるじゃないか」という
-
北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間