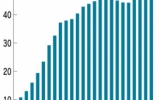放射能のリスクを生活の中のリスクと比較する
放射能の脅威が社会に残る
東日本大震災からはや1年が経過した。昨年の今頃は首都圏では計画停電が実施され、スーパーの陳列棚からはミネラルウォーターが姿を消していた。その頃のことを思い返すと、現在は、少なくとも首都圏においては随分と落ち着きを取り戻した感がある。とはいえ、まだまだ震災後遺症は続いているようだ。
その後遺症のひとつに放射性物質に関する人々の認識がある。放射性物質には発がんリスクがあるとの考えは間違ってはいない。しかし、震災から1年が過ぎて、今回の放射性物質の流出は、ごく一部を除けば恐れなくてもよいレベルであることがわかってきたにもかかわらず、必要以上に恐れている人がいるようだ。
その「恐れ」が、とにかく放射性物質を可能な限りすべて排除しなければ気が済まないとの考えにつながり、結果として、食品中の放射性物質(この場合、セシウムやストロンチウム)の基準値が大幅に引き下げられるなどの措置が講じられている。生協系の生活クラブはその基準値でも甘すぎると考えたのか、自主基準として国よりはるかに厳しい基準値(たとえば米や牛乳は10ベクレル/kg)を設けている。
しかし、今回の放射性物質の被ばくによる発がんリスクが、そのほかの生活習慣によるリスクと比較して、どの程度大きいのか(あるいは小さいのか)については、ご存知ない方も多いだろう。そこで本稿では、さまざまな生活習慣による疾病リスクを数値化して、これを放射性物質の被ばくリスクと比較することで、リスクとどのように付き合うべきかについて考えてみたい。
恐れるだけではなく、リスクを数値化して向き合う
表1(別ページ)は、さまざまな生活習慣による疾病リスクを「相対リスク比」として示したものである。相対リスク比とは、「疾病する確率」が生活の項にある行為によってどれだけ増減するかを示したものである。「相対リスク」という言葉からも理解いただけると思うが、この数値は、生活の項にある行為を行わない人のリスクを1として、行為を行う人のリスクの増減を比率で表している。
たとえば喫煙の項では、タバコの喫煙による肺がんの相対リスク比が3.7となっている。肺がんは、喫煙しなくても発症する可能性がある。ここで、非喫煙者が肺がんにかかる確率をaとすると、喫煙者が肺がんにかかる確率は3.7×aとなる。すなわち、相対リスク比3.7とは、喫煙者は非喫煙者に比べて肺がんにかかる確率が3.7倍となることを意味する。同表の最上段に100ミリシーベルト(mSv)被ばく時の発がん(全がん)の相対リスク比を示した。
なお、同表に示した数値は、疫学調査(すなわち人間を対象にした調査)の結果に基づいたものであり、いわゆる動物実験の結果から推計したものではない。当然のことながら同表に示した数値には統計的な誤差が含まれるほか、民族や地域、生活習慣によっても異なる結果となりうる。しかし、調査は適切に行われていると考えられ、信頼性は高いものと考えられる。
リスクに囲まれた私たちの生活
同表を眺めると、我々の普段の生活習慣が、いかにリスクに晒されているかがおわかりいただけるであろう。喫煙が肺がんの、飲酒が肝臓がんの原因となりうることは、広く知られているが、それ以外にもさまざまなリスクがあることがわかる。
さて、大小を比較してどう思われるだろうか。確かに放射性物質に被ばくすれば発がんのリスクが高まる。これは事実である。しかし、相対リスク比は100 mSvの被ばくで1.005である。すなわち、100 mSvの被ばくがなかったときの発がん率をaとすると、100 mSvの被ばくにより、1.005×aとなると推定される。
これに対して、それ以外の生活習慣のリスクはどのようなものだろうか。喫煙による肺がんの相対リスク比は3.7、ピロリ菌感染による胃がんの相対リスク比は2.6、ストレスによる脳卒中の相対リスク比は2.5である。
これの意味するところは、リスクを下げたいのであれば、現在の放射性物質を怖がるよりも、喫煙やピロリ菌、飲酒、ストレス、野菜不足などをこそ恐れるべきだということである。換言すれば、わずか数百ベクレル(Bq)の放射性物質を取り除こうとするよりは、酒やたばこを控えたり、毎日きちんと歯を磨いたり、ストレスをためないようにしたり、野菜を積極的に摂取する方が、リスクを減らすためにはよほど効果的だということである。
これらのことに触れずに、放射性物質のリスクだけをことさらに強調するのは、バランスを欠いた議論だと言わざるを得ない。
ところで、ここまでの拙文をお読みになればお分かりいただけると思うが、そもそも「絶対安全」というものはないのである。放射性物質を避ければ絶対安全かと言えば、そのようなことはなく、異なるリスクが厳然として存在する。そしてそのリスクの大きさは、避けたリスクよりも大きいかもしれない。被ばくを恐れて子供を外で遊ばせなかったら、ストレスがたまるかもしれない。ずっと家の中にいたら運動不足になるかもしれない。それらのリスクは、避けたリスクより大きいかもしれない。
つまり私たちが考えるべきは、ある特定のリスクだけをゼロにすることではなく、さまざまなリスクがある中で、トータルとしてリスクを減らすことである。その意味で、巷間を賑わせている「放射性物質だけを可能な限り減らす」という議論には注意が必要だ。トータルとしてみたときに、本当にリスクが減っているのかどうか、かなり怪しいからだ。
表1(別ページ)についてはさまざまな観点から議論ができる。GEPRでは今後もリスクについての情報を提供していきたい。

関連記事
-
1. メガソーラーの実態 政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)事業が展開されている。 しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が
-
本年9月の総選挙の結果、メルケル首相率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU)は全709議席のうち、246議席を獲得して第1党の座を確保し、中道左派の社会民主党(SPD)が153議席で第2党になったものの、これまで大連立を
-
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。
-
関西電力をめぐる事件の最大の謎は、問題の森山栄治元助役に関電の経営陣が頭が上がらなかったのはなぜかということだ。彼が高浜町役場を定年退職したのは1987年。それから30年たっても、金品を拒否できないというのは異常である。
-
けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー
-
バイデンの石油政策の矛盾ぶりが露呈し、米国ではエネルギー政策の論客が批判を強めている。 バイデンは、温暖化対策の名の下に、米国の石油・ガス生産者を妨害するためにあらゆることを行ってきた。党内の左派を満足させるためだ。 バ
-
なぜ浮体式原子力発電所がいま熱いのか いま浮体式原子力発電所への関心が急速に高まっている。ロシアではすでに初号基が商業運転を開始しているし、中国も急追している。 浮体式原子力発電所のメリットは、基本構造が小型原子炉を積ん
-
ポイント 石炭火力発電は、日本の発電の3分の1を担っている重要な技術です。 石炭火力発電は、最も安価な発電方法の1つです。 石炭は、輸入先は多様化しており、その供給は安定しています。 日本の火力発電技術は世界一優れたもの
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間