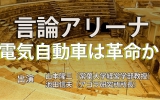サマータイムでエネルギー消費は増える
森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとになる。
森氏は「夏時間で2時間早めたら、午前7時スタートのマラソンが午前5時スタートとなり、日が高くなる前にレースを終えることができる」というが、5時スタートにすればいいだけの話だ。他の仕事も、勤務シフトを変えればいい。時計を変える必要はない。
日本には異なる標準時という習慣がないので、時計を変更したら大混乱になる。アナログ時計なら1時間進めればいいが、コンピュータのクロックはすべての電子機器の基準になっており、ソフトウェアや半導体の時刻の変更は大変だ。同期が狂うと交通機関などのシステムが混乱し、事故が起こる可能性もある。
それより問題は、夏時間がエネルギー節約になるかどうかだ。これは英語ではdaylight saving time、つまり明るいうちに仕事を終えて、夜の照明を節約する習慣だ。これを提唱したのはベンジャミン・フランクリンだといわれるが、いま夏に最大のエネルギーを消費するのは冷房である。
アメリカのインディアナ州では、一部の郡しか夏時間をとっていなかったが、2006年に全州で夏時間が導入された。新たに夏時間を採用した郡でエネルギー消費を調査した経済学者の実証研究によれば、電力消費は平均1%増え、ピーク時には4%も増えた。夏時間で朝早くから活動すると照明の利用は減るが、冷房の利用は増えるからだ。
日本でも1948年から行われた夏時間は、残業が増えて4年で廃止された。1996年に夏時間を採用したEUでも、スイスやフィンランドなどで、夏時間の廃止を求める国民投票の動きがある。ロシアでは2011年に廃止された。生活を混乱させ、エネルギーを浪費する時代錯誤の夏時間は、百害あって一利なしである。

関連記事
-
マンハッタン研究所のマーク・ミルズが「すべての人に電気自動車を? 不可能な夢」というタイトル(原題:Electric Vehicles for Everyone? The Impossible Dream)を発表した。い
-
ドイツでは各政党にシンボルカラーがあり、昨年11月までの政府は、社民党=赤、自民党=黄、緑の党=緑の三党連立だったので、「アンペル(信号)」と呼ばれた。しかし、今は黄色が抜けて、「レッド・グリーン(rot/grün)」政
-
GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。
-
東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。
-
最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末
-
米国の元下院議長であった保守党の大物ギングリッチ議員が身の毛がよだつ不吉な予言をしている。 ロシアがウクライナへの侵略を強めているのは「第二次世界大戦後の体制の終わり」を意味し、我々はさらに「暴力的な世界」に住むことにな
-
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2030年までに世界の平均気温が産業革命前より1.5℃(現在より0.5℃)上昇すると予測する特別報告書を発表した。こういうデータを見て「世界の環境は悪化する一方だ」という悲観的
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間