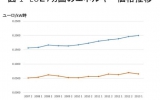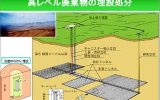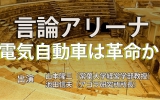論点「放射能のリスク」「原発ゼロは可能か」【アゴラ・シンポジウム資料】
アゴラ研究所は12月8日にシンポジウム「第2回アゴラ・シンポジウム –「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催する。(内容と申し込みはこちら)視聴はインターネット放送などで同時公開の予定だ。
この記事では、アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」で公開してきた議論を整理する。GEPRはビル・ゲイツ氏の支援で、アゴラ研究所(所長・池田信夫)が運営している。(「開設にあたって–私たちの使命」)
今回のシンポジウムでは、原発政策の実施をめぐり、その現状継続に懐疑的な見方をする田坂広志多摩大学教授、橘川武郎一橋大学教授が登場。また、いくつもの企業取締役を務める夏野剛慶応大学教授も参加する。原発をめぐる多様な立場からの意見を集めて、参加者とともに議論と認識を深める。「熟議」が、混迷するエネルギー問題を解決すると信じたい。(第2回アゴラシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」出演者の意見)
ぜひ、御視聴、ご参加をいただきたい。
昨年のシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」
アゴラ研究所は昨年12月、原子力とエネルギーをめぐるシンポジウムを行った。
原発はいつ動くのか–シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告・その1
原発ゼロは可能なのか ― シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告・その2
第1セッション「放射能のリスクを考え直す」関連
放射能をめぐる事実認識が多様であり、原子力利用、また福島からの復興に影響を与えている。シンポジウム前に、アゴラ・GEPRで展開された議論を整理する。
【福島原発事故の放射線の影響】
2011年の原発事故によって、放射性物質が飛散した。幸いなことに、事故による影響は限定的で、日本における健康被害は現時点で確認されていません。そして健康被害の可能性は少ないと、政府、国際機関が揃って報告書を出している。
「福島原発事故で差し迫った健康リスクはない」福島原発事故で国連機関が評価(2013年6月4日、GEPR記事)
低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ (2011年12月23日、内閣府)
これまでの科学的な知見では、低線量被ばくの影響は、生涯の追加の放射線被ばくが100mSv(ミリシーベルト)にとどまる限りにおいて、影響は他のリスクの影響に隠れてしまうほど小さいと研究されている。
「原発、危険神話の崩壊」(池田信夫、PHP新書)第2章、放射能はどこまで恐いのか
放射線の健康影響—重要な論文のリサーチ(2012年1月1日、GEPR記事)
【日本の放射線防護対策】
ところが日本政府は、震災直後において、賠償の基準を曖昧にし、また年1mSvまでの除染を行うなどの対応を行った。これにより、当然に資金を提供している政府の負担は増加。さらに、福島で多くの人が帰宅できないなどの問題が生じている。見直しが議論になっているが、国の動きは鈍い。
福島の除染「1ミリシーベルト目標」の見直しを(2013年6月10日、GEPR記事)
【世界の原子力利用】
今回のシンポジウムに出席するウェイド・アリソン・オックスフォード大学名誉教授は、放射能の恐怖が過度な規制を与え、社会を混乱させていると指摘している。
放射線の事実に向き合う–本当にそれほど危険なのか?(2012年1月1日、GEPR記事)
第2セッション「原発ゼロは可能か」関連
福島第一原発以降、政権与党だった民主党が政策として打ち出した「原発ゼロ」が問題になった。また原子力をめぐる国民の信頼が失墜している。
【需給面で】
需給面では、化石燃料、特に石炭シフトが必要で、不確実性が高まると、GEPRでは指摘している。
現実的な「原子力ゼロ」シナリオの検討 –石炭・LNGシフトへの困難な道のり(2012年7月23日、GEPR記事)」
【放射性廃棄物問題】
しかし、原子力での懸念で、放射性廃棄物の処理の問題が出ている。日本の場合に、再処理によって一部を燃料として使う一方で、残りを地中処分する政策が行われてきた。しかしこの「核燃料サイクル政策」は、高速増殖炉が実用化せず、青森県六ヶ所村の再処理施設が稼動していない現実がある。
原発は「トイレなきマンション」か ― 核廃棄物を考える【言論アリーナ】 (2013年9月2日、GEPR記事)
【解説】核燃料サイクル政策の現状 ― 全量再処理方策の再検討が始まる(2013年9月2日、GEPR記事)
(2013年12月2日掲載)

関連記事
-
雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「 雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「注目のキーワード‐エネルギー貧困率」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。
-
アゴラ研究所の運営するインターネット放送の言論アリーナ。2月24日は「トイレなきマンション」を終わらせよう--使用済み核燃料を考える」を放送した。出演は澤田哲生氏(東京工業大学助教)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)の2人。ジャーナリストの石井孝明が司会を務めた。
-
第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。
-
池田・2022年までに、電力では発送電分離が行われる予定です。何が行われるのでしょうか。 澤・いろいろな説明の仕方がありますが、本質は料金設定の見直しです。規制のかかっていた4割の家庭用向けを自由化して、総括原価と呼ばれる料金算定方法をなくします。
-
朝日新聞7月10日記事。鹿児島県知事に、元テレビ朝日記者の三反園訓氏が当選。三反園氏は、川内原発の稼働に懐疑的な立場で、再検査を訴えた。今後の動向が注目される。
-
言論アリーナ「電気自動車は革命か 」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 テスラの「モデル3」が爆発的に売れ、世界的に電気自動車が注目されています。それはガソリン車に取って代わるのでしょうか。 出演 山本隆三(常葉
-
JBpress 8月18日の池田 信夫氏の記事。ヨーロッパでは2035年までにガソリン車・ディーゼル車はなくなるとの予測もある。電気自動車はガソリン車を駆逐するほど魅力的なのだろうか?
-
最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間