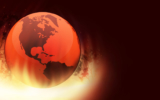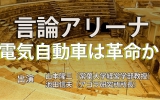温暖化の科学は決着などしていない:『気候変動の真実』
以前紹介したスティーブン・クーニン著の「Unsettled」の待望の邦訳が出た。筆者が解説を書いたので、その一部を抜粋して紹介しよう。
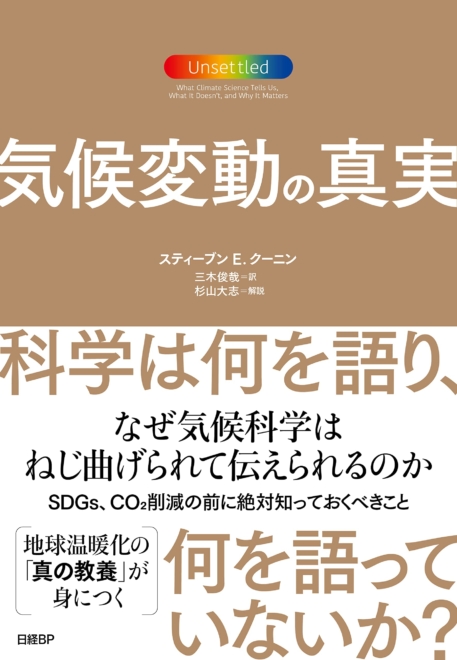
スティーブン・クーニンは輝かしい経歴の持ち主で、間違いなく米国を代表する科学者の1人である。世界最高峰のカリフォルニア工科大学で筆頭副学長までつとめた。伝説の研究者団体JASONの会長も務めた。コンピューターモデルによる物理計算の権威でもある。
温暖化対策に熱心な米国民主党のオバマ政権では、エネルギー省の科学次官に任命されていて、気候研究プログラムも担当した。
クーニンに対して、非専門家だとか、政治的な動機による温暖化懐疑派だとかする批判は出来ようが無い。
政治的な動機だけいえば、本書で書いてあるように、むしろクーニンは多くの政策において民主党を支持している。ならば、党派性からいえばむしろ気候危機説を煽るほうになる。
私利私欲だけを考えるなら、クーニンがこの本を著したのはまったく愚かなことだ。これだけの経歴があれば、かりに気候危機説に対して違和感を持ったとしても、適当に同調したり、口をつぐんでさえいれば、悠々と暮らすことが出来る。
そのクーニンが「気候危機説は捏造だ」と喝破したのがこの本だ。
原文のタイトル「Unsettled」とは、温暖化の科学は「決着していない」、という意味だ。
この本の見解は
- もともと気候は自然変動が大きい。
- ハリケーンなどの災害の激甚化・頻発化などは起きていない。
- 数値モデルによる温暖化の将来予測は不確かだ。
- 大規模なCO2削減は現実的ではなく、自然災害への適応が効果的だ
といったものだ。
じつはこれはこれまで「懐疑派」と呼ばれて迫害されてきた研究者たちが書いてきたことと、内容的にはほぼ重なる。
謝辞でも言及されているジョン・クリスティやウィリアム・ハパーらは、逆風をものともせず、堂々と気候危機説への懐疑を繰り広げてきた。

jaminwell/iStock
本書は、これらの人々の研究成果も織り交ぜつつ、国連や米国の報告書において気候変動に関する「ザ・科学」がいかに捻じ曲げられているか、綿密な検証をもとに論じている。(ちなみに日本の環境白書でも科学は大きく捻じ曲げられている注1)。)
可能な限り平易に書いてあるけれども、問題の複雑さから逃れようとはしない。したがって読むのはかなり大変だが、その価値はある。
災害に関する統計や報道は歪められて、気候危機があると説得するための材料にされている。
温暖化予測に用いる数値モデルは、雲に関するパラメーター等の設定に任意性があり、観測で決めることが出来ない。このパラメーターをいじって地球の気温上昇の大きさを操作する「チューニング(調整)」という慣行がある。クーニンはこれを解説した上で「捏造である」と喝破している。
クーニンの執筆動機ははっきりしている。科学が歪められ、政治利用されていることに我慢がならないのだ。温暖化の科学は決着しており唯一の「ザ・科学」が存在するという見解は間違っている。「気候危機だ」と煽り立てるのは政治が科学を用いる方法として間違っている。何よりも、国連や米国の報告書が、科学的知見を歪めて報告していることに憤っている。
クーニンは物理学者ファインマンに憧れてカルフォルニア工科大学に入学した。物理学出身者には、本書でも登場する同大学の故フリーマン・ダイソンを含め、温暖化の「ザ・科学」に批判的な研究者が多い。
私事ながら小生も物理学出身で、そこで批判精神をおおいに学んだ。そのおかげで気候危機説に疑問を持つようになり、クーニンと全く同じ動機を持ってあれこれ調べ初め、全く同じ見解に達した。本書でクーニンが言っていることに違和感は何一つ無かった。
なぜ温暖化の科学は歪められ、政治利用されるのか。クーニンは、メディア、研究者、研究機関、NGO、政治家などが、それぞれの動機で動いた結果、意図せざる共謀が起きていると指摘している。
センセーショナルな見出しでとにかく注意を引きたいメディア、メディア報道が成果にカウントされて予算獲得や出世につながる研究者、危機を煽って収益につなげたいNGO,危機対策のリーダーとして振舞うことで得票を狙う政治家などだ。この意図せざる共謀の構図は日本でも全く同じである。。。 とても良い本なので、ぜひ、読んでください!
注1)「気候危機」を唱道する環境白書 根拠なく危機あおることへの違和感 (杉山大志 エネルギーフォーラム 2020年9月号)
■

関連記事
-
各種機関から、電源コストを算定したレポートが発表されている。IRENAとJ.P.Morganの内容をまとめてみた。 1.IRENAのレポート 2022年7月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、「2021年
-
地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
-
コロナの御蔭で(?)超過死亡という言葉がよく知られるようになった。データを見るとき、ついでに地球温暖化の健康影響についても考えると面白い。温暖化というと、熱中症で死亡率が増えるという話ばかりが喧伝されているが、寒さが和ら
-
英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立が激化している。11月11日の英紙フィナンシャル・タイムズでは Ministers clash over energy bill という記事が出ていた。今月、議会に提出予定のエネルギー法案をめぐって財務省とエネルギー気候変動省の間で厳しい交渉が続いている。議論の焦点は原子力、再生可能エネルギー等の低炭素電源に対してどの程度のインセンティブを許容するかだ。
-
2024年6月に米国下院司法委員会がGFANZ、NZBAなど金融機関による脱炭素連合を「気候カルテル」「独禁法違反」と指摘して以来、わずか1年でほとんどの組織が瓦解しました。 今年に入って、7月にフロリダ州司法長官がSB
-
今回はマニア向け。 世界の葉面積指数(LAI)は過去30年あたりで8%ほど増えた。この主な要因はCO2濃度の上昇によって植物の生育が盛んになったためだ。この現象は「グローバルグリーニング」と呼ばれる。なお葉面積指数とは、
-
最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間