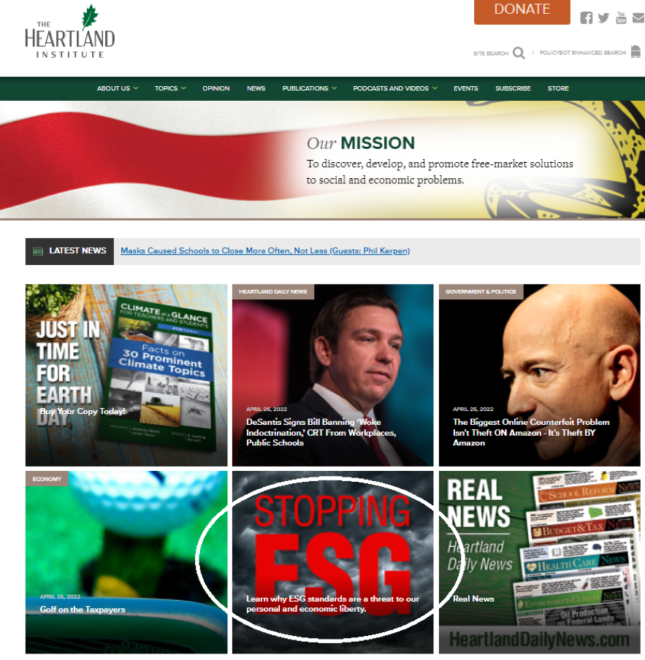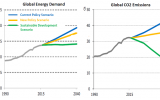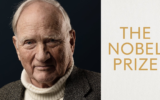ESGの不都合な真実:特集ページ『STOPPING ESG』の紹介

ronniechua/iStock
米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。
https://www.heartland.org/ESG/esg
STOPPING ESGのページに入ると冒頭に4つの論文があり、この4つの論文をまとめたレポートがPDFファイルで掲載されています。以下、企業でESG業務に関わっている筆者が興味深いと感じた記述を抜粋します。
現在、数多くのESGモデルが存在するが、エリートや左翼関係者が好む活動を推進するという共通の目的を持っている。例えば、国際ビジネス評議会(IBC)が開発した指標は、「年齢層、性別、その他の多様性指標(民族性など)の従業員比率」で企業をランク付けする。言い換えれば、アジア人とヒスパニック系労働者の比率が「間違っている」企業は、たとえその企業が消費者により良い製品やサービスを提供し、より高い利益を得ていたとしても、「正しい」比率の競合企業より低いESGスコアを与えられる可能性がある。
ESG課題への取り組みを強制された場合、企業価値が損なわれる可能性がある。例えば、多様性を満たすという理由だけで不適格な候補者が役員やマネージャーに選ばれると、長期的には最適でない企業パフォーマンスにつながる。さらに、ESGを強制的に導入させられた多くの企業は、実績のあるビジネス手法や収益性の高い製品・サービスを放棄することになる。
国際ビジネス協議会(IBC)が推進するシステムは45の指標があり、全く異なるタイプのデータを組み合わせている。IBCの方式では、”研究開発費 “や “社会的投資 “などの定量的な指標と、”目的主導型経営”などの定性的な指標を混ぜ合わせている。
これらの記述は、2021年6月にアゴラで筆者が指摘した内容に通じます。
“前回述べた通り、定量的に把握可能なCO2や化学物質の排出量、水の使用量ですら、業種や規模が異なる企業を比較するのは難しいはずです。
(中略)
S(社会)、G(企業統治)ではEよりもさらに定性的な項目が目立ちます。
(中略)
定量的な数字を示せる社会貢献活動の支出額や参加人数、ボランティア休暇・青年海外協力隊への参加人数、東日本大震災の復興支援などの項目についても、CO2排出量と同様に売上高や従業員数と言った規模を加味する必要があるため、企業間の比較は本来できないはずです。実際のところ、東洋経済の解説にも「評価は全社・全業種統一基準で行った(会社規模、上場・未上場も同様)。一般に、従業員の男女構成、環境対策状況などは業種的特性が強いが、これらは一切加味していない。」との記載があります。“
STOPPING ESGに戻ります。
客観的で統一されたESGモデルは存在しない。ESGスコアは主観的に決定されることが多く、大企業からの偏った自己申告に依存することが一般的。
ESGの制度は、個人の機会や、場合によっては権利も制限する。また、米国ではESGの枠組みは政府機関によって運営されていないため、個人や家族をこのような行為から守るための憲法上の保護がない。
例えば、ネット上の「誤報」をターゲットにしたESGモデルでは、ソーシャルメディア企業に対して、本来なら許されるはずの言動を禁止するように強制する。同様に、ガソリン車を購入しようとする消費者は、ほとんどのESGモデルの場合、最終的に電気自動車を買わされる。
ESGシステムは事実上いつでも調整可能であり、一般市民が発言することもないため、ESGが社会に与える影響に限りはなく、ESGモデルが比較的少数の企業、銀行、投資家に与えるパワーについて深刻な倫理的疑問を引き起こす。
これも以前、杉山大志氏が指摘されていました。
いまESGは、選挙を受けない人々が政治的優先順位を付けることで推進され、それによって不当に不利を被る企業があり、人々の生活水準を低下させている、ということだ。”
他にも、興味深い内容が盛りだくさんです。昨今のESGの風潮に疑問をお持ちの方には大変おすすめのサイトです。
■

関連記事
-
2011年3月11日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故により、原子炉内の核分裂生成物である放射性物質が大気中に飛散し、広域汚染がおこった。
-
ご存じの方も多いと思いますが、先月末にビル・ゲイツ氏が気候変動対策への主張を転換しました。 ビル・ゲイツ氏、気候変動戦略の転換求める COP30控え | ロイター 米マイクロソフト創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏は28
-
7月25日付けのGPERに池田信夫所長の「地球温暖化を止めることができるのか」という論考が掲載されたが、筆者も多くの点で同感である。 今年の夏は実に暑い。「この猛暑は地球温暖化が原因だ。温暖化対策は待ったなしだ」という論
-
はじめに この二十年間、ヨーロッパは世界のどの地域よりも熱心に「グリーンエネルギー」と「脱炭素」に取り組んできた。再生可能エネルギーを大規模に導入し、化石燃料からの離脱を政治目標として掲げ、「気候リーダー」を自任してきた
-
オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te
-
細川護煕元総理が脱原発を第一の政策に掲げ、先に「即時原発ゼロ」を主張した小泉純一郎元総理の応援を受け、東京都知事選に立候補を表明した。誠に奇異な感じを受けたのは筆者だけではないだろう。心ある国民の多くが、何かおかしいと感じている筈である。とはいえ、この選挙では二人の元総理が絡むために、国民が原子力を考える際に、影響は大きいと言わざるを得ない。
-
2022年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・F・クラウザー博士が、「気候危機」を否定したことで話題になっている。 騒ぎの発端となったのは韓国で行われた短い講演だが、あまりビュー数は多くない。改めて見てみると、とても良い
-
ウォール・ストリート・ジャーナルやフォーブズなど、米国保守系のメディアで、バイデンの脱炭素政策への批判が噴出している。 脱炭素を理由に国内の石油・ガス・石炭産業を痛めつけ、国際的なエネルギー価格を高騰させたことで、エネル
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間