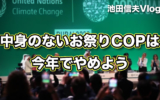ドイツは原発稼働延長を本当にできないのか?
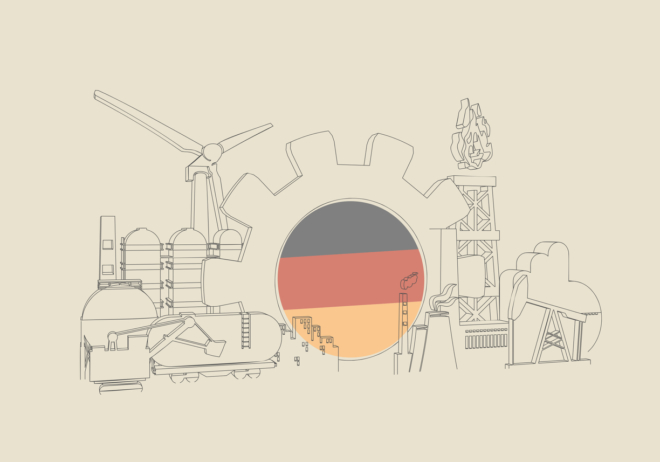
Evgeny Gromov/iStock
6月23日、ドイツのハーベック経済・気候保護相は言った。「ガスは不足物資である」。このままでは冬が越せない。ガスが切れると産業は瓦解し、全世帯の半分は冬の暖房にさえ事欠く。
つまり、目下のところの最重要事項は、秋までにガスの備蓄タンクを満たすこと。だから、ガスを発電のために使うわけにはいかない。よって発電には「予備の石炭・褐炭火力を立ち上げる!」
ただ、その途端にあちこちから、「ふざけるな、石炭・褐炭ではなく、今、動いている原発の稼働を延長しろ」という声が噴出した。当然の話だ。
ちなみに褐炭はドイツ国内に捨てるほどあり、しかも地表にあるから、わざわざ坑道を掘る必要さえない格安の資源だ。ただ、低品質なのでたくさんCO2を出す。これまで緑の党がCO2を毒ガス並みに扱ってきたことを思えば、これを燃やすのは絶対におかしいと中学生でも思う。
ドイツは、今世紀初めのSPDのシュレーダー政権(緑の党との連立)の時代より、脱原発に向かって粛々と進んできた。現在、奇しくもその2党が政権におり、今年の暮れに脱原発を完遂するという目標を、ブラックアウトが視野に入ってきている今でさえ捨てない。それどころか、自分たちの政権下でその昔年の夢が叶えられることが至上の幸せなのである。
そのためには石炭と褐炭が復活しても止むを得ない。「CO2は若干増える(ハーベック氏)」が、それも止むを得ない。原発は止めるしかないと断定している。
一方、ドイツに対して、原発を止めるなと言っている国は多い。例えばポーランドの電力関係者は数年も前から、脱原発は考え直すよう提言していた。ドイツのような大国で電気の供給が不安定になったら、周辺国はたまったものではないからだ。
また6月25日には、EU欧州委員会の圏内市場担当の委員(フランス人)が、現在動いている3基を、あと1〜2年、稼働延長すべきだと、自国のラジオの中で提案した。EUが、いや、世界中がエネルギー不足で困っているのだから、原発を動かせる国はそれを活用し、エネルギー事情の緩和に協力すべきだという主張は筋が通っている。
ところが、ドイツ最大の電力会社RWEの代表、マルクス・クレッバー氏は、「今頃、そんな話を始めてももう遅い」とつれない。「核燃料棒もないし、そんなに急に安全確認もできない」というのがその理由。年末に止めるつもりだから、10年ごとの定期点検もしていないし、予備の部品も切れかけている。燃料棒は今から注文しても来るのは1年以上先だ・・云々。
それを聞いた野党CDU(キリスト教民主同盟)のメルツ党首は、「フランスは53〜56基もの原発を運転しているのに、何故ドイツはたった3基の運転ができないのだ!」とぶち切れた。CSU(キリスト教社会同盟)のゼーダー党首も、「今、使用中の核燃料が、年末で突然、使えなくなるわけではない。世界中探して、早く次の燃料棒を注文しろ!」
はたして原発の稼働延長はできるのか、できないのか?
実は今年の3月、経済・気候保護省と環境省が、原発の稼働延長が可能かということを独自に調査し、不可能であるという結論を出している。いうまでもなく両省とも緑の党の省だ。
ところが現在、それを否定する論文や記事が多く出始めた。それによれば、この調査には原子力の専門家が入っていなかったらしい。
私には、それを確かめる術がないが、ただ2011年に、22年の脱原発が可能であるという結論を出した「倫理委員会」には、原子力の専門家も電力会社の関係者もほとんどおらず、その代わりに社会学者や聖職者が脱原発を決めた。また2019年に、2038年の脱石炭を決めた委員会でも、石炭産業の関係者は締め出され、環境団体が複数入っていた。だから、今、それと似たようなことが起こっていたとしても私は驚かない。そもそもハーベック大臣が、この調査は「イデオロギーに左右されずに」行うと、ZDF(第2テレビ)の朝のニュース番組でわざわざ言及していたことからして怪しかった。なお、ZDFも緑の党とは相性が良い。
一方、稼働延長が可能であるという記事は皆、少なくとも専門家の見解を元に書かれている。彼らは、新しい燃料棒の調達までは出力は弱まるが、今冬の電力のかなりの助けになるとした。また、点検は稼働しながらすれば良く、世界には440基もの原発が動いているのだから、部品の調達も不可能ではない。それより、早く燃料棒を注文しないと、本当に間に合わなくなってしまうと懸念している。ひょっとすると、ハーベック氏らは今、「間に合わなくなる」のを待っているのかもしれない。
なお、ドイツの脱原発は国民と国土の安全のためと言われるが、周辺には原発がたくさんあるので、ドイツの脱原発で安全になるわけではない。しかも東欧では、まだソ連時代の原発も動いており、かえってドイツの原発の方が安全かもしれない。
一方、電力会社が稼働延長に乗り気でないのも様々な理由がある。
政府に無理やり脱原発を強いられて11年、それを違法だと訴えていた裁判では、政府が敗訴を恐れて示談に持ち込み、電力会社に莫大な賠償金(税金!)を支払った。つまり、電力会社にしてみれば、すでに片は付いている。
また、以前は使用済み核燃料の輸送のたびに、自称環境団体の暴力的な抗議活動に悩まされ、しかも、メディアはいつも環境団体の味方だった。ドイツ人の原発アレルギーは今も強いから、もし稼働延長になり、あの悪夢が蘇ると思えば、気が進まないのはよくわかる。それより何より、今では電力会社でも再エネ派が力を持ち、原発の稼働延長など俎上に載らないのかもしれない。
日本が原発を稼働できないのは、政府の無能と無責任のせいだ。しかし、ドイツの脱原発は緑色のイデオロギー。そして政府が、CO2が増えようが、冬のブラックアウトの危険が迫ろうが、そのイデオロギーを実践しようとしている。なんと恐ろしい政府かと思う。

関連記事
-
「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーショ
-
2020年はパリ協定実施元年であるが、世界はさながら「2050年カーボンニュートラル祭り」である。 パリ協定では産業革命以後の温度上昇を1.5度~2度以内に抑え、そのために今世紀後半に世界全体のカーボンニュートラルを目指
-
1月20日、ドナルド・トランプ大統領の第2次政権の発足直後、ドイツの公共第2放送の総合ニュースでは、司会の女性がものすごく深刻な顔でニコリともせずにそれを報じた。刻々と近づいていた巨大ハリケーンがついに米国本土に上陸して
-
英国はCOP26においてパリ協定の温度目標(産業革命以降の温度上昇を2℃を十分下回るレベル、できれば1.5℃を目指す)を実質的に1.5℃安定化目標に強化し、2050年全球カーボンニュートラルをデファクト・スタンダード化し
-
北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する
-
ドバイで行われていたCOP28が先週終わったが、今回のCOPはほとんど話題にならなかった。合意文書にも特筆すべきものがなく、何も決まらなかったからだ。 今年は「化石燃料の段階的廃止(phase out)」という文言を合意
-
今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された。著者は渡辺正博士。全体は「気候変動」編と「脱炭素」編に分かれ、それぞれ7つの「ウソ」について解説されている。前稿の「気候変動」編に続き、今回は
-
国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間