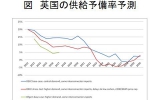米国気候作業部会報告へのコメントの大半は科学的根拠無し

tolgart/iStock
気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表された。
タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate)」である。
その位置づけや内容についてはすでに連載したので参照されたい。
米国の気候作業部会報告を読む⑬:一方的な削減は気候変動対策では無い
さて、パブリックコメントが9月2日に締め切られたが、その内容に関して、著者の一人であるクーニンがウォール・ストリート・ジャーナルにオピニオンを掲載して人気記事になっている。
At Long Last, Clarity on Climate
The Energy Department’s recent report is drawing predictable criticism from politicized scientists.
クーニンはオバマ政権でも要職を務めたことがあるぐらいで、元々は民主党的な信条の持ち主だが、気候変動に関しては全く民主党の気候危機説に同調していない。著書には「気候変動の真実」がある。
ではクーニンの記事の一部を抜粋しよう。タイトルは「ついに明らかになった気候問題の真実:エネルギー省の最新報告書は、政治化された科学者たちから予想通りの批判を浴びている」である。
エネルギー省の最近の報告書は、温室効果ガス排出が国家に深刻な脅威をもたらすという広く信じられている見解に異議を唱えた。・・気候変動に対する一般の認識と気候科学の間、そして過去の政府報告書と科学そのものの間には乖離がある。クリス・ライトエネルギー長官はこの点を理解している。だからこそ、気候変動に関する既知と未知の領域についてより明確な知見を提供するため、私を含む5人の上級科学者チームによる独立評価を委託したのだ。
・・本報告書は、気候が破滅に向かっているというナラティブに従わない、ワシントン発の数年ぶりの報告書である。こうした知見が多くの人々を驚かせた事実は、政府が気候科学を正確に国民に伝えることに失敗してきたことを示している。・・確立された科学に基づくにもかかわらず、本報告書は強い批判を集めた。公表後1か月で連邦官報に約6万件のコメントが寄せられ、「環境防衛基金および懸念を持つ科学者連合」なる団体はエネルギー省や環境保護庁が報告書を政策決定に利用するのを阻止するため訴訟を起こした。だがこうした異議申し立ての大半は科学的根拠を欠いている(傍線は筆者)。
気候変動に関するいわゆる「コンセンサス」を支持する科学者たちが複数の本格的な批判を展開したが、それらはせいぜい我々の調査結果に詳細やニュアンスを加える程度で、報告書の中核的主張を否定するものではない。
それでもこれらは応答に値するものであり、温室効果ガス排出の影響に関する遅ればせながらの公的議論の次なる段階を形成するだろう。・・気候政策は、気候変動のリスクと、対応策のコスト・有効性・付随的影響とのバランスを取らねばならない。我々の報告書は多くの怒りを招くかもしれないが、気候科学の重要な側面を正確に描写している。事実を認めることは、情報に基づいた政策決定に不可欠である。
「気候危機説」に異議を唱えると、殆どの場合、科学的根拠の無い批判がわんさか寄せられる。私もそれには慣れっこだが、クーニンも「予想通りだね」といった反応だ。
日本でも気候危機説ナラティブを垂れ流してきたメディアはやたらとこの気候作業部会報告をこき下ろそうとするが、科学的根拠を欠いているものばかりだ。コメントへの対応は特段の問題なく進みそうだ。
■

関連記事
-
前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当
-
CO2濃度が過去最高の420ppmに達し産業革命前(1850年ごろ)の280ppmの1.5倍に達した、というニュースが流れた: 世界のCO2濃度、産業革命前の1.5倍で過去最高に…世界気象機関「我々はいまだに間違った方向
-
国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ
-
中国のCO2排出量は1国で先進国(米国、カナダ、日本、EU)の合計を追い越した。 分かり易い図があったので共有したい。 図1は、James Eagle氏作成の動画「China’s CO2 emissions
-
2025年7月15日の日本経済新聞によると、経済産業省は温泉地以外でも発電できる次世代型の地熱発電を巡り、経済波及効果が最大46兆円になるとの試算を発表した。 次世代地熱発電、経済効果は最大46兆円 経産省が実用化に向け
-
ドナルド・トランプ氏が主流メディアの事前予想を大きく覆し、激戦区の7州を制覇、312対226で圧勝した。この勝利によって、トランプ氏は、「グリーン・ニュー・スカム(詐欺)」と名付けたバイデン大統領の気候政策を見直し、税制
-
自由化された電力市場では、夏場あるいは冬場の稼働率が高い時にしか利用されない発電設備を建設する投資家はいなくなり、結果老朽化が進み設備が廃棄されるにつれ、やがて設備が不足する事態になる。
-
私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間