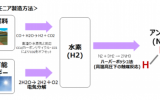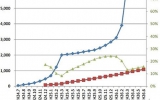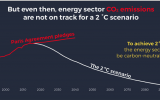今週のアップデート - 再エネ振興策の行き詰まりを考える(2014年10月14日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」・映像
アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開しました。東南海地震とエネルギーのリスクを専門家が集い、語り合いました。内容の報告を近日中に公開します。
電力会社の再エネ接続の保留、経産省の見直し策を、分かりやすくまとめました。
今週のリンク
1)九州電力はなぜ再エネ接続を留保するのか- 衝撃と背景を考察、打つべき一手を提案する
日経ビジネス10月6日号。再エネ研究者の山家公雄さんの論考です。制度の存続を前提に、揚水発電の利用などによる問題の解決を提案しています。
2)太陽光発電の参入凍結 大規模施設
増設も認めず 買い取り価格、大幅下げへ 経産省検討
日本経済新聞10月11日記事。経産省の再エネ振興策の転換を伝えています。
AFP(フランス国営通信)10月11日記事。フランスが10日、現在の発電に占める原発の依存を現在の75%から10年以内に50%にする法案を可決しました。再生エネルギーの拡充と省エネを柱としますが、野党からは実現を疑問視する声が広がっています。
河北新報10月11日掲載。福島県民の4割超が、脱原発に伴う電気料引き上げを容認する考えであることが河北新報社のアンケートで分かりました。福島第1原発事故を契機とした厳しい市民感情を裏付けています。26日に福島県知事選が行われますが、現時点で全候補が脱原発を訴えています。
5)再エネ、支援政策の光と影(上)–太陽光、投資10倍の急拡大
GEPR記事3月24日。再掲載。今回の再エネ政策の見直しの背景になった功罪について検証しています。全3回。

関連記事
-
日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見され
-
EUのEV化戦略に変化 欧州連合(EU)は、エンジン車の新車販売を2035年以降禁止する方針を見直し、合成燃料(e-fuel)を利用するエンジン車に限って、その販売を容認することを表明した。EUは、EVの基本路線は堅持す
-
「ドイツの電力事情3」において、再エネに対する助成が大きな国民負担となり、再生可能エネルギー法の見直しに向かっていることをお伝えした。その後ドイツ産業界および国民の我慢が限界に達していることを伺わせる事例がいくつか出てきたので紹介したい。
-
全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。
-
私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。
-
世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太
-
今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており
-
国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間