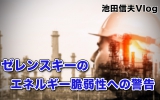今週のアップデート — 自然エネルギーとスマートグリッド、新たな動きに注目しよう(2012年6月11日)
今週のコラム
1) GEPRはエネルギー問題をめぐるさまざまな立場の意見を紹介しています。環境問題のオピニオンリーダーで、UNEP・FI(国連環境計画金融イニシアティブ)特別顧問である末吉竹二郎さんにインタビューを行いました。
「脱原発は国民の総意、道筋を考えよう=自然エネルギーによる社会変革への期待(上)」
「太陽光発電と買取制度の秘められた力=自然エネルギーによる社会変革への期待(下)」
末吉さんは原発事故を受けて脱原発で国民の意見はまとまっていると指摘。しかし、それを現実的にかつ長期的な視点で行う発想が政府に乏しいと指摘します。そして脱原発を進める手段が自然エネルギーで、その可能性を育てることを訴えます。
GEPRは中立的な立場に立ち、エネルギーについて読者の皆様の参考になる情報を提供しています。これまでのコンテンツでは急速な脱原発や、また自然エネルギーの過度の支援についての批判がありました。末吉さんの意見を読み比べ、読者の皆様の思索をまとめていただきたいと考えます。
2) GEPRを運営するアゴラ研究所は、ドワンゴ社の提供する「ニコニコ生放送」で、「ニコ生アゴラ」という番組を提供しています。月250万ページビューで日本最大級の閲覧数を持つ言論プラットホーム「アゴラ」の寄稿者によるリアルの対論番組です。6月5日の番組を記事化しました。
「ニコ生アゴラ「2012年の夏、果たして電力は足りるのか!?」報告−解決のカギはスマートグリッド」
元グーグル日本法人社長の村上憲郎氏、国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏、環境コンサルタントの竹内純子さんが出演し、アゴラ研究所の池田信夫所長が司会を務めました。
この夏の電力需給の状況を話し合い、その上で、電力不足の状況を乗り越える方法を話し合いました。池田氏は「IOTコンソーシャム」というNPOを立ち上げる予定を公表しました。IOTとは「Internet of Things :モノのインターネット」のことで、インターネットが家電製品などさまざまな現実の出来事と結びつき、より定着していく潮流の総称です。
IOTコンソーシャムではエネルギーシステムの改革、そしてスマートグリッドとIOTを結びつける活動を行います。GEPRはその事務局となります。(池田氏の解説記事『ソフトバンクのスマートメーター構想』)
3)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有しています。民間有志からつくる電力改革研究会のコラム「日本の停電時間が短いのはなぜか」を提供します。日本の停電時間の短さは、詳細なシステム作りの工夫があるためです。
今週のニュース
1)6月8日に野田佳彦首相が記者会見で停止中の関西電力の大飯原発3号機、4号機の再稼動が必要であり、日本では現時点で国民生活を守りながら、安全性を確保しつつ原発を使い続けなければならないことを明言しました。(野田総理記者会見の映像と音声の原稿化、首相官邸ホームページ記事)
今週のリンク
1)「エネルギー・環境政策の国民的議論のために」。電力中央研究所(2012年5月公表)。1・震災時のエネルギー利用および節電の実態調査 2・エネルギー・環境政策の実効性の評価 3・地球規模での温暖化のあり方を探る−以上の3論文の書かれたパンフレットです。いずれも詳細な調査に基づいた意義深い論文です。特に節電実態調査では、15%の節電義務が加わった昨年の夏の節電で、大規模工場は平均で1200万円のコスト増になったという厳しい現実が紹介されています。
2) 「原子力損害賠償法の特色と課題−賠償スキームを含めた「安全・安心」を確立する」(2012年6月公表)。今回の記事に登場したNPO国際環境研究所の澤昭裕氏、また竹内純子さんが日本原子力学会誌12年6月号(40ページ以降)に寄稿しています。日本の原子力損害賠償法は、政府の関与の程度があいまいです。また福島原発事故の後で、政府の負担を減らすために、東電に負担を負わせる形になっています。それが逆に東京電力の資金調達を困難にして、政府が関与せざるを得ない状況をつくる可能性があることを指摘。今後の事故の可能性がゼロでない以上、国の関与の程度を明確化することが必要と提言しています。
3) 原子力学会誌12年6月号特集「福島第一原発事故の対応と今後の計画」東京電力の社員らが、現時点の原発の状況と今後の対応について解説しています。

関連記事
-
ゼレンスキー大統領の議会演説は、英米では予想された範囲だったが、ドイツ議会の演説には驚いた。 彼はドイツがパイプライン「ノルドストリーム」を通じてロシアのプーチン大統領に戦争の資金を提供していると、かねてから警告していた
-
突然の家宅捜索と“異例の標的” 2025年10月23日の朝、N・ボルツ教授の自宅に、突然、家宅捜索の命を受けた4人の警官が訪れた。 ボルツ氏(72歳)は哲学者であり、メディア理論研究者としてつとに有名。2018年までベル
-
長崎県の宇久島で計画されている日本最大のメガソーラーが、5月にも着工する。出力は48万kWで、総工費は2000億円。パネル数は152万枚で280ヘクタール。東京ディズニーランドの5倍以上の巨大な建築物が、県の建築確認なし
-
情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ
-
なぜか今ごろ「東電がメルトダウンを隠蔽した」とか「民主党政権が隠蔽させた」とかいう話が出ているが、この手の話は根本的な誤解にもとづいている。
-
以前、大雨の増加は観測されているが、人為的なものかどうかについては、IPCCは「確信度は低い」としていることを書いた。 なぜかというと、たかだか数十年ぐらいの観測データを見て増加傾向にあるからといって、それを人為的温暖化
-
広島高裁は、四国電力の伊方原発3号機の再稼動差し止めを命じる仮処分決定を出した。これは2015年11月8日「池田信夫blog」の記事の再掲。 いま再稼動が話題になっている伊方原発は、私がNHKに入った初任地の愛媛県にあり
-
「地球温暖化で海面が上昇すると、日本の砂浜が大きく失われる」という話は、昔はよく報道されてけれど、最近はさすがに少なくなってきた。後述するように、単なる誤情報だからだ。 それでもまだ、以下のような記事の見出しがあった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ
- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか
- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)
- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由
- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア
- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す
- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか
- 米国エネルギー長官が英国・ドイツの脱炭素政策を猛批判
- 経営危機でも排出権を4兆円も買わされるドイツ産業は明日の日本の姿
- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング