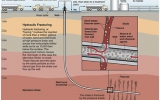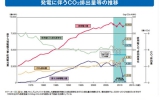非在来型ウランの埋蔵量について
きのうのG1サミットの内容が関係者にいろいろな反響を呼んでいるので、少し補足説明をしておく。
放送でもいったことだが、核燃料サイクルの問題は技術ではない。高速増殖炉の技術に大きな問題があるわけではない。もんじゅの事故は単なる配管の破断であり、原子炉そのものに欠陥があるわけではない。致命的な問題は、採算性である。
河野太郎氏も指摘したように、もんじゅや六ヶ所村のプラントには想定をはるかに超えるコストがかかって実用化が40年後に遅れているばかりでなく、そもそも再処理の目的である高速増殖炉(FBR)が経済的に意味をなさないのだ。
FBRはプルトニウムを燃料にしてそれより多くのプルトニウムを生み出す「夢の原子炉」といわれているが、1970年代に核燃料サイクルの計画が始まったときは、ウランの埋蔵量が数十年しかなく、世界で原子力開発が進んだら枯渇してしまうという危機感があった。このため、国内でエネルギーを生産できる「準国産エネルギー」としてFBRが期待されたのだ。
しかし最近の「非在来型エネルギー」の開発によって、この根本前提がゆらいできた。OECDの報告書はこう書いている:
1980年代以来、ウラン探鉱は限定的にしか行われてこなかったが、2002年以降はウラン価格の上昇を受け、探鉱活動は以前の3倍以上に増加した。近年の探鉱活動が活発でなかったにも関わらず、現在の消費量に対する既知のウラン資源の割合(=可採年数)は、他の鉱物エネルギー資源とほぼ同等で、約100年である。さらに現在の地質学的情報に基づいて発見が見込まれる資源を加えると、可採年数は300年分近くになる。また、「非在来型」資源、具体的にはリン鉱石中に含まれるウランも加えると、この数字は約700年にまで延びる。
通常のウラン(価格130ドル/kg以下)の埋蔵量は、世界全体で630万トン程度と推定され、これは世界のウラン消費量(約6.3万トン)の100年分ぐらいだが、それ以上のコストで採掘可能な非在来型ウランの埋蔵量は、IAEAによれば3500万トンある。これは世界の消費量の550年分である。OECDは2200万トンという数字を「きわめて保守的な推定」として紹介しているが、これでも350年分である。
さらに海水中にはほぼ無尽蔵のウランが含まれているが、その精製コストも下がり、日本の原子力委員会の報告によれば25000円/kgまで下げられる。これは通常のウランの価格基準(130ドル)の2倍程度で、今後の技術進歩で在来型のウランと競争できる可能性もあり、そのコストは核燃料サイクルよりはるかに低い。
そういうわけで、たとえFBRが完璧で安全な技術だとしても必要ないのだ。使用ずみ核燃料を直接処分したほうが安いからである。そしてFBRが必要なくなると、核燃料サイクルは宙に浮いてしまう。プルサーマルは核燃料サイクルを延命するための技術で、再処理から撤退すれば必要ない。こういう事実認識は、河野太郎氏から電力会社に至るまでほぼ同じだ。必要なのは政治的な決断だけである。
(2013年2月12日掲載)

関連記事
-
過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714
-
世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?
-
新たなエネルギー政策案が示す未来 昨年末も押し迫って政府の第7次エネルギー基本計画案、地球温暖化対策計画案、そしてGX2040ビジョンという今後の我が国の環境・エネルギー・産業・経済成長政策の3点セットがそれぞれの審議会
-
北朝鮮の野望 北朝鮮はいよいよ核武装の完成に向けて最終段階に達しようとしている。 最終段階とは何か—— それは、原子力潜水艦の開発である。 北朝鮮は2006年の核実験からすでに足掛け20年になろうとしている。この間に、核
-
日本経済新聞12月5日記事。東電の支援の方向が少しずつ固まっている。他者の支援、国の負担の増加、電力料金への上乗せが検討されている。
-
2020年10月の菅義偉首相(当時)の所信表明演説による「2050年カーボンニュートラル」宣言、ならびに2021年4月の気候サミットにおける「2030年に2013年比46%削減」目標の表明以降、「2030年半減→2050
-
2030年の電源構成(エネルギーミックス)について現時点で予断はできない。だが、どのようなミックスになるにせよ、ヒートポンプ・EVを初めとした電気利用技術は温暖化対策の一つとして有力である。さらに、2030年以降といった、より長い時間軸で考えると、電力の低炭素化は後戻りしないであろうから、電力化率(=最終エネルギーに占める電力の割合)の上昇はますます重要な手段となる。
-
列車事故から殺人事件へ 8月11日16時ごろ、北ドイツのニーダーザクセン州で、ウクライナからの避難民で、16歳の少女、リアナが、時速100キロで走ってきた貨物列車に轢かれて死亡した。当初、警察は、「悲劇的な重大事故」とし
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間