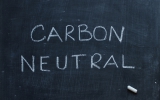戦略なきエネルギー基本計画
(アゴラ版)
政府のエネルギー基本計画がやっとまとまった。もとは2012年末に出す予定だったが、民主党政権が「原発ゼロ」にこだわったため、経産省が審議を遅らせ、昨年11月にやっと素案が出た。今回の政府原案は、それに対するパブリックコメントをへて修正されたものだが、内容はほとんど変わっていない。
メディアに注目されているのはもっぱら原子力の部分だが、「安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」という表現は意味不明だ。原発がベースロードになるのは出力を調整できないからで、それが基礎的だとか重要だとかいうことを意味するものではない。
エネルギー調査会では原発の比率をどうするかが争点だったようだが、現実の問題として日本でこれから原発を新規立地することは不可能である。福島事故で国と電力会社の信頼関係が崩壊し、地元の了解も得られないので、新たに原発を立地する電力会社はない。問題は、既存の原発をどうするのかだ。
いま全国の原発が原子力規制委員会の違法な行政指導で止まっていることは、「規制委員会が再稼動を認可する規定はない」という閣議決定で明らかだ。この状況について何もいわないのは「世論」を恐れているのだろうが、不作為の罪である。中長期の原発比率より、再稼動に向けての体制づくりが緊急に必要だ。
もう一つの問題は、現在のサイトで古い原子炉の寿命が来たとき、更新を認めるのかどうかだ。認めないとすれば原発はおのずからゼロに近づいてゆくが、それでいいのか。リスクや賠償コストも内部化し、確率で割り引いて評価すると、既存の原発の運転コストは群を抜いて低い(1〜2円/kWh)ので、再稼動は当然だ。
既存の原発を更新するかどうかは電力会社の判断だが、私は軽水炉の更新はやめたほうがいいと思う。GEPRにも書いたように、不確実なテールリスクが大きいからだ。軽水炉はもともとつなぎの技術で、冷却水が抜けた場合に炉心溶融を防げないという致命的な弱点をもっており、いくら多重防護しても「想定外」のリスクは残る。その安全対策を完璧にやろうとすると、莫大なコストをかけるか小型化するしかなく、経済性が見合わない。
それより軽水炉以外の第4世代原子炉の研究開発を国が補助すべきだ。「パンドラの約束」で印象的なシーンは、1986年にアルゴンヌ国立研究所で行なわれた実験だ。これは実際にEBR(実験的増殖炉)のスイッチを切って電源を喪失させ、緊急停止系も動作しない状態を作り出したもので、炉内の温度は直後に上がったがやがて下がり、核反応は自動的に停止した。
福島事故で原発すべてが恐いという印象が植えつけられてしまったが、軽水炉は特殊な原子炉である。これをIFRやビル・ゲイツの進行波炉のような第4世代技術に置き換えれば、安全性は高まる。物理的に炉心溶融が起こりえないからだ。第4世代には技術やコストの問題は残るが、安全性という点では軽水炉にはるかにまさる。
基本計画はバックエンドについても現状維持で、直接処分については「代替処分オプションに関する調査・研究を推進する」となっているだけだ。しかし昨年12月のシンポジウムでも専門家の意見が一致したように、「全量再処理」にこだわる合理的理由はない。これはサンクコストの錯覚である。
経産省が「福島事故を教訓として日本は軽水炉から徐々に撤退し、安全な原子炉の開発に政策資源を投入する。核燃料サイクルは見直し、全量再処理はやめる」という方針を打ち出せば、世界から注目されただろう。今回の基本計画にはそういう戦略がなく、短期の再稼動問題からも逃げている。これは政策ではなく、報告書にすぎない。
(2014年3月3日掲載)

関連記事
-
デンマークの統計学者、ビョルン・ロンボルグ氏の著書『地球と一緒に頭を冷やせ』を軸に、温暖化問題を考察しました。GEPR編集部が提供します。
-
11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。 世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あ
-
福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。
-
【気候変動 climate change】とは、人為的活動等に起因する【地球温暖化 global warming】などの気候の変化であり、関連して発生するハザードの問題解決にあたっては、過去の定量的評価に基づく将来の合理
-
20世紀後半から、人間は莫大量の淡水を農工業で利用するようになった。そのうち少なからぬ量は海に還ることなく蒸発して大気中に放出される。それが降水となることで、観測されてきた北半球の陸地における2%程度の雨量増加を説明でき
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:
-
おかしなことが、日本で進行している。福島原発事故では、放射能が原因で健康被害はこれまで確認されていないし、これからもないだろう。それなのに過剰な放射線防護対策が続いているのだ。
-
北朝鮮の野望 北朝鮮はいよいよ核武装の完成に向けて最終段階に達しようとしている。 最終段階とは何か—— それは、原子力潜水艦の開発である。 北朝鮮は2006年の核実験からすでに足掛け20年になろうとしている。この間に、核
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間