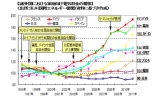原電敦賀2号機の破砕帯問題、科学技術的な審議を尽くし検証せよ
民主党政権の仕掛けか? 規制委の性急な審議
菅直人元首相は2013年4月30日付の北海道新聞の取材に原発再稼働について問われ、次のように語っている。「たとえ政権が代わっても、トントントンと元に戻るかといえば、戻りません。10基も20基も再稼働するなんてあり得ない。そう簡単に戻らない仕組みを民主党は残した。その象徴が原子力安全・保安院をつぶして原子力規制委員会をつくったことです」と、自信満々に回答している。
実際にすべての原発が現在(2014年9月1日時点)で停止しており、審査が進んでいるとされた九州電力川内原発でさえ、いつ稼動できるか不明のままだ。菅氏の言う通りになっている。
また、この記事で菅氏は①「活断層と認定する」か、②「40年問題」(建設後40年経過の原子炉の安全性検証を著しく困難にした)で多くの原発を廃炉にしていき、2030年代半ばには日本の原発をゼロにできる。③もんじゅと再処理もやめさせることで核燃料サイクルも無くせるという趣旨の発言をしている。
筆者は、独立性を持ち、適切な運営を行う原子力の規制当局が必要と考え、その実現の主張を政府、学界などに訴えてきた。ところが2012年に設立された原子力規制委員会は、事業者や学会との対話を行わず、活断層や震源を特定しない地震動に代表される反対派の虜になったのかのような偏重した審査を行っている。この事態を憂慮している。
菅氏の発言の示すものは、現在の原子力規制委員会が、脱原発政策を推進した当時の民主党政権が残した強固な「脱原発推進組織」であることを物語っているように思える。
原電敦賀2号機の性急な審査
特に問題なのは、日本原電敦賀発電所の敷地内にある破砕帯の審査だ。これが「活断層」と認定されれば、同原発は廃炉に追い込まれる。菅氏、民主党の意向という背景があるからであろうか、規制委員会は、特に原電敦賀2号の敷地内の断層を十分な審議をしないまま「活断層」と烙印を押そうと懸命の短縮日程をたてた。原電が昨年調査報告書を提出してからのこの1年の間に1回の現地調査と2回の会合しか開いていないのに、8月27日と9月4日に2週連続会合を開くというのである。
8月11日の規制庁と事業者である原電の議事要旨が公開されている。
これを見る限り、敦賀2号の議論はしばらく継続するように見える。しかし、地元の福井新聞は、8月27日の会合では、原電は参加させず有識者のみの会合を開いて方向性を議論し、9月4日の会合で評価書の修正などについての骨子案を提示すると報道している。
先の議事要旨によれば、規制庁は4日の会合では原電も交えて議論を深めていくとしている。福井新聞の記事が正しいのであれば、規制庁は端から原電と科学技術的な議論をする気はなく、速やかに活断層と結論づけた骨子案の取りまとめにかかり、島崎委員の在任中に決着させたいとの規制委員会側の意図が見える。
提出新事実を考えれば「活断層はない」
焦点となっているD-1 破砕帯は、敦賀2 号機の建設当時から調査、評価がなされ、活断層では無いとの判断から設置許可がなされている。(参考・GEPR記事『敦賀原発の活断層判定、再考が必要(上)・対話をしない原子力規制委』『(下)・行政権力の暴走』)
しかし、規制委員会は、菅直人元首相の意図を汲んだかのように新規制基準のなかに、活断層の上に原子力発電所の設置を認めない条文を入れ、科学技術的な議論を十分することなくD-1破砕帯を活断層と認定するような動きを見せている。
原電は、敦賀の敷地内破砕帯の大がかりなトレンチの調査結果から以下の科学技術的な知見を得て、これを報告書にまとめ、規制委員会に既に提出している。(注・前期記事参照)重要なのは、この報告書が、「D-1破砕帯の活動性」について、テフラ分析(火山灰の特徴からの分析)と花粉分析(花粉の種類を特定し、当時の気候から地層の堆積時期がわかる)から、D-1 破砕帯(G断層含む)は、少なくとも中期更新世以前(12~13 万年前よりもさらに古い時代)よりも最近は活動していないとしている点である。
また、「D-1 破砕帯の連続性」について複数の地質的性状から総合的に検討した結果、D-1破砕帯はG断層と一連であり、K断層とは一連ではないと結論づけている点である。すなわち、D-1 破砕帯(G断層含む)は、「将来活動する可能性のある断層等」には該当しないと結論づけ、活断層や活断層に誘導されて動く破砕帯であることを明確に否定する内容である。
これらの新知見は、評価会合においで未だ詳細な科学技術的な検討がなされていない。規制委員会はこれらの新知見を公開の場で十分に審議をし、そのうえで科学技術的な判断を下すべきだ。
(2014年9月1日掲載)

関連記事
-
原子力規制委員会は、日本原電敦賀2号機について「重要施設の直下に活断層がある」との「有識者調査」の最終評価書を受け取った。敦賀2号機については、これで運転再開の可能性はなくなり、廃炉が決まった。しかしこの有識者会合なるものは単なるアドバイザーであり、この評価書には法的拘束力がない。
-
3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。
-
「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。
-
第6次エネルギー基本計画は9月末にも閣議決定される予定だ。それに対して多くの批判が出ているが、総合エネルギー調査会の基本政策分科会に提出された内閣府の再生可能エネルギー規制総点検タスクフォースの提言は「事実誤認だらけだ」
-
7月22日、インドのゴアでG20エネルギー移行大臣会合が開催されたが、脱炭素社会の実現に向けた化石燃料の低減等に関し、合意が得られずに閉幕した。2022年にインドネシアのバリ島で開催された大臣会合においても共同声明の採択
-
きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき
-
先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。
-
新しいエネルギー基本計画が決まり、まもなく閣議決定される。「再生可能エネルギーを主力電源にする」といいながら再エネ22~24%、原子力20~22%という今のエネルギーミックスを維持したことに批判が集まっているが、問題はそ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)
- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか
- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由
- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す
- 世界の気温が急速に低下していることをオールドメディアは報じない
- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング
- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア
- EU内燃機関禁止を撤回、日本へのドミノ効果は?
- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ
- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ