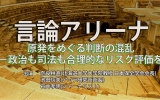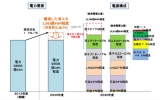今週のアップデート - アゴラ静岡シンポジウム27日開催(2014年9月16日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) 第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」
アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。
アゴラ・シンポジウムで基調講演『東日本大震災が教えるもの』を行う畑村洋太郎氏に、寄稿をいただきました。畑村氏は震災前から災害、原発、津波のリスクを指摘してきました。政府福島原子力発電所事故調査・検証委員会では委員長を務めました。
「想定」「避難」「復興」「全体像」「共有」「平時と有事」「複合災害」「過去の経験」などのキーワードで表される8つの視点から問題を分析。防災、そして個人の生活に示唆の富む文章です。ご一読ください。
3) 専門家の陥る数字と論理の罠—効果的なリスコミとは?【アゴラ・シンポ関連】
アゴラ・シンポジウムの第1セッション『東海地震のリスクをどう考えるか』に出席いただく西澤真理子氏に寄稿をいただきました。西澤氏はリスクコミュニケーションコンサルタントとして、リテラジャパンという会社を経営しています。福島の実務体験を参考にして、効果的なリスコミの方法を提言しています。
4)欧州と米国から学ぶエネルギー安全保障【アゴラ・シンポ関連】
アゴラ・シンポジウムの第2セッション『エネルギーの選択と環境問題におけるリスクを考える』に出席いただく常葉大学経営学部教授の山本隆三氏に寄稿をいただきました。他国のエネルギーでのリスクの事例を紹介し、エネルギーを多面的に考え、原子力を位置づけることの必要性を訴えています。
5)蟷螂の斧―河野太郎議員の電力システム改革論への疑問・その3
国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏の寄稿です。電力の系統接続という専門的な問題で、電力会社批判を強める河野太郎衆議院議員への疑問です。澤氏はアゴラ・シンポジウムでは第2セッションのパネリストとして出席します。
今週のリンク
ニューズウィーク日本版。9月10日記事。池田信夫アゴラ研究所所長のコラムです。原子力規制委員会が、日本原電の敦賀原発2号機の下に活断層があるとの主張をまとめつつあります。原電、内外の有識者の疑問に真剣に応えようとしません。これを「閉じこもる」という表現で批判しています。
内閣府。9月12日公表。これまで公開されていなかった、政府事故調査委員会のヒアリング記録が公開されました。当時の菅直人首相、故・吉田昌郎東京電力福島第一原発所長などの生の証言が記録されています。事実関係では新しいものは、政府報告書に記載されているためありません。しかし当事者の心情がうかがえ、大変興味深いものとなっています。
3)朝日新聞社、記事取り消し謝罪 吉田調書「命令違反し撤退」報道
朝日新聞。9月12日記事。吉田調書の公開を受け、朝日新聞は同社が5月に報道した吉田調書報道で「命令違反し撤退」という趣旨の記事を書いたことを誤報と認め、謝罪しました。慰安婦報道と合わせ、同社には批判が集まっています。
4)9月10日放送分の報道ステーション(テレビ朝日)での報道について
原子力規制委員会。9月12日公表。テレ朝の火山の審査基準を修正するという報道の誤報をしたこと、また田中俊一委員長の「答える必要がない」という言葉を編集し、火山の審査に対する質問への答えにしたことを指摘。テレ朝側は、その事実を認め謝罪しました。(委員会の報告文)
内閣府原子力防災会議。9月12日公表。再稼働手続きが進む九州電力の川内原発(鹿児島県)について、災害時の避難対策をまとめました。計画の実行準備が期待されます。そして再稼働手続きが進むことになります。

関連記事
-
経済産業省は再エネ拡大を「燃料費の大幅削減策」として繰り返し訴えている。例えば2024年1月公表の資料では〈多大な燃料費削減効果を有する〉と強調した※1)。 2022年以来、未曽有の化石燃料価格高騰が起きたから、この局面
-
ドバイではCOP28が開かれているが、そこでは脱炭素化の費用対効果は討議されていない。これは恐るべきことだ。 あなたの会社が100億円の投資をするとき、そのリターンが100億円より大きいことは最小限度の条件だが、世界各国
-
16年4月29日公開。出演は原子力工学者の奈良林直(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。4月の九州地震、3月には大津地裁で稼動した高浜原発の差し止めが認められるなど、原子力の安全性が問われた。しかし、社会の原子力をめぐるリスク認識がゆがんでいる。工学者を招き、本当のリスクを分析している。
-
「生物多様性オフセット」COP15で注目 懸念も: 日本経済新聞 生物多様性オフセットは、別名「バイオクレジット」としても知られる。開発で失われる生物多様性を別の場所で再生・復元し、生態系への負の影響を相殺しようとする試
-
経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。
-
前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす
-
日本の温室効果ガス排出は減少している。環境省はカーボンニュートラル実現について「一定の進捗が見られる」と書いている。 伊藤信太郎環境相は「日本は196カ国の中でまれに見るオントラックな削減をしている」と述べ
-
12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間