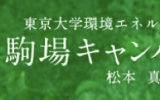今週のアップデート - 再エネ振興策の行き詰まりを考える(2014年10月14日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」・映像
アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開しました。東南海地震とエネルギーのリスクを専門家が集い、語り合いました。内容の報告を近日中に公開します。
電力会社の再エネ接続の保留、経産省の見直し策を、分かりやすくまとめました。
今週のリンク
1)九州電力はなぜ再エネ接続を留保するのか- 衝撃と背景を考察、打つべき一手を提案する
日経ビジネス10月6日号。再エネ研究者の山家公雄さんの論考です。制度の存続を前提に、揚水発電の利用などによる問題の解決を提案しています。
2)太陽光発電の参入凍結 大規模施設
増設も認めず 買い取り価格、大幅下げへ 経産省検討
日本経済新聞10月11日記事。経産省の再エネ振興策の転換を伝えています。
AFP(フランス国営通信)10月11日記事。フランスが10日、現在の発電に占める原発の依存を現在の75%から10年以内に50%にする法案を可決しました。再生エネルギーの拡充と省エネを柱としますが、野党からは実現を疑問視する声が広がっています。
河北新報10月11日掲載。福島県民の4割超が、脱原発に伴う電気料引き上げを容認する考えであることが河北新報社のアンケートで分かりました。福島第1原発事故を契機とした厳しい市民感情を裏付けています。26日に福島県知事選が行われますが、現時点で全候補が脱原発を訴えています。
5)再エネ、支援政策の光と影(上)–太陽光、投資10倍の急拡大
GEPR記事3月24日。再掲載。今回の再エネ政策の見直しの背景になった功罪について検証しています。全3回。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。
-
立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ
-
1.太陽光発電業界が震撼したパブリックコメント 7月6日、太陽光発電業界に動揺が走った。 経済産業省が固定価格買取制度(FIT)に関する規則改正案のパブリックコメントを始めたのだが、この内容が非常に過激なものだった。今回
-
経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日
-
世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太
-
10月21日(月)、全学自由研究ゼミナール「再生可能エネルギー実践講座」3回目の講義のテーマは、地熱発電です。地熱は季節や天候に関係なく安定した自然エネルギーで、日本は活火山数119個を有し、地熱資源量は2347万kWと米国、インドネシアに次ぐ世界第3位の地熱資源大国です。
-
去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月3
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)
- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか
- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由
- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す
- 世界の気温が急速に低下していることをオールドメディアは報じない
- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング
- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア
- EU内燃機関禁止を撤回、日本へのドミノ効果は?
- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ
- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ