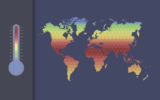年収5億ドルの“石油大国”IS、輸出ルートを断て!
 シリアでIS攻撃をするロシア軍機
シリアでIS攻撃をするロシア軍機「世界で最も富めるテロ組織」
過激派組織IS=イスラミックステートは、なぜ活動を続けられるのか。今月のパリでのテロ事件、先月のロシア旅客機の爆破、そして中東の支配地域での残虐行為など、異常な行動が広がるのを見て、誰もが不思議に思うだろう。その背景には潤沢な石油による資金獲得がある。
世界のテロ組織の資金を米財務省が追跡している。今年の報告では、14年のISの石油からの収入は5億ドル(600億円)と推計されている。2013年末段階で、優秀な情報機関モサドを持つイスラエル政府は、ISの資産総額を20億ドル(2400億円)と推計し、「世界で最も富めるテロ組織」と、警鐘を鳴らしていた。
これまでISは誘拐による原油の販売、身代金ビジネス、シリアにある遺跡からの盗掘品の売りさばき、参加したイラクの旧フセイン政権残党の持つ隠し財産などを軍資金にした。ISはシリア北部で数カ所しか油田を占領していなかったが、昨年イラク中部に進出して、より多くの油田を手に入れた。そこからの原油を売り、資金がさらに豊かになった。
イラクでは以前から中央政府に統制されない、現地の有力者や部族の協力による、トルコ-東欧へつながる石油密輸ルートがあったという。これをISは乗っ取ったもようだ。ISの原油はもちろん表で売買できないが、それを精製して闇市場に流す業者がいるらしい。
ある石油アナリストは、「東欧でガソリンの余剰感が強く、それが西欧の市場の需給が緩む原因になっている。ISの影響らしいと言われるが、実態は不明なままだ」という。原油は使うために精製が必要だが、ガソリンは比較的取り出しやすく、粗悪な品質でも車は動く。
シリア国境で、トルコ軍が作戦行動中のロシア軍機を24日に撃墜。両国の非難合戦が続いている。ロシア大統領府が「トルコがISから石油を買っている」と非難。トルコのエルドアン大統領は27日の演説で「恥ずべき中傷。もしそれが事実なら私は辞任する」と言い切るなど、ISの石油が注目を集めるようになっている。
ロシアの空爆の拡大
「オバマ政権も世界の中東専門家もISを過小評価していた。10万人と推定される兵士・組織員を養える集団に成長している。石油を断たなければならない」。米通信社ブルームバーグは11月、米ランド研究所のアナリストのコメントを伝えている。
米国は昨年夏から空爆を行っている。ただし米軍は原油施設の本格的な破壊には、慎重だったようだ。これらは現地企業の資産だ。しかもシリアとイラクではIS以外にもさまざまな武力集団が紛争にかかわる。空爆強化は状況を一段と混乱させかねない。
ところが事態は動いた。ロシアが今年夏から、シリア政府軍に協力してISに空爆を開始。先月のロシア旅客機爆破事件でISが関与したことが確認されると後で、プーチン大統領は「地球上のどこにいてもテロリストを見つけ出して処罰する」という激しい怒りを表明し、その指示で熾烈な攻撃を継続している。
今月18日にロシア国防省はISの原油を運搬するタンクローリー車を500台、24日に1000台破壊したと発表し、映像を公開した。画像では、数十台の車列が映り、それが爆撃で一瞬にして消し飛ぶ姿が映っていた。ISの石油ビジネスの大きさが印象づけられる映像だった。そして米国防省も石油施設への空爆写真を公開した。
“空気を読まない”乱暴者のロシアが動いたことで、ISの石油ビジネスへの攻撃がようやく本格化している。その影響はどうなるのだろうか。
アラブと日本、安全保障協力の可能性
中東の騒乱は、日本から遠く離れた話に見えるかもしれない。ところが、日本の安全保障と結びつく話が浮上している。あるエネルギーのニュースレターによれば、GCC(湾岸協力機構、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、クウェート)諸国の新聞で、今年夏の日本の安保法制の整備を好意的に受け止める報道が相次いでいるという。6月のサウジ現地紙「アル・ヨウム」は、「GCCは石油を通じて、日本と関係を深めよ」という論説を掲げた。
これらの諸国は、民主化はされていない王政国家で、国内はその強権的統治によって、比較的政情は安定している。ただしサウジに隣接するイエメン、またシリアの混乱に巻きこまれないように難民受け入れを拒絶し、ISやテロ組織アルカイダを取り締まり、軍事活動を行う米国などと協調している。
彼らは親日であり、09年以来、サウジから紅海の対岸にあるアフリカのジプチ共和国に自衛隊が基地を設け、海賊対処行動をしていることも注目している。日本とアラビアは距離がある。しかし経済的な利害の一致する日本の軍事面での協力を求めているのだ。
イランの核問題が一段落したが、まだ中東の政治的混乱は続く。ISへの攻撃強化は日本にとっても影響が大きい。テロの危険の拡大に加えて、その先行きは国際石油市場に影響を与え、日本のエネルギー安全保障にもつながる。そして、日本の石油の8割、天然ガスの3割は、GCC諸国から購入している。中東の混乱を私たちは今後も注視しなければならない。
(2015年11月30日掲載)

関連記事
-
東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。
-
前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当
-
IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は
-
去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月3
-
世界でおきているESGファイナンスの変調 昨年のCOP26に向けて急速に拡大してきたESGファイナンスの流れに変調の兆しが見えてきている。 今年6月10日付のフォーブス誌は「化石燃料の復讐」と題する記事の中で、近年の欧米
-
途上国の勝利 前回投稿で述べたとおり、COP27で先進国は「緩和作業計画」を重視し、途上国はロス&ダメージ基金の設立を含む資金援助を重視していた。 COP27では全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年ま
-
札幌医科大学教授(放射線防護学)の高田純博士は、福島復興のためび、その専門知識を提供し、計測や防護のために活動しています。その取り組みに、GEPRは深い敬意を持ちます。その高田教授に、福島の現状、また復興をめぐる取り組みを紹介いただきました。
-
「GEPR」を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供しています。9月3日は1時間にわたって「地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える」(YouTube)を放送しました。その報告記事を提供します。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間