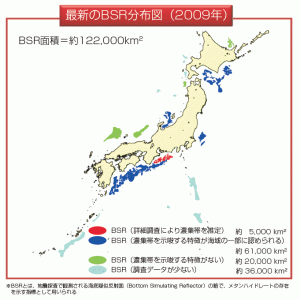メタンハイドレート、役立つエネルギー源か?
無資源国日本の新エネルギー源として「燃える氷」と言われるメタンハイドレートが注目を集める。天然ガスと同じ成分で、日本近海で存在が確認されている。無資源国の日本にとって、自主資源となる期待がある。ただしMHは、埋蔵量の実態は不明で、他のエネルギー源に比べて有利な点はそれほど見えない。開発の現状を整理してみよう。
(写真1)燃えるメタンハイドレート(経産省資料)
メタンハイドレートとは何か
「メタンハイドレート」(MH)は海底や永久凍土などに分布するメタンと水分子からなるシャーベット状の物質だ。深海や土中の圧力と冷却によって氷になった。
経産省・資源エネルギー庁は2015、16年度予算で、各年約130億円のMHの調査費用を獲得した。(経産省資料)厳しい財政事情の中でかなりの金額だ。福島第一原発事故以来新しいエネルギー源の獲得が政治課題になり、安倍政権の重要政策に「海洋開発」が盛り込まれている。それで予算を取りやすくなったのだろう。自治体の期待も大きい。2012年にはMHの採掘などの支援を行うため、新潟県など10の自治体が「海洋エネルギー資源開発促進日本海連合」を立ち上げた。
経産省は2000年代から、JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)に予算を投じて太平洋の和歌山沖、熊野灘近海でMHの調査を進めてきた。同海域では水深1000‐3000メートルの海底に小粒のMH粒子が散在。18年度を目標に商業生産を行う予定だ。(JOGMECホームページ)
(図表1)日本近海におけるメタンハイドレートの分布
(経産省資料より。ただし、上記調査に加えて14年公表の調査では、日本海側の緑色の一部の隠岐島沖、若狭湾沖で凝集帯が見つかり、また記載のない能登半島沖、秋田沖でも存在が確認された。)
突然政治的な関心を集める
ここ数年、MHに多くの人が関心を持つようになった。民間シンクタンクの独立総合研究所(独研・東京)の社長で、政治評論活動で知られる青山繁晴氏が、その発信力を活かして訴えたためだ。青山氏は、今年7月の参議院選挙で自民党公認候補として当選し、安倍晋三首相とも親しいとされる。
独研は2004年ごろから東大などと組んで調査を行った。日本海側の新潟沖の水深数百メートルの浅い近海で結晶状のMHの巨大な塊を大量に見つけた。従来は石油工学の延長で地質調査、ボーリングを行った上で探査した。しかし独研は魚群探知機を使いメタンの泡を探してMHの集積する場所を見つける方法を開発した。この方法ならば調査が容易だ。
青山氏は日本海側の探査を主張したが、一度動きだしたことを行政はなかなか変えない。政府支援によるJOGMECの調査は太平洋側で先行した。しかし3・11以降のエネルギー関連の予算拡充、そして自民党議員に支持者の多い青山氏の主張が影響して、日本海側でも調査が2013年から行われるようになった。自民党では経産省政務官を務めた平将明衆議院議員、片山さつき参議院議員も、MH予算の確保に尽力したと、自ら表明している。そして14年にはこれまでの調査より数多く、MHの集積場所が見つかった。独研の調査方法も有効に機能したという。
まだ採算ラインに乗らず
日本の公益のために、新しいエネルギー源を開発することは必要であり、MHは期待できる資源だ。しかし問題は、投資が有効なものになるかということだ。青山氏にこの問題を複数回聞いた。2011年6月18日号の週刊東洋経済の取材で次の話が出た。
青山氏に面会した大手石油会社の社長は本音を話したという。「あなた方のMHの発見は大変なことだ。今までの枠組みが全部変わる。戦争に負けた日本が自主資源を持つのはまずい。アメリカや国際メジャー石油資本の言う通り資源を海外から買っていればすべて丸く収まる」。親交のあった資源エネルギー庁長官(当時)にも「影響が大きすぎる」と〝忠告〟されたという。
また中国、韓国の企業、政府や軍が、日本海のMHに関心を向けて調査を行い、情報収集を行っている形跡があるという。
「エネルギーをめぐる日本の官民は既得権益と保身で凝り固まり、それを学界が支えるアンシャンレジューム(旧体制)がある。メタンハイドレートを活用し、自主エネルギーの国に変えてほしい」と、青山氏は訴えていた。
たしかにこれまで利益を得てきた既得権益層は警戒しそうな話だし、政府がエネルギー確保に躍起になる中国や韓国と違って、日本の政治家の動きは鈍い。青山氏はMHの将来を訴えるときに、上記の「既得権益層との戦い」とか、「国防」に絡めて主張。これは彼の支持者の保守層の琴線に触れ、MHの開発は支持を集めた。筆者はインターネット、SNS、紙媒体で新しいエネルギーの解説をするが、メタンハイドレートをめぐる質問が大変多い。
一般の人が重要な社会問題を共有し、知見を深めることはとても大切だ。原子力では、こうした人々の議論の積み重ねが不足していたゆえに、福島事故の後で不信が高まり混乱が続いている。しかし、そうした議論の広がりは、専門家の意見が埋もれ感情的になることがある。もちろん青山氏も、MHを支持する人もその危険は十分承知していると思うが、MHの開発に過剰な期待を持つ人が多い。
エネルギー問題は投資が常に巨額になるため、仮にそれが失敗すると損失は莫大なものになる。MHの開発では、そうさせてはならない。
現時点では埋蔵量が不明
エネルギーの世界には「井戸から軸へ」(Well to Wheel)という言葉がある。石油は油井などから取り出しただけでは使うことはできない。車や工場機械の駆動軸にまでつながる流通、エネルギー化の道筋が必要という意味だ。それにはそのエネルギーが、ビジネスとして回り続けるものでなければならない。
そうした観点からMHを考えると、活用までに次のことが必要になる。
1)埋蔵量の確認、2)採掘技術の確立、3)運搬と発電や産業、家庭用向けに転換するインフラの整備、4)産官学民の協力体制の確立、5)他のエネルギーと比べた安いコストでの利用見通しーというものだ。
しかしMHでは、実際には1)の段階である埋蔵量の確認さえ終わっていない。現時点で、重要なエネルギー源とするのは無理がある。MHの開発の遅れを「既得権益の妨害」と問題を規定するのは無理があるだろう。
90年代にMHの開発可能性調査を、国の委託を受けて行った、石井吉徳東大名誉教授は、「メタンハイドレートは資源ではない。「質」が悪い」「利権を生みかねない」と指摘している。(石井氏ブログ記事)ある商社の幹部は「既得権益のためにMHを使わないのではない。既存のエネルギーより量と値段でいい内容になれば、喜んで取り扱う」と述べていた。
経産省・エネ庁は2001年ごろ、MH活用の目標を立てた。2010年代後半に商業化し、発電換算で1キロワットアワー当たり、20-25円程度で開発するとしている。現在の太陽光の同30円前後より安いが、原発の同5円前後に比べると高すぎる。そして今、シェール革命が起こり、米国などに多数あるシェール層から、ガス、石油が大量に採掘されている。そして2016年にはシェールガスの日本への輸入が始まる。ガス、石油が世界的に余る傾向が出てくるかもしれない。また日本は少子高齢化、産業空洞化の中で、エネルギーの需要が今後減ると見込まれている。
さらに温暖化への対策として、化石燃料の使用抑制が、国際的に重要な問題になっている。メタンのCO2の排出の程度は単位エネルギーでかなり高い。もちろん燃焼の方法によって異なるが、その問題への配慮も必要になる。
日本の化石燃料の輸入量は年20兆円(16年度見通し)と膨大なもので、その削減は必要だ。だからといって、不明な点の多いMHに転換するまでに巨額の投資をする必要は今のところ、見当たらない。今するべきなのは技術的に確立した既存のエネルギー源の化石燃料、再エネ、原子力を、適切に使うことだ。今は原子力が稼働していない。そういう重要問題を放置して、MHの開発に動くのは順序が違うだろう。
調査と議論の深化がMHの未来に必要
一方で私は石井東大名誉教授のようにダメと切り捨てる態度も疑問だ。青山氏の予想通り、日本の経済水域内の浅瀬で大量にMHが見つかれば日本は突如、資源大国になるかもしれない。
例えば日本の石油をめぐる過去の経験が考える材料になるだろう。日本は事実上の植民地だった満州(現中国東北部)で石油を探したが見つからなかった。ところが1953年に黒竜江省で大慶油田が発見され、1990年代まで大量にガスと石油を産出した。日本は満州を1945年の敗戦で放棄するが、もしこれを戦前に活用できたなら、エネルギー不足を一因にして起こり、それを供給する海上交通線の切断によって日本が敗北した太平洋戦争の様相はまったく違ったものになっただろう。石炭、石油、天然ガスなど、新たなエネルギーの出現が歴史と経済の姿を何度も変えた。もしかしたらMHは日本の未来を良い方向に変えるかもしれない。エネルギーの変革は社会への影響が大きいのだ。(もちろん中国東北部の地下資源は中国の国家と国民のものであり、それを使えたかもしれないという仮定は倫理的に問題であるが、仮説として使う)
メタンハイドレートの開発を「政治イシュー」にして騒ぐ必要はない。経産省は今、MH開発の商業化のためのロードマップを検討している。(メタンハイドレート開発実施検討会)その審議の過程をよりオープンな形に、そして多くの人に知られるようにして知恵を集め、年130億円も使う国費を有効に活用することを考えるべきだ。そして日本海側の埋蔵量を早急に確定することだ。冷静に問題に向き合い、できる限り感情や利権を排除した決断が必要である。
(2016年7月19日更新)
石井孝明・経済ジャーナリスト、GEPR編集者

関連記事
-
アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過
-
製品のCO2排出量表示 環境省、ガイドラインを策定 環境省は製品の製造から廃棄までに生じる二酸化炭素(CO2)の排出量を示す「カーボンフットプリント」の表示ガイドラインを策定する。 (中略) 消費者が算定方法や算定結果を
-
(前回:温暖化問題に関するG7、G20、BRICSのメッセージ①) 新興国・途上国の本音が盛り込まれたBRICS共同声明 新興国の本音がはっきりわかるのは10月23日にロシア・カザンで開催されたBRICS首脳声明である。
-
原油価格は1バレル=50ドル台まで暴落し、半年でほぼ半減した。これによってエネルギー価格が大きく下がることは、原油高・ドル高に加えて原発停止という三重苦に苦しんできた日本経済にとって「神風」ともいうべき幸運である。このチャンスを生かして供給力を増強する必要がある。
-
岸田首相肝いりのGX実行会議(10月26日)で政府は「官民合わせて10年間で150兆円の投資でグリーン成長を目指す」とした。 政府は2009年の民主党政権の時からグリーン成長と言っていた。当時の目玉は太陽光発電の大量導入
-
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。
-
ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。 今回のウクライナ侵攻をどう見るか 今回のロ
-
去る4月22日から経済産業省の第13回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆるFIT法)の改正議論が始まった。5月3
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間