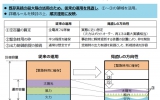水素社会の実現、政治が支える- 福田峰之衆議院議員
 水素エネルギーの活用への期待が盛り上がっている。今年3月に安倍首相が、福島訪問で同地を水素活用のセンターにすることを表明。トヨタ自動車が燃料電池自動車(FCV)「MIRAI」を2015年に発売し、大変な人気になっている。(写真はMIRAI)
水素エネルギーの活用への期待が盛り上がっている。今年3月に安倍首相が、福島訪問で同地を水素活用のセンターにすることを表明。トヨタ自動車が燃料電池自動車(FCV)「MIRAI」を2015年に発売し、大変な人気になっている。(写真はMIRAI)
水素をめぐり政治家として政策提言を積極的に行っている福田峰之衆議院議員(神奈川8区・横浜市(青葉区、緑区)、自民党)のインタビューを紹介する。
かつては重要な政策課題や産業支援には政治の支援があった。昭和30年代の原子力の推進では中曽根康弘元首相、正力松太郎初代科学技術庁長官などが後押しした。ところが、今はそうした例が少なくなっている。業界や利権との癒着を批判する厳しい世論があるためだろうが、それによって重要な問題の社会的な支援が継続されない問題も出ている。
要はバランスだ。福田氏のような政策通で真摯に普及を目指す政治家を含めて、多くの支えがある水素エネルギーは、幸運な例だろう。その成長を期待したい。
なお、このインタビューは専門誌エネルギーフォーラム5月号の原稿に掲載され5月に行われた。転載を認めていただいた関係者に感謝を申し上げる
(以下、福田議員(写真)インタビュー本文)
問題を「語り続ける」必要性
私は自民党議員連盟「FCVを中心とした水素社会実現を促進する研究会」(通称:水素議連)の事務局長として、会長である小池百合子衆議院議員(編注・インタビュー時点)や仲間と共に、水素社会の実現を政治の立場から支えようとしている。水素の活用による国民の幸福を確信している。
どんな政策でも誰かが語り続けなければ、その政策は形になっていかない。私は水素について「語り続ける」ことを、自らの政治課題の一つにしている。
安倍晋三首相が3月の福島視察で「福島を水素社会先駆けの地に」と表明したことで、水素エネルギーへの関心が一段と高まったのは喜ばしい。安倍首相の指示と支援の下で、着々と前に進んでいる。13年、14年に政府・経産省が自民党と協力して取りまとめた「水素・燃料電池戦略ロードマップ」、また「水素社会を実現するための政策提言」が着実に実行されている。2020年の東京オリンピックまでに、水素インフラを整え、そこから日本社会がさまざまメリットを享受できるようにすることが、政府・自民党の目標だ。
目標として2020年代半ばには、FCVでハイブリッド車並みの価格を実現し、また家庭に置ける燃料電池を開発し、発電に活用するなど、水素が国の支援がなくても経済で活用され、その関連製品が商品化されることを目指している。FCVではトヨタ自動車、ホンダ、また燃料電池ではJXグループなど、開発力のある立派な会社が、商品化を行い、開発努力を重ねており、大変心強くありがたく思う。そして、目標は十分に実現が可能だ。
政治が水素振興でできること
今の政治の課題は、毎年の予算措置、制度設計で、政府・経産省と協力しながら支援を続けることだ。さらにやらなければならないのは、国際的な連携、規格づくりであると思う。市場を世界に求めることで、水素が大きなビジネスになるだろう。日本は製品化、インフラ整備でも他国に比べて進んでいるために、そうした規格作りで主導的な役割を果たせるはずだ。
育成中の新エネルギーの支援策の選択も、政治の現場で今後必要になると懸念する声がある。私は、それぞれの新エネで、用途に応じた棲み分けができると思う。対立するものではない。例えば、遠距離を動く車は水素自動車、近距離は家庭用水素燃料で発電した電池でEVが走るなどの使い分ける未来が考えられる。10年後には技術革新によって再エネ発電で使った電気を運ぶE水素、また産業用や発電用への水素の活用も、視野に入るだろう。エネルギーの効率的な多元化という日本の追求してきた目標が、水素の活用によってできると思う。
国民の皆さまにお願いしたいのは、こうした動きにビジネスとして、消費者として参加し、メリットを享受しながら、水素社会の実現を支えていただきたいと思う。これは日本が優位性のある分野であり、安倍政権の目指す「強い経済」を担う産業になりうる。私はそうした動きを政治の立場から支えていきたい。(談)
(構成・石井孝明 GEPR編集者)

関連記事
-
前回に続き「日本版コネクト&マネージ」に関する議論の動向を紹介したい。2018年1月24日にこの議論の中心の場となる「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」の第二回が資源エネルギー庁で開催されたが、
-
中川先生はチームを組んで福島の支援活動を続けてきました。どういう理由からだったのですか。中川 私は、東大病院の緩和ケア部門の責任者です。この部署では放射線技師、看護師、医師、心理学カウンセラーなどさまざまな専門家ががんの治療に関わります。そのために原発事故で、いろいろな知恵を活用しやすいと思いました。
-
エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供している。9月3日は1時間にわたって『地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える』を放送した。
-
豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算
-
小泉純一郎元首相の支援を受けて、細川護煕元首相が都知事選に出馬する。公約の目玉は「原発ゼロ」。元首相コンビが選挙の台風の目になった。
-
経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を
-
英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい
-
共存共栄への可能性 私は再エネ派の人々とテレビ番組やシンポジウムなどで討論や対話をする機会が時々ある。原子力推進派のなかでは稀な部類であると思っている。メディアでもシンポジウムでも、再エネvs.原子力という旧態依然の構図
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間