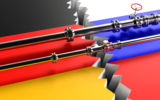炭素税を「国境調整」する保守派の提案
パリ協定を受けて、炭素税をめぐる議論が活発になってきた。3月に日本政府に招かれたスティグリッツは「消費税より炭素税が望ましい」と提言した。他方、ベイカー元国務長官などの創立した共和党系のシンクタンクも、アメリカ政府が炭素税を採用するよう求める提言を出した。彼らの柱は4つある:
- ゆるやかに炭素税を増税し、40ドル/トン程度にする
- 炭素税の収入は一般財源として全国民に還元する
- 国際的な炭素税率の違いは国境調整し、アメリカ国内で課税する
- 環境規制を大幅に緩和する
この提言のポイントは、炭素税による国際競争力の低下を国境調整することだ。炭素税の最大の問題は、高い税率をかけると製造業の国際競争力が低下することだが、彼らの提言では、国内で払った炭素税は輸出するとき払い戻され、輸入品には国境で(両国の差に相当する)炭素税をかける。
これは共和党が提案している税制改革案の考え方で、すべての輸入品に20%の関税を課し、輸出品に20%の補助金を出す。フェルドシュタインの説明では、国境税は輸入減と輸出増をもたらすので、アメリカの貿易赤字は減るが、貿易収支はその国の投資と貯蓄の差額に等しいので、国境調整で変化しない。変化するのは為替レート、つまりドル高だ。たとえば日本からの輸入品には20%の関税がかかるが、円が20%下がると、その効果は相殺される。
フェルドシュタインやマンキューが提案していることでわかるように、国境調整税は保護主義ではない。これは課税ベースを(個人や法人の)所得から支出に切り替え、その負担を国際的に均等化するものだ。彼らの炭素税も、需要を抑制する消費税の代わりに「外部性」を内部化する炭素税をかけようというものだ。
たとえばアメリカが40ドル/トンの炭素税をかけると、炭素税のない国はそれに「ただ乗り」して輸出できる。このときアメリカが輸入品にも40ドルの炭素税をかけ、輸出品には炭素税を払い戻せば、貿易収支に中立になる。日本で財界が炭素税に反対しているのも「国際競争力」が理由だが、これも国境調整すれば炭素税のバイアスはなくなる。
しかし国際調整税は保護主義的なイメージが強いので、輸入コストの上がる流通業界や石油業界などが反対している。足元のふらついてきたトランプ政権が、石油業界の反対を押し切って実行できるかどうかも不明だが、もしアメリカがこういう課税の国際的な均等化を始めると、税制の枠組が大きく変化する可能性がある。

関連記事
-
原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼
-
太陽光パネルを買うたびに、日本国民のお金が、ジェノサイドを実行する中国軍の巨大企業「新疆生産建設兵団」に流れている。このことを知って欲しい。そして一刻も早く止めて欲しい。 太陽光パネル、もう一つの知られざる問題点 日本の
-
経済産業省は東電の原子力部門を分離して事実上の国営にする方向のようだが、これは順序が違う。柏崎刈羽原発を普通に動かせば、福島事故の賠償や廃炉のコストは十分まかなえるので、まず経産省が今までの「逃げ」の姿勢を改め、バックフ
-
3人のキャスターの飾らない人柄と親しみやすいテーマを取り上げることで人気の、NHK「あさイチ」が原子力発電を特集した。出演者としてお招きいただいたにもかかわらず、私の力不足で議論を深めることにあまり貢献することができなか
-
米ニューヨーク・タイムズ、および独ARD(公営第1テレビ)などで、3月7日、ノルドストリームの破壊は親ウクライナ派の犯行であると示唆する報道があった。ロシアとドイツを直結するバルト海のガスパイプラインは、「ノルドストリー
-
女児の健やかな成長を願う桃の節句に、いささか衝撃的な報道があった。甲府地方法務局によれば、福島県から山梨県内に避難した女性が昨年6月、原発事故の風評被害により県内保育園に子の入園を拒否されたとして救済を申し立てたという。保育園側から「ほかの保護者から原発に対する不安の声が出た場合、保育園として対応できない」というのが入園拒否理由である。また女性が避難先近くの公園で子を遊ばせていた際に、「子を公園で遊ばせるのを自粛してほしい」と要請されたという。結果、女性は山梨県外で生活している(詳細は、『山梨日日新聞』、小菅信子@nobuko_kosuge氏のツイートによる)。
-
メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい
-
アゴラチャンネルにて池田信夫のVlog、『地球温暖化はあと2℃以内』を公開しました。 ☆★☆★ You Tube「アゴラチャンネル」のチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録すると、最新のアゴラチャンネルの投稿をい
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間