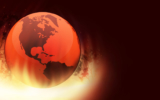民主党政権の「原発事故責任」を総括するとき
まもなく3・11から10年になる。本書は当時、民主党政権の環境相として福島第一原発事故に対応した細野豪志氏の総括である。当時の政権の誤りを反省し、今も続くその悪影響を考えている。

本人ツイッターより
あの事故が民主党政権で起こったのは、不幸なめぐり合わせだった。菅直人首相はヘリコプターで現地に乗り込んで事故処理を妨害し、政権は過剰避難を勧告して、現地には大混乱が起こった。そして細野氏が設定した1ミリシーベルトという環境基準が除染に莫大なコストをもたらし、今も被災者の帰宅を妨害し、福島の農産物や魚に風評被害を起こしている。
本書の第1章は6人の関係者と細野氏の対談だが、前原子力規制委員長の田中俊一氏の話には違和感がある。彼はトリチウムを含む処理水について「海洋放出しかない」と判断して、2014年に経産相に進言したら、大臣が「じゃあ私がやる」と約束したが、やらなかったという。
まるで他人事のように話しているが、田中氏はこの問題についての責任者なのだから、正式に「海洋放出すべきだ」という委員会決定をなぜ出さなかったのか。問題を先送りした政治家に責任はあるが、田中氏も2017年に東電の川村会長が海洋放出を示唆したとき、「はらわたが煮えくり返る」と発言して、処理を混乱させた張本人ではないのか。
もう一つ田中氏が責任を負うべきなのは、田中私案と呼ばれる怪文書で原発の再稼動を法的根拠なく阻止し、原子力規制委員会が原発の再稼動を審査するかのような慣例をつくったことだ。これは後に委員会が「再稼動の審査はしていない」と否定したが、いったんできた慣例は変わらなかった。これについては何も語っていない(細野氏も質問していない)。
フクシマを食い物にする人々
第2章は現地の人6人との対談だが、林智裕氏は「事故を千載一遇のチャンスと考えた人々が問題を長引かせてきた」という。安全神話が崩壊したのだから、必要なのは科学的事実だったが、マスコミは「プロメテウスの罠」や「核の神話」といった新たな神話をつくり、人々に核への恐怖を植えつける宣教師になった。
2013年に国連は「放射能の人的被害はない」という報告書を出したが、マスコミはそれを無視し、フクシマという言葉でビキニ環礁など無関係な問題と混同して、その恐怖を世界に売り込んだ。その意味で福島事故は、民主党政権とマスコミと活動家が被害を何倍にも誇張して作り出した情報災害だった。
これはコロナと似ている。両者に共通するのは不確実性の中の最悪の場合だけを想定する発想である。本書にも登場する近藤駿介氏(事故当時の原子力委員長)のシミュレーションについて「首都圏で3000万人の避難が必要だった」というデマを拡散している政治家が今もいる。
全国各地で原発の再稼動を差し止めて名前を売る弁護士や、甲状腺癌の過剰検査を求めて「福島は恐い」というイメージを植えつける医師がいる。そしてそういう人々を英雄扱いするマスコミがいる。10年たっても福島を食い物にして、復興を妨げているのはこういう人々である。
彼らは「被災者に寄り添う」と称して、自分たちのリスク評価が大幅な誇張だった事実を隠し、「まだ最終結果はわからない」と逃げる。ここでもコロナと同じく、不確実性が大きいことが言い訳となり、その中で最悪の場合を想定したのは善意だったという免罪符になる。
彼らが人々に与えた恐怖は10年たっても収まらず、1ミリシーベルトは今も福島を呪縛し、処理水は今も放出できない。これもコロナと似ている。行政がいったん最悪の場合を想定して基準をつくると、それが民衆の感情に刷り込まれ、正常化はきわめて困難になるのだ。
そういう福島事故の「戦犯」が野党の政治家である。特に菅氏や枝野幸男氏など当時の責任者がいまだに事故処理の責任から逃げ、「原発ゼロ」などという無責任な主張を続けている。それに比べると自分の責任を直視する細野氏の姿勢は立派だが、今後は民主党政権の責任を追及し、彼らの振りまいてきた放射能デマを是正してほしい。

関連記事
-
有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ
-
トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本
-
エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。
-
私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。
-
地球温暖化予測に使う気候モデルは、上空(対流圏下部)の気温も海水面温度も高くなりすぎる、と言う話を以前に書いた。 今回は地上気温の話。米国の過去50年について、観測値(青)とモデル計算(赤)の夏(6月から8月)の気温を比
-
環境(E)・社会(S)・企業ガバナンス(G)に配慮するというESG金融が流行っている。どこの投資ファンドでもESG投資が花ざかりだ。 もっともESG投資といっても、実態はCO2の一部に偏重しているうえ、本当に環境に優しい
-
EUの気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、2023年の世界の平均気温が過去最高を記録し、産業革命前より1.48℃高くなったと発表した。 これは気温上昇を1.5℃以内に抑えるというパリ協定の努力目標まであと0.02
-
東日本大震災を契機に国のエネルギー政策の見直しが検討されている。震災発生直後から、石油は被災者の安全・安心を守り、被災地の復興と電力の安定供給を支えるエネルギーとして役立ってきた。しかし、最近は、再生可能エネルギーの利用や天然ガスへのシフトが議論の中心になっており、残念ながら現実を踏まえた議論になっていない。そこで石油連盟は、政府をはじめ、広く石油に対する理解促進につなげるべくエネルギー政策への提言をまとめた。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間