科学無視の「脱炭素」談義はいつまで続く?

今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。
いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。
1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす
排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす(日本経済新聞)
マスコミは「CO2が原料」となると何にでも喜んで飛びつくが、何とも無知かつ幼稚な態度としか言えない。
以前にも書いたが、CO2と言うのは炭素の酸化された最終の状態で、保有エネルギーが最低のレベルにある。これを化学原料または燃料などに使うには、CO2から酸素(O)を引き剥がし、水素(H)をくっ付けてやらなければならない。
化学的には、どちらも「還元」操作であり、外部から高温などのエネルギーを加えてあげて、やっと実現できる。大抵は水素と熱エネルギーを消費する工程になるから、むろん、その過程で多くの場合、追加のCO2発生がある。
これを化石燃料を使わず再エネ電力だけで行うと、CO2は出なくても偉く高い製品になる。むしろ、作った水素を原料にするよりエネルギーとして直接使う方がまだマシである。CO2を原料とする原料・燃料製造の人工的プロセスは、ほぼ全部そうである。
1970年代の石油危機以降、CO2を再利用する研究は山ほど行われてきたが、実用化されたものは一つもない現実を見るべきだ。
実際、この種の報道は「実証をめざす」とは書くが「いつまでに実証できる」とは書かない。筆者の経験では、例えば「5年後には実用」と言うのは、多くの場合危ない。5年と言うのは今すぐみたいだが、技術開発では結構な年数で、それだけ実用へのハードルが高いという意味である。それに多くの場合、5年も経つと報道の読者はもはや覚えていないから、ウヤムヤになる。「あれ、どうなったっけ?」なんて聞くのは、筆者のような、昔のことをいつまでも覚えている執念深い人間に限られる。
現状で、大気中CO2から原料・燃料を合成するプロセスで上手く行っているのは「生物的炭酸固定」だけだろう。緑色植物などの「光合成」と、独立栄養細菌などの非光合成的炭酸固定の2種類あるが、量的には圧倒的に前者が多い。
光合成と言うのは、大気中CO2と水から太陽光だけで有機物を合成し、その副産物として酸素(O2)を発生する(しかも常温常圧で!)、もの凄く「有難い」反応である。我々従属栄養生物が生きていられるのは、この有機物のお陰であり、酸素呼吸できるのもこの副産物のお陰である(水を水素供与体に使わない光合成もあるが、その副産物は元素硫黄などで酸素ではない)。
故に、今の人間がまず行うべきは、緑色植物を含む生態系(森林、草地、農地など)を極力大切に維持して、将来世代に残すことである。むろん、陸だけでなく海洋も。
2. 炭素フリー水素、HTTRで大量製造へ
HTTRとは「高温ガス炉」のこと。今実用されている軽水炉と違い、減速材に黒鉛を使い作動流体にヘリウムを使う。950℃と言った高温を作れるので、高温核熱を利用する水素製造技術が注目されている。
これも以前触れたことがあるが、この場合でも、作った水素を燃やして発電燃料に使うか燃料電池に使って電力生産することになるのだから、それならば最初から高温で効率的に発電してしまう方が得だろう。熱機関は高温ほど効率が高いからである。「炭素フリー水素」なら何でも良いのか?と問う姿勢が大切である。
またこの水素を使ってCO2から燃料・原料等を作るのは、上記と同じ理屈で大損であり、その水素を直に利用する方がまだマシである。
3. CO2地下貯留、年480ヶ所必要に 50年時点目安
CO2地下貯留、年480カ所必要に 50年時点目安(日本経済新聞)
これは「人為的地球温暖化説」を全く信用していない筆者からは、論外としか言いようのない試算である。何しろ、毎年480ヶ所ずつ必要で、掘削だけで2.4兆円かかると言うから、CO2を回収し圧縮し埋め立てるまでには、一体いくらかかるんだ?となる。それで埋め立てられるCO2は2.4億トンだとのこと。つまり1tCO2に掘削費だけで1万円かかる計算。
ちなみに、日本の2018年の温室効果ガス排出量は12億4千万t-CO2でその91.7%がCO2なので11.4億t-CO2、従って2.4億トンCO2はその21%となる。つまり毎年480ヶ所ずつ掘っても2018年時点発生量の約1/5しか埋め立てられない。2050年時点なら発生量はもっと減っているだろうが、それにしても「毎年480ヶ所」なんて、持続可能なのか大いに疑問である。
日本は世界の3%しかCO2を出していない。その1/5埋め立てるのさえ、これほどまでに困難であると言う現実をしかと見つめるしかないだろう。すなわち、CCS(CO2埋め立て)と言う選択肢には実際的な効用がほとんど見込めないと言う現実である。
4. 「ブルー」も「グリーン」も・・脱炭素時代へ、湾岸産油国の水素戦略
「ブルー」も「グリーン」も…脱炭素時代へ、湾岸産油国の水素戦略(朝日新聞)
水素推進論者は、水素に「色づけ」するのが好きなようだ。この記事でもグレー・ブルー・グリーン・イエローと4種ある。
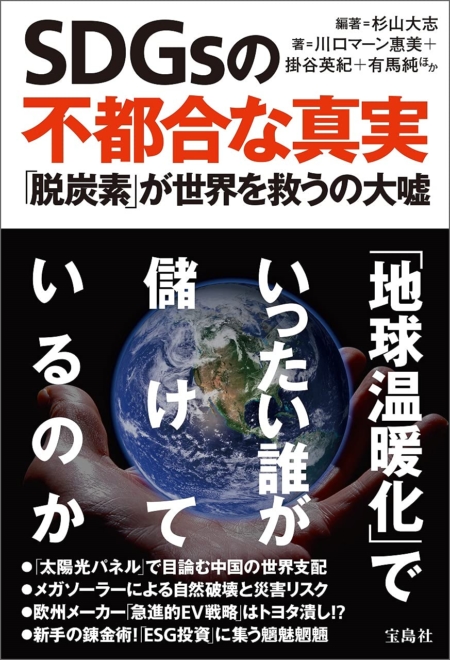 もっとも、以前に著者が書いた原稿(「SDGsの不都合な真実」所収)では、この記事での「グレー(化石燃料由来、CO2排出)」はブラック、「ブルー(化石燃料由来だがCCS併用)」をグレーと呼んでいたのであるが。「グリーン」が再エネ電力を使い水の電気分解で水素を得るのは同じである。
もっとも、以前に著者が書いた原稿(「SDGsの不都合な真実」所収)では、この記事での「グレー(化石燃料由来、CO2排出)」はブラック、「ブルー(化石燃料由来だがCCS併用)」をグレーと呼んでいたのであるが。「グリーン」が再エネ電力を使い水の電気分解で水素を得るのは同じである。
この記事ではさらに、原子力発電で水を電気分解する「イエロー」を加えているが、それならば上記HTTR由来水素も加えるべきだったろう(それは何色になるやら?イエロー+ブルーだとグリーンになってしまうけど、それはないな・・)。
これらを産油国では将来のエネルギー戦略に見立てていると言うが、ご冗談でしょう。この記事で言うグレーとブルー水素は、どちらも天然ガスが主な原資である。これを改質して水素にすると保有エネルギーが半分に減るから、エネルギー単価は2倍になる。今でさえ天然ガスは化石燃料の中で石油の次に高い。これが2倍になったら、ほぼ売れないだろう。「ブルー」だとCCSを適用するのでさらに高くなる。
天然ガスを売るのなら、水素などに転換せずそのまま売るに限る。そもそも、天然ガスを原資としていながら「脱炭素」との言い草はあり得ない。詐欺に近い。
また「グリーン」と「イエロー」は共に水の電気分解で水素を得るので、エネルギー的には完全なるロスである。電力をそのまま使うに限る。HTTRでも多分そうである。それに中東の産油国では水資源の方が貴重である。H2の分子量は2だがH2Oは18。つまり生成する水素の9倍量の水が要る。水素1万トン作るには、水9万トン要るのである(水素源として海水使用が現実的でないことは以前にも述べた)。
産油国でもどこでも、水の電気分解で作る水素は高い。記事でもグリーン水素の平均単価はブルー水素の2〜4倍とある。「ブルー」って、CCSを使って結構高くなっているはずなのに。これがブルー程度まで下がるのは2040年頃と書いてあるが、時間が経てばなぜ安くなるのか説明はない。2040年なんて先に、この記事を覚えている人間はほぼいないから、まあいいか・・?
砂漠地帯に広大な太陽電池を敷き詰め、これで水素を作れば輸出できるとの構想もあるが、まずは自国の電力需要をすべて賄って、その余力で水素を作る段取りになるはずだから、かなり先の話になる。
太陽光発電コストはまだ高いし、太陽電池が寿命を迎えた後の廃棄・リサイクルにも課題が見えつつある。膨大な量の太陽電池を作ること自体、かなり限界がありそうだ。しかも、発電したら水素などに転換せず電力としてそのまま使えば良いのである。これを輸出するなどと考えるから、無理に無理を重ねる構想になってしまう。電力は基本的に地産地消であるべきだ。
5. この世の終わりを避けるのにかかるコストの意外な安さ
この世の終わりを避けるのにかかるコストの意外な安さ ハラリ氏寄稿(朝日新聞)
世界的なイスラエルの歴史学者ハラリ氏の論説だが、これまた筆者からは科学無視の「夢物語」にしか見えない。多くの経済学者が、クリーンエネルギーへの年間投資額を世界のGDPの3%前後まで増やせば気温上昇を1.5℃に抑えることができると言っているから、結構安いんじゃないの? と言う論旨。現在、この投資は1%程度なので、あと2%程度増やせば? と言う提案をしている。
しかし、その根拠は示されていない。この中で、この1.5℃と言う値は「科学的に確固とした閾値」だが、2%は大まかな推測だと。そうかな? そもそも、この1.5℃と言う値自体が科学的根拠不明だし、これを越えたら世界の終わりだと言う説にも科学的な説得力は見出せない。
人間由来のCO2排出量が自然由来総量の5%程度に過ぎないと言う科学的知見から考えると、クリーンエネルギー投資で人間由来のCO2量を減らしたとしても、地球上のCO2収支にはほとんど影響しないと考えるのが自然なはずだが。
◇
大手マスコミには、この種の科学的根拠不明または明確な誤解に基づく論説・記事が当たり前のように載る。
エネルギーを真面目に議論するには、基本的な物理・化学・熱力学などの知識が要る。また、気温や大気中CO2などの基本データを心得る必要もある。そうした素養のないライターは、単なるデマゴギーに過ぎないと言うべきだろう。
問題は、多くの読者がそうした記事の真偽を確かめることも出来ずに、真説だと受け取ってしまうことにある。故に筆者としては、かつてドン・キホーテをたしなめた田舎娘アルドンサの言葉を繰り返すしかなくなる。
曰く「よくお見なさい・・ものを、よくお見にならなくては・・」。

関連記事
-
今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。
-
これは環境省の広域処理情報サイトのトップページにあるメッセージ。宮城県と岩手県のがれきの総量は、環境省の推計量で2045万トン。政府は2014年3月末までに、がれき処理を終わらせる目標を掲げている。
-
日本でも縄文時代は今より暖かかったけれども、貝塚で出土する骨を見ている限り、食べている魚の種類は今とそれほど変わらなかったようだ。 けれども北極圏ではもっと極端に暖かくて、なんとブリや造礁サンゴまであったという。現在では
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送している。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送した。
-
台風19号の被害は、14日までに全国で死者46人だという。気象庁が今回とほぼ同じ規模で同じコースだとして警戒を呼びかけていた1958年の狩野川台風の死者・行方不明は1269人。それに比べると台風の被害は劇的に減った。 こ
-
こうした環境変化に対応して原子力事業を国内に維持するには、個別施策の積み重ねではなく、総合的なパッケージとなる解決策を示す必要がある。その解決策として出した提案の柱の第一は、民間主導でのリプレースが行われることであり、そのための資金調達が可能となる事業環境整備である。
-
3人のキャスターの飾らない人柄と親しみやすいテーマを取り上げることで人気の、NHK「あさイチ」が原子力発電を特集した。出演者としてお招きいただいたにもかかわらず、私の力不足で議論を深めることにあまり貢献することができなか
-
国際エネルギー機関の報告書「2050年実質ゼロ」が、世界的に大きく報道されている。 この報告書は11 月に英国グラスゴーで開催される国連気候会議(COP26 )に向けての段階的な戦略の一部になっている。 IEAの意図は今
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間














