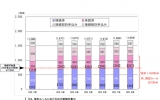チェルノブイリ原発危機の実相

diegograndi/iStock
外部電源喪失
チェルノブイリ原子力発電所はロシアのウクライナ侵攻で早々にロシア軍に制圧されたが、3月9日、当地の電力会社ウクルエネルゴは同発電所が停電していると発表した。
いわゆる外部電源喪失といって、これは重大な事故につながる起因事象である。外部電源は文字通り発電所の外から送電線で供給される。戦争状態のなかで送電線が破損したようである。戦争状態であるため、思うように送電線が復旧できないという。
外部電源は原子力発電所内の様々な機器を動かすために用いられる。そのような機器の一つに使用済み燃料プールの冷却システムがある。
福島第一に匹敵する大量の使用済み燃料
チェルノブイリ原子力発電にはRBMKという黒鉛減速沸騰水圧力管型炉が4基設置されている。いずれも電気出力の規模は100万kWである。1986年に事故を起こしたのは4号機である。1〜3号機はかねてより原子炉は停止しており運転はしていない。2000年までに全ての原子炉が停止された。今は廃炉措置の過程にある。
崩壊熱は時間とともに急速に減って行くので、20年以上たてば通常運転時の発熱量の0.1%以下に低下している。しかし、それでも発熱は続けているので冷やし続けなければならない。さもなければ、福島第一原子力発電所の4号機で懸念されたような事態になる可能性が排除しきれない。
つまり使用済み燃料プールの冷却水が加熱されて蒸発・減少して、燃料棒が水面に露出する。そうすると燃料棒が過熱して果ては溶ける可能性がある。福島第一では、コンクリートポンプ車を用いて外側から冷却水を注入し万事休す結果となった。
チェルノブイリ原子力発電の1〜3号機には大量の使用済み燃料がある。その量は福島第一原子力発電所の1〜4号機の使用済み燃料にほぼ匹敵する。
これらの使用済み燃料を冷やすためには電源が必要で、その主力が外部電源であり、バックアップとして非常用ディーゼル発電機がある。
非常用ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機は重油を燃料として使う。発電機には重油タンクが付いていて、チェルノブイリの場合は一回の給油で48時間の連続運転が可能のようである。
発電所内には補給用の大型の重油タンクがあるので、必要に応じて追加の補給をすれば良い。
ただし、ロシア軍の制圧状況が不詳なので、補給が滞りなく行えるか否かについては何とも言えない。
危機の実相
仮に非常用ディーゼルも停止して、さらに外部電源も復旧しない状態が長時間続けば、燃料が露出し最悪事態として燃料が溶け始めることもあり得る。どれぐらい長時間かといえば、その時間的目安は数週間程度と考えられる。
燃料が溶け始めれば、放射性物質が環境に漏れ出す可能性があり、欧州のみならず世界に悪影響を及ぼす可能性がある。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
-
メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい
-
小泉進次郎環境相の発言が話題になっている。あちこちのテレビ局のインタビューに応じてプラスチック新法をPRしている。彼によると、そのねらいは「すべての使い捨てプラスチックをなくす」ことだという。 (フジテレビ)今回の国会で
-
スティーブン・クーニン著の「Unsettled」がアマゾンの総合ランキングで23位とベストセラーになっている。 Unsettledとは、(温暖化の科学は)決着していない、という意味だ。 本の見解は 気候は自然変動が大きい
-
サプライヤーへの脱炭素要請は優越的地位の濫用にあたらないか? 企業の脱炭素に向けた取り組みが、自社の企業行動指針に反する可能性があります。2回に分けて述べます。 2050年脱炭素や2030年CO2半減を宣言する日本企業が
-
寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す
-
丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をしました。しかし、この発言は大きく間違っていません。除染をめぐるタブーの存在は危険です。
-
2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間