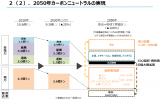米国最高裁判断は脱炭素の動きにどう影響するか?
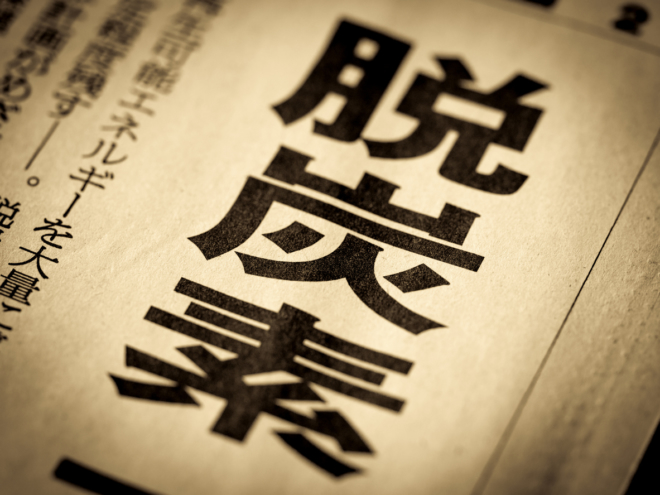
y-studio/iStock
米最高裁、発電所温暖化ガス排出の米政府規制制限
6月30日、米連邦最高裁は、「発電所の温暖化ガス排出について連邦政府による規制を制限する」判断を示した。
南部ウェストバージニア州など共和党の支持者が多い州の司法長官らは、米環境保護局(EPA)を相手取り、発電所のガス排出を規制する権限がないと主張していた。
その訴えを、最高裁が認める判断を示したということで、バイデン政権の脱炭素政策に痛手となることが予想される。これは、今後の脱炭素・ゼロエミッションの動きに対して、大きな影響を与えると考えられる。
アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)とは
アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)は、ニクソン大統領時代に設立され、1970年に活動を開始した。市民の健康保護と自然環境の保護を目的とし、大気汚染、オゾン層の保護、水質汚染、土壌汚染などが主な管理の対象として活動を行って来た。
一般に知られている活動としては、マスキー法(自動車排ガス規制)、大気浄化法(Clean Air Act of 1963)修正法などがある。
EPAの当初のミッションは、大方達成していると捉えられている。組織維持のため、1988年以降、世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により発足したIPCCなどとの連携が始まった。EPAも大気浄化法にはなかった、CO2を汚染物などと称して、温暖化政策へと走り出した。
オバマ政権下、温暖化対策として、EPAは発電所からのCO2排出基準などを設定した。例えば、IGCC(石炭ガス化複合発電)のCO2排出基準、1.4 lb/kWH = 635 g/kWhなど。
IGCCについては、三菱重工業(株)が空気/ 酸素吹きという2つの石炭ガス化技術を保有し、技術力で世界をリードしている。また、我が国の発電技術ロードマップによれば、電源開発(株)が広島大崎にてIGFCの実証試験(大崎クールジェン事業)を行っており、将来的には、発電効率55%、CO2 590g/kWhの実現を目指している。

出典:METI資料「次世代⽕⼒発電に係る技術ロードマップ 技術参考資料集」
今後の影響について
考えられる影響としては、
- 米国連邦政府の権限が制限されることにより、各州の政策がより優先される。ウエストバージニアなどの産炭州は、石炭作業従事者の意向を取り組む形の政策が打ち出される。
- バイデン政権や民主党が進めている気候変動対策、グリーン・ニューディールにブレーキが掛けられる。共和党で気候変動を重要な案件だと思っている割合は、20%程度なので、この最高裁の決定により、共和党の否定派の勢いが増すと考えられる。
- 秋の中間選挙では、民主党が大敗するという予想が濃厚であり、ますます、民主党が掲げ推進しようとして来た環境原理主義的政策は頓挫するようになる。
- ヨーロッパは、2021年から起きているエネルギー危機に対応するため、石炭火力の再稼働などを始めたが、それが暫く継続される。
ヨーロッパのいい加減さと日本
こうした中で、エネルギー、物価高、経済雇用などの問題を解決しようと、ドイツやオランダなどの気候変動推進主要国も、ロシア以外からの天然ガス調達先を模索したり、石炭火力を稼働させたり、原子力に目を向けるなど、大幅な方向転換を行っている。
6月19日ドイツのハベック経済相は、ロシアからの供給削減による電力不足が懸念される中、発電用の天然ガスの使用を制限し、その解決策として石炭火力を増やすと発表した。
2015年に採択されたパリ協定、それによる脱炭素、ゼロエミッション、炭素中立などの動きも、一旦お蔵に閉じ込めて、急場を凌ごうという考えのようだ。
ヨーロッパの動きを「国際情勢に即した柔軟な動きだ」と評価する人がいる。逆に、「どうにでも変わる。思想や哲学があるようで、やっていることから判断すれば、そういう高尚なものはなく、矛盾だらけ。自分の都合の良い理屈を並べ、他に強制する。やっていることは、植民地時代の発想ではないのか」といった声も聞かれる。
そもそも、CO2は汚染物ではないのだし、炭素は、すべての「生きとし生けるもの」に不可欠な元素である。「脱炭素という概念自体、基本的に欠陥概念である」という人も、世界ではかなり増えてきている。
6月22日、G7の結果を受けて、日本は、バングラデシュとインドネシアで進めていた2つの石炭火力発電プロジェクトの支援を中止するというニュースが流れた。
日本が中止すれば、中国が入って来て、SOx、NOx、粉塵などを排出する安価なプラントを建設する。発注元の仕様を満たすことができず、それでていて、中国の影響力だけ強まるというのであろうか。
我が国も、「省エネポイント、屋上ソーラーパネル設置」などではなく、ヨーロッパのいい加減さを見倣った方が良いのかもしれない。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。 今回のテーマは「アメリカの環境政策と大統領選挙」です。 アメリカではグリーン・ニューディールという大胆な地球温暖化対策が議会に提案され、次の大統領選挙とからんで話題にな
-
賛否の分かれる計画素案 本年12月17日に経産省は第7次エネルギー基本計画の素案を提示した。27日には温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が
-
猪瀬直樹氏が政府の「グリーン成長戦略」にコメントしている。これは彼が『昭和16年夏の敗戦』で書いたのと同じ「日本人の意思決定の無意識の自己欺瞞」だという。 「原発なしでカーボンゼロは不可能だ」という彼の論旨は私も指摘した
-
総選挙とCOP26 総選挙真っ只中であるが、その投開票日である10月31日から英国グラスゴーでCOP26(気候変動枠組条約第26回締約国会議)が開催される。COVID-19の影響で昨年は開催されなかったので2年ぶりとなる
-
バイデン政権は温暖化防止を政権の重要政策と位置づけ、発足直後には主要国40ヵ国の首脳による気候サミットを開催し、参加国に2050年カーボンニュートラルへのコミットや、それと整合的な形での2030年目標の引き上げを迫ってき
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表され
-
気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき
-
菅首相の16日の訪米における主要議題は中国の人権・領土問題になり、日本は厳しい対応を迫られると見られる。バイデン政権はCO2も重視しているが、前回述べた様に、数値目標の空約束はすべきでない。それよりも、日米は共有すべき重
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間