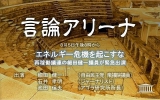EUの野心と悩み

PeskyMonkey/iStock
3月上旬に英国、ベルギー、フランスを訪問し、エネルギー・温暖化関連の専門家と意見交換する機会があった。コロナもあり、久しぶりの欧州訪問であり、やはりオンライン会議よりも対面の方が皮膚感覚で現地の状況が感じられる。
ウクライナ戦争とEU
EUは2022年5月に「REPowerEU」を掲げ、ロシアへの化石燃料依存からの脱却を進めている。それにとどまらず、中長期に、脱炭素化(グリーン)をさらに加速しようとしている。EUにとってのエネルギー安全保障の軸は脱炭素であり、RePowerEUはフォンデアライエン委員長の施策の1丁目1番地的位置づけとなっている。
EU域内ではウクライナ戦争を契機に再エネへのスイッチへの支持が更に高まっており、改正再エネ指令において再エネのエネルギー供給に占めるシェアを40%から45&に引き上げ、これに伴い、EU委員会はパリ協定の下での国別目標を90年比▲55%から▲57%に引き上げることを提案している。
2022年6月中旬よりロシアはEU向けのガス供給を大幅に制限。その結果もあり、40%を超えていたガスのロシアへの依存度は、10月時点では7.5%程度に低下した。価格高騰による需要減、ロシア以外からのLNG輸入の増強や暖冬傾向もあって、ガス貯蔵率はEU全体で2023年2月末時点で6割程度となり、ガス非常事態は防ぐことができた。
他方、昨年の貯蔵率増加にはロシアガスを活用していること、中国の景気回復等により世界のガス需要が増える可能性が高いことから、2023-4年冬のガス不足への対応は引き続き課題である。
EU域内のエネルギー価格は、2021年夏から上昇を続け、ウクライナ侵攻後さらに高騰したが、昨年から今年にかけての暖冬傾向による需要減や貯蔵量の増加により価格高騰は落ち着いている状況にある。しかし上記のような世界のガス需要の動向、ウクライナ戦争の動向如何によって再び価格が高騰する可能性はある。
ウクライナ戦争は長期化するという見通しが関係者の間では支配的であった。ロシア軍が支配地域を拡大することも困難だし、ウクライナ軍が奪還することも困難だからだ。加えてウクライナ国内ではクリミア奪還が政治的にマストとなっており、ロシアとの手打ちができない状況にある。ウクライナ国内には戦争終結機運はなく、他方、ロシア国内でのプーチン支持は盤石なようである。
上述のようにEUは対ロシアガス依存のみならず、化石燃料依存全体から脱却しようとしているため、時間がたてばたつほど、ロシアがエネルギーを政治的武器に使う有効性が低下する。EUがウクライナへの武器支援を強める中でロシアが短期的に天然ガスを政治的武器に使う可能性もあるが、EUはロシアガスが完全に止まる場合も想定して対策を講じているとのことである。
EUの抱えるジレンマ
ウクライナ戦争等による石油、ガス、電力料金上昇に直面してもEU域内において脱炭素政策に対しては幅広い政治的支持がある。2022-23年の冬を大過なく乗り切り、かつエネルギー需要、電力需要の低下、再エネのシェア上昇もあったことからRePower EUが機能しているとの自信を深めている模様である。
他方、EUがかかえるジレンマもある。第一に2022年8月に成立した米国のインフレ抑制法(Inflation Reduction Act: IRA)に対する危機感である。
IRAで提供されるインセンティブが巨額であり、EUに比べてエネルギーコストが安く、カーボンプライシングもない米国にグリーン残業の基盤がシフトしてしまう可能性がある。
例えばフォンデアライエン委員長は2022年12月にIRAの有する「バイ・アメリカン」のロジックや補助金競争の可能性について懸念を表明している。このことが2023年2月1日、EU委員会は「グリーン・ディール産業計画」(Green Deal Industrial Plan)の発表、3月の「ネットゼロ産業法」(Net-Zero Industry Act)の提案につながっている。
特にこれまで厳しく管理されていた加盟国の国家補助ルールを、EU全体の競争力向上のために緩和する議論が起きていることは注目される。ルール緩和により国家補助を拡大する経済余力のある独仏と、それ以外の国で路線対立が生じている。
第二にグラスゴー合意以降の世界の排出動向(2021年、2022年と連続で過去最高を更新)を見れば、EUがいくら頑張っても、2030年▲45%、2050年全球カーボンニュートラルが不可能であることは誰の目にも明らかであることだ。
EUにとって1.5℃目標は今や宗教のようなものであり、いかに実現可能性がなくとも、これを見直したり、断念したりすることを口に出せる状況ではない。欧州で高コストの温暖化政策に疑問を差しはさむコメントをすると「ファシスト」的な扱いを受けるという話を聞いた。これはプラグマティックな政策論議を阻むものである。
例えば現在のエネルギー危機に対応するために化石燃料投資、特にガス投資が必要であることは自明であるが、政策担当者がそれをオープンに言えない「空気」が支配的である。他方、BP、シェルといったEUメジャーは既存油田・ガス田投資だけでは不十分ということはわかっており、注意深い言い回しながら、新規油田・ガス田投資の必要性に言及しはじめている。
第三に2050年全球カーボンニュートラルに決定的な影響を与えるのは先進国ではなく、中国、インド等の途上国であるが、彼らは温暖化防止をトッププライオリティにおらず、欧米先進国がそれに対する有効なレバレッジを有していないことだ。EUが導入する炭素国境調整措置(CBAM)の一つの目的は新興国の行動を促すことにあるが、中国、インドはCBAMが枠組み条約に反発を強めており、CBAMが彼らの政策変更につながる可能性はほとんどない。
EUが1.5℃目標へのコミットメントから野心レベルを引き上げ、域内エネルギーコストが上昇すれば(CBAMの導入はEU域内の物価上昇をもたらす)、片やエネルギーコストの安い米国とのグリーン産業競争上、不利となり、片や中国等、温暖化目標と心中するつもりのない新興国とのレベル・プレイイング・フィールドが更に失われる。
こうした状況にEU域内の産業がどこまで持ちこたえられるのだろうか。

関連記事
-
エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい
-
さて、繰り返しになるが、このような大型炭素税を導入する際、国民経済への悪影響を回避するため、税制中立措置を講じることになる。
-
先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本
-
今度の改造で最大のサプライズは河野太郎外相だろう。世の中では「河野談話」が騒がれているが、あれは外交的には終わった話。きのうの記者会見では、河野氏は「日韓合意に尽きる」と明言している。それより問題は、日米原子力協定だ。彼
-
福島原発事故で流れ出る汚染水への社会的な関心が広がっています。その健康被害はどのような程度になるのか。私たちへの健康について、冷静に分析した記事がありません。
-
政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間