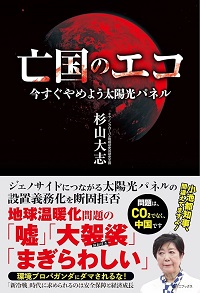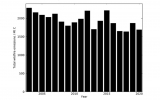食料安全保障の脅威は台湾有事より気候変動なのか

wildpixel/iStock
政府「不測時における食料安全保障に関する検討会」のとりまとめが発表された。
その内容は、不測の事態によって食料が不足するときに、政府が食料の配給をしたり、価格を統制したり、コメやサツマイモなどの高カロリーの作物への生産の転換を促す、といった内容だ。
確かにこれ自体は必要なことだが、「不測の事態」の認識がどうもおかしい。
「とりまとめ」を読むと、不測の事態のトップになっているのが「気候変動による食料生産への影響」である。
たしかに旱魃(かんばつ)で作物に被害が出ることはある。だが旱魃が「人為的な気候変動のせい」で起きたと証明されたことなど無い。
IPCCの報告を見ても、旱魃については、極めてCO2排出量が高く推移したとしても2100年に至るまで人為的な影響は自然変動と区別できない、となっている。つまり旱魃が起きるとしても誤差の内なのだ。洪水についても同様で、IPCCを信じても、2050年に至るまでは人為的な影響は自然変動と区別できず、誤差の内、となっている。
その一方で、「とりまとめ」では、「地政学的な情勢の不安定化」についてはごく短く触れているだけだ。引用すると「地政学的な情勢の不安定化は、輸入依存度の高い我が国の食料供給に深刻な影響を及ぼす可能性がある。」これだけだ。
だがこれで大丈夫か? 台湾有事が迫っている。日本周辺の海域も安全な航行が出来なくなるかもしれない。すると食料輸入もエネルギー輸入もストップしてしまう。
いくら食料を配給したり、作物の転換をすると言っても、そもそも配る食料がなくなる。エネルギーが輸入できなければ、作物の転換といっても生産すらできず、また食料の輸送もできない。冷蔵も冷凍も使えないので食料は腐ってしまう。
台湾有事まで考えれば、飢えないために必要なことは、まずは玄米などの食料を充分に備蓄することであり、またエネルギーの備蓄である。
だが今回の政府「とりまとめ」では、そもそも台湾有事は「想定外」、シーレーンの遮断も「想定外」、食料だけでなくエネルギーが同時に不足することも「想定外」のようだ。
これで「不測時における食料安全保障」になっているのだろうか。国民が飢え死にすることは避けられるのか。
■

関連記事
-
報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。 この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ
-
政府のエネルギー基本計画はこの夏にも決まるが、その骨子案が出た。基本的には現在の基本計画を踏襲しているが、その中身はエネルギー情勢懇談会の提言にそったものだ。ここでは脱炭素社会が目標として打ち出され、再生可能エネルギーが
-
NHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦(1月9日放映)」を見た。一部は5分のミニ動画として3本がYouTubeで公開されている:温暖化は新フェーズへ 、2100年に“待っている未
-
チェルノブイリの現状は、福島の放射能問題の克服を考えなければならない私たちにとってさまざまな気づきをもたらす。石川氏は不思議がった。「東さんの語る事実がまったく日本に伝わっていない。悲惨とか危険という情報ばかり。報道に問題があるのではないか」。
-
米国の国家安全保障戦略が発表された。わずか33ページという簡潔な文書である(原文・全文機械翻訳)。トランプ政権の国家安全保障に関する戦略が明晰に述べられている。 筆者が注目したのは、エネルギー、特に天然ガスなどの化石燃料
-
24日、ロシアがついにウクライナに侵攻した。深刻化する欧州エネルギー危機が更に悪化することは確実であろう。とりわけ欧州経済の屋台骨であるドイツは極めて苦しい立場になると思われる。しかしドイツの苦境は自ら蒔いた種であるとも
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間