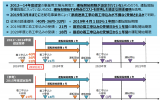ドイツ総選挙とエネルギー温暖化政策

Evgeny Gromov/iStock
2月のドイツ総選挙においてフリードリッヒ・メルツ氏が率いるCDU/CSU(キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟)が勝利(得票率2021年時24.2%→28.5%)を収める一方、現政権を構成するSPD(社会民主党)(25.7%→16.4%)、緑の党(14.7%→11.6%)は大幅な議席減となった。
極右とされるAfD(ドイツのための選択肢)は得票率を倍増させ(10.4%→20.8%)、第二党に躍進した。他方、FDP(自由民主党)、BSW(サラ・ヴァーゲンクネヒト同盟)は議席獲得に必要な5%ラインを越えることができなかった。
CDU/CSUは第一党になったとはいえ、単独では政権を運営できないため、連立相手を探さねばならない。メルツ氏は「AfDとの連立は絶対にありえない」との「ファイアーウオール」を設定しており、連立の選択肢はSPDとの大連立、もしくはSPD、緑の党との三党連立に限られる。
メルツ氏はSPDとの大連立協議を進めており、現時点で緑の党が次期政権に入る可能性は低い。メルツ氏は「ドイツおよびEUが直面する数多くの国内および国際的な課題に対処するためには、欧州最大の経済大国であるドイツが可能な限り迅速に意思決定のできる政府を樹立する必要がある」と述べ、復活祭(4月)までに連立政権樹立を目指すとしている。
選挙期間中のエネルギー温暖化に関する各党の公約は以下のとおりである
- CDU/CSU:カーボンプライシングを重視。電力税、送配電料金を引き下げ、原発再開を検討し、次世代炉の研究開発を推進。
- AfD:気候保護のための政策や税を拒否。パリ協定からの離脱。
- SPD:地域暖房網の構築(個別にヒートポンプを設置するよりも効率的で費用対効果が高い)。 原発は廃止済みであり、再開検討は不要。放射線物質の最終処分を支持。
- 緑の党:2030年までに石炭火力を廃止。原発回帰は不可。
緑の党が連立政権に参加しなければ、メルツ新政権が前政権以上に野心的なエネルギー・温暖化政策を追及することはなさそうだ。むしろ効果的な気候対策と経済の安定性および市民の支払い能力を両立させることが最大の課題となる。
とはいえ、新政権は2045年までに温室効果ガス排出量を正味ゼロ、暫定目標として2030年までに65%削減との前政権の目標は堅持すると言われている。また気候変動対策奨励金制度や、市民や企業を救済するための送電利用料の削減やすべての部門における再生可能エネルギーの拡大等においては両党のポジションに違いはない。
連立協議におけるエネルギー温暖化関連の論点としては、第一に債務ブレーキの調整がある。気候変動対策、インフラ、防衛等、多くの分野で莫大な投資ニーズがある一方、新規借り入れについては憲法上の上限があり、エネルギー転換を進めるためには債務ブレーキを調整するためのメカニズムに合意せねばならない。SPDは債務上限の改革を強く主張しているのに対し、CDU/CSUは民間投資家に強力なインセンティブを与えるべきであるとして債務上限の見直しに否定的であった。
トランプ政権の下で米国のウクライナ戦争への関与方針が大きく変わり、欧州において防衛費増強へのドライブがかかる中、3月初め、両党は防衛費については債務ブレーキの対象から除外することに合意した。防衛はさまざまなセクター絡むため、エネルギー転換関連支出の一部も債務ブレーキの適用除外になる可能性もある。
第二に暖房法の見直しだ。前政権が導入した化石燃料による暖房システムの段階的廃止については消費者の負担が大きく、国民からの不満が強い。CDU/CSUは選挙戦において消費者の選択を制約する同法の廃止を公約している。
第三に内燃機関エンジン自動車の販売規制だ。CDU/CSUは2035年に内燃機関エンジンの新車販売を禁止するというEUの目標を拒否している。SPDは目標堅持を支持してきたが、経済成長の低迷、労働者の解雇、ドイツ全土での自動車工場の閉鎖が迫る中、労働組合や国内自動車産業の支持を得るため妥協を迫られるだろう。
ドイツの石炭火力は遅くとも2038年までに段階的に廃止される予定であるが、緑の党が主張するような目標年限の前倒しには両党ともに否定的だ。メルツ氏は、電力供給の安全性が保証されるまでは石炭火力発電所の閉鎖は行わないと明言している。
連立協議において原子力発電をめぐって議論が対立する可能性は低い。CDU/CSUは2024年4月に運転停止した3基の原発が技術的にも財政的にも妥当なコストで再び稼働できるかどうかを検討したいとしているが、事業者や研究者はその可能性やメリットに疑問を呈しており、実現する可能性は高くない。
前政権を構成していた中道左派(SPD)、緑の党が敗北し、中道右派(CDU/CSU)、極右(AfD)が躍進するという選挙結果であったが、AfDを排除した結果、エネルギー温暖化政策は前政権と大きく変わらないものになるだろう。
非現実的とも思える脱炭素目標を見直さなければ、ドイツ国民、産業が苦しんでいるエネルギーコスト問題の根本的解決にはならないだろう。CSD/CSUとSPDの大連立で移民問題、エネルギーコスト問題等、国民の不満の強い様々な問題が改善しなければ、次の選挙ではAfDが更に議席を伸ばすこととなり、遅かれ早かれAfDの政権参加が実現するとの見方もある。
ドイツのエネルギー温暖化政策が本当に変わるのはその時かもしれない。

関連記事
-
先日、COP28の合意文書に関する米ブライトバートの記事をDeepL翻訳して何気なく読みました。 Climate Alarmists Shame COP28 into Overtime Deal to Abandon F
-
2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
朝日新聞に「基幹送電線、利用率2割 大手電力10社の平均」という記事が出ているが、送電線は8割も余っているのだろうか。 ここで安田陽氏(風力発電の専門家)が計算している「利用率」なる数字は「1年間に送電線に流せる電気の最
-
ウォール・ストリート・ジャーナルやフォーブズなど、米国保守系のメディアで、バイデンの脱炭素政策への批判が噴出している。 脱炭素を理由に国内の石油・ガス・石炭産業を痛めつけ、国際的なエネルギー価格を高騰させたことで、エネル
-
総裁候補の原発観 今の自民党総裁選をリードしているとされる河野太郎氏は、〝原発再稼働容認に転換〟とも伝えられたが注1)、今も昔も強烈かつ確信的な反原発の思想の持ち主である。河野氏の基本理念は核燃料サイクル注2)を止めるこ
-
去る10月22日に経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に関して、同法に基づく価格決定ルールの運用変更案を定めた省令、告示のパブリックコメントを開始した。この改正内容のう
-
福島原発事故で流れ出る汚染水への社会的な関心が広がっています。その健康被害はどのような程度になるのか。私たちへの健康について、冷静に分析した記事がありません。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間